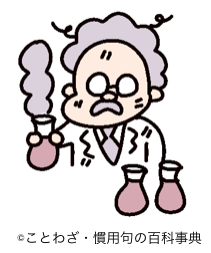ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。
ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。
「二度あることは三度ある」と庶民の生活感覚
ことわざでは「二度あることは三度ある」といいますが、本当でしょうか。
文字どおりには、(同じようなことが)二度あったら三度あるということですが、実際には、そうならないこともあるのは皆さんもご存じでしょう。それなのに、なぜ、昔から「二度あることは三度ある」といい、いまも多くの人がこのことわざを口にしたり思い浮かべたりするのでしょうか。
その原因の一つは、ことわざの好む表現法(レトリック)です。ことわざは、基本的に断定形で終わります。「二度あることは三度ある」と言いきって、印象を強めているのです。実際は三度はない場合があっても、「二度あることは三度あることもあるし、ないこともある」とか、「二度あることは三度あるかもしれない」といったのでは、ことわざらしく感じられませんね。
もう一つ、ことわざが簡潔な表現で、くわしい説明をしないことも挙げてよいでしょう。ことわざは、使われる場面や状況と密接に結びついているのですが、どんなケースに使われるのか、ことわざ自体は何も語らないことが多いのです。
このことわざの場合、用例をみると、おおむね好ましくないことや不吉なことが二度つづいて、三度目が起こる予兆(きざし)として警戒する場合が多いといえるでしょう。(勝負事などで、二つ勝って次もまた勝てる〔勝った〕というときにも使えますが、ことわざの用法としてはかなり軽く、副次的なものです。)
谷崎潤一郎の名作『細雪』には、次のような用例がありました。
◆たまたま今度の見合いの場所が東京と云う廻り合せになったので、何となく幸先(さいさき)が悪いような気がし、東京では又ロクでもないことが起るのではないか、二度あることは三度である、と云うような予感がしないではなかった〈略〉
大阪船場の蒔岡家の次女幸子の回想で、妹(三女)雪子の見合いのために妹たちと上京した折に、過去に東京に来るとなぜか心配事が生じたことが二度あったのを思い出し、縁談の行く末に一抹の不安をいだいたことを述べています。
この予感ははからずも的中し、雪子の縁談は破談になります。「東京」と「ロクでもないこと」を結びつけるのは論理的でなく、直感によるものです。しかし、嫌なことが二度続いたときに、その二つに共通する背景として「東京」に思いあたり、妹の将来を案じるのは姉として当然の心理でしょう。
一般に、二度あったから三度目がかならず起こるわけではないにしても、重大な結果になりかねない場合は、三度目がありうると思って身構えるのは人としてごく自然な反応です。「三度ある」というのは、三度あると思って恐れ、そのリスクに備える必要を強調したものと受け取ってよいと思います。
ところで、現代では「二度あることは(かならず)三度ある」と信じるのは、俗信あるいは迷信ということになりますが、笑ってすまされない場合もあります。たとえば、同じ年に同じ家で二人が亡くなったようなケースです。
少し重い話になりましたが、そんなとき昔の人は、ことわざを引いて三度目の災厄を避けるために、二人目の死者を葬るときににその隣に藁人形や木槌などを三人目の死者の代わりに埋葬しました。二人の故人をとむらい、これ以上の禍を避けるために区切りをつけ、精神的なバランスを取り戻すことにつながっていたものでしょう。この風習は多くの地方で確認されていて、一部では近代までのこっていました。
他方で、醤油などを二度こぼしたときに、三度目の大きな被害をまぬがれるために、わざともう一度ほんの少しこぼすようなことも行われていました。今日では理解しがたい、ちょっとユーモラスな光景ですが、ことわざが庶民の日常生活にそれだけしっかり根づいていたことがうかがわれます。
このことわざは、文献の上では18世紀後期が初出とされていますが、こうした習俗を視野に入れると、さらに数世代前、あるいはもっと古い時代から庶民の間で使われていたと推定され、かつては庶民の生活感覚の一端を占めていたといっても過言ではない、と私は考えています。(2025/2/5)
©2025 Yoshikatsu KITAMURA
【北村孝一先生のその他のコラム記事】
多くのことわざ資料集を監修し、『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館、2012)を編纂・監修した。後者を精選しエッセイを加え、読みやすくした『ことわざを知る辞典』(小学館、2018)も編んでいる。視野を世界にひろげ、西洋から入ってきた日本語のことわざの研究や、世界のことわざを比較研究した著書や論考も少なくない。近年は、研究を続けるほか、〈ミニマムで学ぶことわざ〉シリーズ(クレス出版)の監修や、子ども向けの本の執筆にも取り組んでいる。
主な編著書
『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館)、『ことわざを知る辞典』(小学館)、『世界のふしぎなことわざ図鑑』(KADOKAWA)、『ミニマムで学ぶ 英語のことわざ』(クレス出版)、『ことわざの謎 歴史に埋もれたルーツ』(光文社)、『世界ことわざ辞典』(東京堂出版)、『英語常用ことわざ辞典』(武田勝昭氏との共著、東京堂出版)など。
北村孝一公式ホームページ
ことわざ酒房(http://www.246.ne.jp/~kotowaza/)