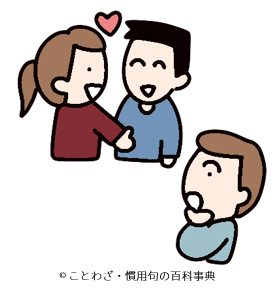大島中正(おおしま ちゅうせい)先生
縁は異なもの。味なもの。
「~ハ」のピリオド越え・名詞が形容詞の用法をもつようになること
今回は、「縁は異なもの。味なもの。」 ということわざを材料にして日本語学のトピックを2つとりあげることにします。
一つめは、「縁は」の部分を主題部とし、つづく「異なもの。」および第2文の「味なもの。」のいずれをも叙述部と称することにするならば、「縁は」は、第1文の主題部でもあり、つづく第2文の主題部でもあるというトピックです。2文いずれにもそれぞれの主題部を明示すると、
- 縁は異なもの。
- 縁は味なもの。
ということになります。
ことわざとしても「縁は異なもの。縁は味なもの。」と表現できないわけではありませんが、主題部「縁は」がくりかえされると、日本語を母語とする者は、ある種のしつこさを感じてしまうのではないでしょうか。
②の「縁は」が省略されていれば、しつこくなくなるばかりでなく、①②の2文が緊密につながっているという感じがするようにおもえます。いかがでしょうか。
三上章(1903-1971)は、その著作『象は鼻が長い』で、「Xハ」に「ピリオドを越える底力(三上章1960:119)」をみとめています。
たとえば、夏目漱石の小説『吾輩は猫である』の冒頭の主題部「吾輩は」が、つづく4つの文の共通の主題部でもあること、つまり「~ハのピリオド越え」という文法的現象が生じていることを指摘しています。原文の一文一文に共通の主題部「わが輩」を明示したものを次のように提示しています。
わが輩(に)は、名前はまだない。
わが輩は、どこで生まれたか見当がつかぬ。
わが輩は、何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いて居丈は記憶して居る。
このほかに、川端康成や太宰治の小説などからも類例が提示されています。読者の皆さんも、「~ハのピリオド越え」の実例をさがしたり、自分で用例を、ぜひつくってみてください。
2つ目は「味なもの」にみえる「味な」という形容詞についてです。「味」と同様、「現金」「罪」等の名詞が「―な」という形式にささえられて形容詞の用法をもつという現象です。村木新次郎(2012:245)につぎのような実例があげられています。
- 文面を見るなり気分が晴れ、同時に味な企画だと感心した。(朝日新聞04.01.13)
- 最も多かったのは、「愛より現金が欲しい!」という現金な調査結果だった。(朝日新聞99.03.02 )
- そう思うと、W杯はパーフェクトを求める罪な大会なのかもしれない。(朝日新聞02.06.20)
村木新次郎(2012)に収録の論文「「神戸な人」という言い方とその周辺」は、「神戸な人」「味な企画」「大人なイメージ」「現実な対応」「メルヘンな雰囲気」「普通な 感じ/気分」「花の都」「がけっぷちの経済」「底抜けな/底抜けの 明るさ」といった言い方がとりあげられています。現代日本語における名詞と形容詞について、実例にもとづく記述がなされています。
「縁は異なもの。味なもの。」とおなじように、「~ハ」のピリオド越えのみえることわざは他にあるでしょうか。また、「味な」のように「―な」という形式にささえられて名詞が形容詞の用法をもつようになった単語がみえることわざは、あるでしょうか。
今回は、日本語の構文の根幹にかかわる「~は」の問題および品詞に関係する問題を紹介しました。三上章、村木新次郎(1947-2019)両氏の遺著は、いずれも日本語学の重要な文献です。日本語学にご関心をおもちの方にはおよみになることをおすすめします。
大島中正【著】
村木新次郎(2012)『ひつじ研究叢書<言語編>第101巻 日本語の品詞体系とその周辺』ひつじ書房
【大島中正先生のその他のコラム記事】
- ことわざで「日本語再発見」(第1回)ことわざの中の「ひと(人)」
- ことわざで「日本語再発見」(第2回)ことわざの文型「名詞1は名詞2。」
- ことわざで「日本語再発見」(第3回)文型「名詞1が 名詞2と なる」