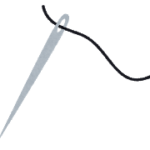この記事を書いた人
北村孝一(きたむら よしかつ)先生

ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。
“好きこそ物の上手なれ” の眼差(まなざ)し
(好きこそ物の上手なれ)
今回取り上げる「好きこそ物の上手なれ」は、皆さんも耳にしたことがあるでしょう。
趣味でも仕事でも、好きなことが大切で、好きであってこそ上手になる。いまは下手(へた)でも、ほんとうに好きなら大いに上達する望みがある、ということです。初心者やなかなか上達しない人にとっては、とても温かく励みになることわざですね。
しかし、ただ温かいばかりでなく、見方によっては、なかなか厳しいことばともいえます。器用なだけではダメで、稽古熱心だけでも大成はしないとも受け取れるのです。
なんとなくわかるけど、ちょっと古くさく、あまりよくわからないという人もいるでしょう。わからないのも無理はありません。「~こそ~なれ」という、いまではふつう使われない“係り結び”が出てくるからです。
ここでは、係り結びの文法的説明には深入りしませんが、「~こそ」と強調したとき、これを受ける「~なり」の語尾が已然形(いぜんけい)の「なれ」になることを頭の隅に入れておいてください。「好きこそ物の上手」という言い方もしますが、現代でも「好きこそ物の上手なれ」と言う人のほうが多く、それだけ印象深い形ともいえるでしょう。
ことわざでも滅多に使わない係り結びですが、「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」にも顔を出しています。後者の場合も、「こそ」があるので「あり」が「あれ」になっていますね。
話を本題にもどすと、「好きこそ物の上手なれ」は、「好き〔な人〕は物の上手なり」を強調したもの、と受け取ってよいことになります。
この「物の」は、「物のはずみ」のように、漠然として、さほど意味のないことばです。「上手」は、かつては「名人上手」と続けて言うことも多く、現在の上手のニュアンスと微妙に異なり、名人に次ぐ優れた技量の人を敬意を込めて呼ぶことも少なくありませんでした。
でも、好きな人こそ(本当に)上手な人だというのは、どういうことでしょうか? たとえば、楽器をひくのは大好きだけれど、まだ習いはじめたばかりで自分でも下手だと思っている人もたくさんいることでしょう。
この表現には、ことわざ特有の誇張があり、また文字どおりに受け取ると、論理的にはいくぶん飛躍があることも否定できません。いったい、どういうことなのか、このことわざがひろく使われるようになった江戸時代にさかのぼって考えてみましょう。
このことわざ(異形を含む)の初出は、俳人宝井其角(たからいきかく、1661~1707)の十七回忌に編まれた『其角十七回』(1746)で、次のように書かれています。
「器用さとけいことすきと三つのうちすきこそものの上手なりけれ」と口ずさみせられけるが、将棋の宗匠(そうしょう)宗桂もこの狂歌を折りふしず(誦)しられけるとぞ
(其角は「器用さと稽古と好きと三つのうち好きこそものの上手なりけれ」と口ずさんでいらしたが、将棋の宗匠大橋宗桂も折にふれ同じ狂歌を口にされていたという)
大橋宗桂の名は江戸幕府が公認した将棋所の初代名人が始まりで、其角の時代には五代目が活躍していました。「狂歌」は、滑稽味やユーモアのある和歌のことですが、ここでは、花鳥風月ではなく人間や社会を題材とする和歌をさしています。
この狂歌のいわんとするところは、芸道の名手となる上で、「器用さ」(生まれもった素質)と「稽古」と「好き」を比べてみると、いずれも大切に違いありませんが、最後の「好き」なことこそ最も肝心な要件だ、ということです。この狂歌をガイドにして、ことわざを見直すと、ことわざの隠れた文脈が浮かんでくるように思われ、とてもわかりやすくなります。
この狂歌が、其角の時代に俳句だけでなく、ジャンルの異なる将棋の世界でも名人の共感を呼んでいたわけですが、浄瑠璃や歌舞伎にも類似の表現が見出せます。《菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)》(1746)に、「上根と稽古と好きと三つの中(うち)好きこそ物の上手とは芸能修行教えの金言」とあり、「上根」は生まれつきの能力のことなので、手習い(書道)についても同じようなことが言われていたようです。
ことわざは、狂歌の内容を極限まで削って短縮する一方で、結論を誇張した表現とみてよく、だからこそ、いっそう印象深い表現となっているといってよいでしょう。そして、その背後には、宝井其角や大橋宗桂などの芸道の第一人者による深い洞察力と、後進の者への厳しくも温かい眼差しが感じられるのではないでしょうか。
©2024 Yoshikatsu KITAMURA
【北村孝一先生のその他のコラム記事】
北村孝一(きたむら よしかつ)先生
多くのことわざ資料集を監修し、『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館、2012)を編纂・監修した。後者を精選しエッセイを加え、読みやすくした『ことわざを知る辞典』(小学館、2018)も編んでいる。視野を世界にひろげ、西洋から入ってきた日本語のことわざの研究や、世界のことわざを比較研究した著書や論考も少なくない。近年は、研究を続けるほか、〈ミニマムで学ぶことわざ〉シリーズ(クレス出版)の監修や、子ども向けの本の執筆にも取り組んでいる。
主な編著書
『故事俗信ことわざ大辞典』第2版(小学館)、『ことわざを知る辞典』(小学館)、『世界のふしぎなことわざ図鑑』(KADOKAWA)、『ミニマムで学ぶ 英語のことわざ』(クレス出版)、『ことわざの謎 歴史に埋もれたルーツ』(光文社)、『世界ことわざ辞典』(東京堂出版)、『英語常用ことわざ辞典』(武田勝昭氏との共著、東京堂出版)など。
北村孝一公式ホームページ
ことわざ酒房(http://www.246.ne.jp/~kotowaza/)
 ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。
ことわざ研究者(ことわざ学会代表理事)。エッセイスト。学習院大学非常勤講師として「ことわざの世界」を講義した(2005年から断続的に2017年3月まで)。用例や社会的背景を重視し、日本のことわざを実証的に研究する。