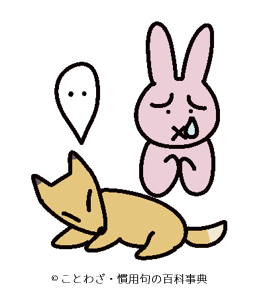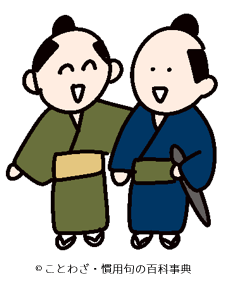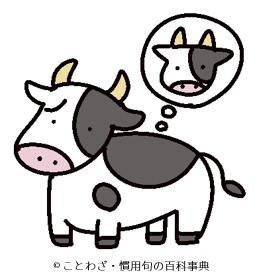目次
「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」の意味(出典)

【ことわざ】
文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり
【読み方】
ぶんしんぜにをあいせず、ぶしんしをおしまざればてんかたいへいなり
【意味】
文官は潔白で金銭への欲を断ち、武将は国のために死を恐れずそれぞれの職分を守れば、世の中は平和になるということ。


みんながちゃんと自分の仕事をすることが、ええ国をつくる秘訣やな。
【出典】
「宋史」
「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」の解説

「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」という言葉は、国を治める上で文官と武将がそれぞれの役割を正しく果たすことの重要性を表しているよ。
このことわざではね、文官(政府の役人や知識人)がお金を欲しがらないで潔白であること、そして武将(軍の将軍や兵士)が国のために自分の命を惜しまない勇気を持つことが、国が平和で安定するために必要だと教えているんだ。
例えばね、文官がお金に汚れずに正直に仕事をすると、政府は公正で信頼されるようになるんだ。一方で、武将が自分の命を惜しまずに国を守ることで、国の安全が守られるんだよ。
この言葉は、それぞれの人が自分の職責を全うすることで、全体としての社会がうまく機能し、平和が保たれるという教えを含んでいるんだね。だから、「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」と言うわけだよ。
「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」の使い方




「文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なり」の例文

- この国は、文臣が銭を愛せず、武臣が死を惜しまないため、長い間平和を享受している。まさに文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なりの理想を体現している。
- 歴史を振り返ると、多くの混乱期がありましたが文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なりという考え方が徹底された時代は、国が安定し、発展してきたことがわかります。
- 政治家たちは文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なりという言葉を引用しながら、自らもその精神に則って行動することを誓った。
- 会議で一人の老政治家が立ち上がり、文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なりと述べ、現在の政治の腐敗を批判した。
- 教科書には、文臣銭を愛せず、武臣死を惜しまざれば天下太平なりという古言が引用されており、学生たちはその意味と重要性を学ぶことになる。