「風樹の嘆」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)
【ことわざ】
風樹の嘆
【読み方】
ふうじゅのたん
【意味】
親孝行をしようと思い立った時には、すでに親は亡くなり孝養をつくすことができないなげき。


だから、今できることはその時にしっかりやっておかなアカンって、切ないけど大事な教えやね。
【語源・由来】
「風樹」とは、風に吹かれて揺れ動く樹木のことを表し、風の有無で揺れ動く樹木のように、どうすることもできない事から。
【出典】
中国前漢時代の韓嬰による著書『韓詩外伝』にて、「樹静かならんと欲すれども風止まず。子養わんと欲すれども親待たず。往きて見るを得べからざる者は親なり(木が静かにしたいと思っていても、風がやまないのでどうすることもできない。孝行したいと子が思っても親は待ってくれない。あの世に行ってしまえば二度と会えないものは親である)」という記述から。
【類義語】
・石に布団は着せられず
・樹静かならんと欲すれども風止まず
・孝行のしたい時分に親はなし
・子養わんと欲すれども親待たず
・墓に布団は着せられず
【英語訳】
・A good thing is known when it is lost.
・regretting one’s unkindness to one’s deceased parents when they were alive
「風樹の嘆」の解説

「風樹の嘆」という表現は、本来は静かに立っていたい木が、風によって揺れ動かされることを避けられないように、子供が親に孝行をしたいと思った時にはもう親が亡くなってしまっていて、孝行の機会を逃してしまうという悲しみを表しているんだよ。
この言葉は、「韓詩外伝」に由来していて、人の世の無常さや、タイミングの重要性を教えてくれる言葉だね。子供が親への感謝や愛情を示すために何かしたいと思う時には、時すでに遅しで親がこの世にいないという状況を悲しむことを「風樹の嘆」と表現しているんだ。
このことわざは、大切な人に対して、一緒にいる間に感謝や愛を示すことの大切さを伝えているんだね。
「風樹の嘆」の使い方




「風樹の嘆」の例文

- 彼女は長い間海外で生活しており、帰国したときにはすでに母が亡くなっていた。彼女の心には風樹の嘆が重くのしかかった。
- 風樹の嘆を感じるとは、子どもとしての義務を果たせなかったことに対する深い後悔を意味する。
- 彼は、成功を収めた今、かつて両親に苦労をかけたことを思い出し、その風樹の嘆に苛まれている。
- 父の長い病気の間、彼女は仕事の都合でなかなか実家に帰ることができず、風樹の嘆に心を痛めていた。
- 幼いころからの夢を叶えた彼も、忙しさにかまけて親孝行の一つもできずに時が過ぎ、いざというときには風樹の嘆を背負うことになった。












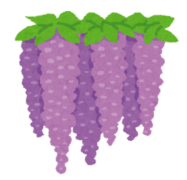
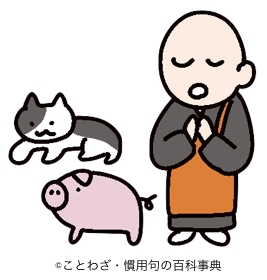


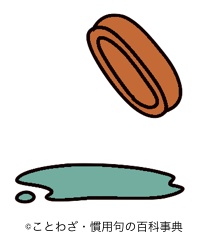








これを人間の感情に当てはめると、子どもが親に孝行をしたいと思うときには、すでに親が亡くなっていて何もできないという悲しい状況を示しているんだよ。