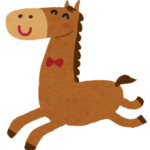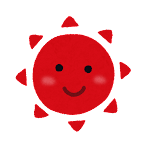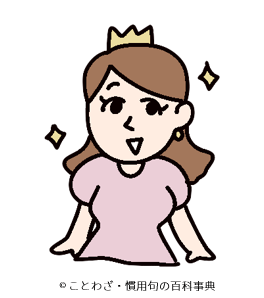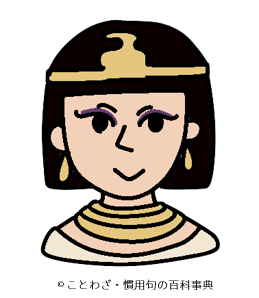「百礼の会、酒に非ざれば行われず」の意味(出典)

【ことわざ】
百礼の会、酒に非ざれば行われず
【読み方】
ひゃくれいのかい、さけにあらざればおこなわれず
【意味】
人が集まる会には酒がつきものだということ。どんな儀礼も酒がないとうまくいかないということ。


お祝い事や、大事な会議でも、ちょっとした飲み物があると、雰囲気が和んで、事がうまくいくってわけや。昔から酒は、人と人とをつなぐ大事な役割を持ってたんやね。でも、ほどほどにせなアカンけどな。
【出典】
「漢書」
「百礼の会、酒に非ざれば行われず」の解説

「百礼の会、酒に非ざれば行われず」という言葉は、どんなに格式の高い会や儀式でも、酒がなければうまく進まないという意味を持っているんだよ。これは、「漢書」に出てくる教えで、昔から酒が社交の場や儀式、会合で重要な役割を果たしていたことを示しているんだ。
たとえば、お祝い事や、大切な会議、友達や家族との集まりなど、さまざまな場面で酒が振る舞われることがあるよね。酒は人々をリラックスさせたり、話を弾ませたりする効果があるから、会をより和やかに進めるための一助となるんだ。
この言葉からは、昔から酒が人々の間でどれだけ大切な役割を果たしてきたかということを学ぶことができるね。もちろん、酒を飲むことがすべての会合で必要なわけではないけれど、酒が持つコミュニケーションを促進する力や、人と人とをつなげる力について考えさせられる言葉だよ。ただし、酒を飲む時は、その場の雰囲気を大切にしつつ、適量を心掛けることも重要なんだ。
「百礼の会、酒に非ざれば行われず」の使い方




「百礼の会、酒に非ざれば行われず」の例文

- 結婚式の席上で、新郎の父が立ち上がり、百礼の会、酒に非ざれば行われずという言葉を述べながら、祝杯を挙げた。
- 会社の創立記念パーティーで、社長は百礼の会、酒に非ざれば行われずと言い、成功を祝うための特別なワインを開けた。
- 地域の祭りの計画会議で、主催者は百礼の会、酒に非ざれば行われずと強調し、祭りのプログラムに日本酒のテイスティングを盛り込むことを提案した。
- 親族が集まる新年の宴会で、祖父が百礼の会、酒に非ざれば行われずと言いながら、家族の健康と幸福を願って乾杯を提案した。
- 文化交流イベントで、日本文化を紹介する講演者は、百礼の会、酒に非ざれば行われずと述べ、日本のお酒の文化とその社会的な意味について解説した。