「三年飛ばず鳴かず」の意味(語源由来・英語訳)
【ことわざ】
三年飛ばず鳴かず
【読み方】
さんねんとばずなかず
【意味】
他日雄飛する機会を待って長い間雌伏していること。


何年もの間、こっそりと準備して、その結果を一気に発揮する瞬間は、本当に感動的やね!
【語源・由来】
楚の荘王の部下である伍挙が、三年もの間享楽にふけっている王を三年間飛びも鳴きもしない鳥に見立てて諫めたところ、王は「この鳥は飛べば天に昇り、鳴けば人々を驚かすだろう」と答えて伍挙を退けたが、後日、大夫の蘇従の諫言に従い、放逸な生活を改め、伍挙と蘇従を重用して国事に専念したという故事から。
【英語訳】
英語訳はありません。少し説明が必要ですが、加えて He/She lay low for three years in wait for his/her opportunity. といえば意味合いは通じます。
「三年飛ばず鳴かず」の解説

「三年飛ばず鳴かず」っていうのは、ある古い話や本に出てくる話から来ているんだ。この話には、3年間全く飛ばないで、鳴かない鳥がいて、でもその鳥が一度飛ぶとすごく高く天まで飛んで行って、鳴くとすごく大きな声で人々を驚かせるっていう話があるの。
この言葉の意味は、長い間何もしないで待っているけど、その後で大きな活躍をする、っていうことを表しているんだよ。要するに、ちょっと待つことで、その後の大きな成功や活躍のチャンスがあるということを教えてくれる言葉なんだね。
「三年飛ばず鳴かず」の使い方




「三年飛ばず鳴かず」の例文

- 彼があんなに素晴らしい仕事をするとは思っていませんでした。三年飛ばず鳴かずで会社の様子を見ていたのでしょうか。
- 会社を立ち上げて三年飛ばず鳴かずです。なんとかしたいとは思っています。
- 三年飛ばず鳴かず、ここが辛抱(しんぼう)のしどころです。
まとめ
三年といえば石の上にもということわざがあります。このことわざと同じように三年という期間がひとつの目安となっています。三日・三月・三年という話は、新入社員教育などで聞いたことがある方も多いと思います。現代は社会が変化する時間の流れが速くなっていますので、時間感覚は違うのでしょうが、長い日本の歴史の中では、三年とは、相当長い期間のことを指しているのでしょう。





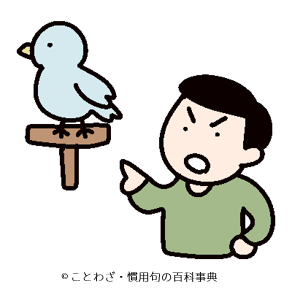







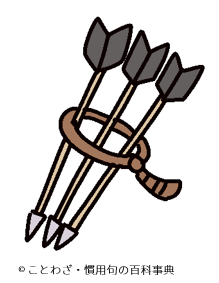

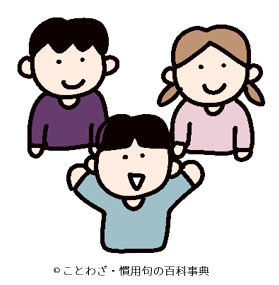

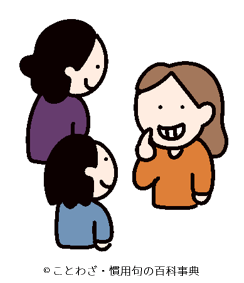







これは、準備や研鑽の期間が長くても、その成果が一度表れれば人々を驚かせることを指しているよ。