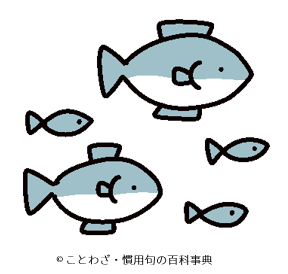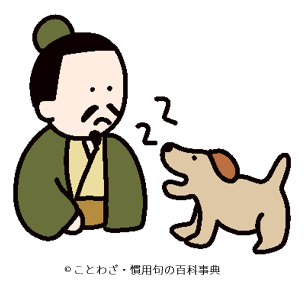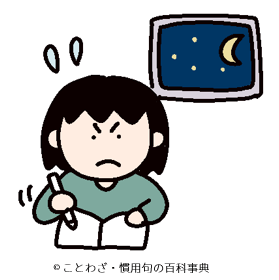「三人虎を成す」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)

三人虎を成す
【読み方】
さんにんとらをなす
【意味】
事実無根の風説も、言う人が多ければ、ついに信じられるようになることのたとえ。


うわさって、ほんまは違っても、言う人が多いと信じちゃうんやな。これは、うわさを鵜呑みにしないように気をつけなアカンねんてことやね!
【語源・由来】
三人の口にかかれば虎ができ、十人の口にかかれば鉄椎(てっつい)がたわめられ、多数の口に乗れば、翼も無いのに空を飛ぶということから。
【出典】
「戦国策」
【類義語】
・市に虎あり(いちにとらあり)
・三人市虎を成す(さんにんしこをなす)
・三言市虎(さんげんしこ)
・三人之を疑わしむれば即ち慈母も信ずる能わず(さんにんこれをうたがわしむればすなわちじぼもしんずるあたわず)
【英語訳】
英語訳はありません。似たような意味合いで A lie well stuck to is as good as the truth. (上手く嘘をつくとホントになる)や Many a true word is spoken in jest. (嘘から誠になる)という表現があります。
「三人虎を成す」の解説

「三人虎を成す」っていう言葉は、ちょっと面白い話があるんだよ。昔の話の中で、市に虎がいるって3人の人が言ったら、本当にいないのに、みんながそれを信じちゃうっていう話から来てるんだ。
つまり、何かの噂や話が事実じゃなくても、たくさんの人がそれを言ったり、伝えたりすると、結局、みんなが本当だと思って信じちゃうことがあるんだよ。
だから、この言葉は、「たくさんの人が同じことを言うと、それが本当みたいに思われちゃうから、情報や噂を鵜呑みにしないように注意してね!」っていうことを教えてくれるんだね。
「三人虎を成す」の使い方




「三人虎を成す」の例文

- 三人虎を成すか、話を信じて特売日だと思って行ってみたら、みんなも来ていたけど特売なんてしていませんでしたが、どこで嘘の話を聞いたのでしょうか。
- そういうもっともらしい話を信じて、三人虎を成すといって、自分で事実を確認しないようでは、この業界では生きていけません。
- 簡単に信用すると大変なことになるのは、特に外国における事業で、都合のよい三人虎を為すような儲け話がたくさんありますから用心した方がいいでしょう。
- 最近の報道機関は三人虎を為すような解説番組が多くて、何を信用していいのか分からなくなりました。
まとめ
情報手段が限られた昔なら三人虎を為すということは普通にあったのでしょうが、不思議なことにこれだけ情報が溢れかえっている現代社会でも同じようなことが続いているのはなぜでしょうか。誰でも情報発信が出来る良い時代ですが悪意ある先導には気をつけた方がいいと思います。