「斯の人にして斯の疾あり」の意味(語源由来・出典)

斯の人にして斯の疾あり
【読み方】
このひとにしてこのやまいあり
【意味】
立派な人が重い病にかかること。転じて、立派なのに色欲などの欠点があり、身の修まらないことをいう。


人間だもん、誰しも完璧じゃないもんな。見た目ばっかりに惑わされず、ちゃんと中身も見ることが大切やね。
【語源・由来】
孔子が愛する弟子の冉耕が死病に冒されてしまったのを嘆き悲しんだ言葉から。
【出典】
「論語」
「斯の人にして斯の疾あり」の解説

「斯の人にして斯の疾あり」ということわざはね、すごく立派な人なのに、運悪く困った病気にかかっちゃうような状況を言っているんだ。でも、この言葉はもう一つの意味も持っていて、それは、すごく素晴らしい人なのに、例えば色欲のような欠点や弱点がある、っていうことも指しているんだよ。
要するに、どんなに素晴らしい人でも、ちょっとした弱点や困った点があることを伝えているんだ。みんなが持っている小さな欠点や弱点を指して、そんな部分も含めてその人を理解し、受け入れるっていうことを示しているよ。
例えば、すごく優れた先生がいるけど、その先生がちょっとだけ食べ物の好き嫌いが多い、とか、そういうちょっとした欠点を言うときに使えるんだ。
「斯の人にして斯の疾あり」の使い方




「斯の人にして斯の疾あり」の例文

- せっかく仕事が増えてこれからって時に、斯の人にして斯の疾ありだ。
- 立派なのにギャンブル好きが玉に瑕で、斯の人にして斯の疾ありです。
- 言うことなしなのに、女癖が悪いところが斯の人にして斯の疾ありといえる。
- 非の打ち所のない人なのに、斯の人にして斯の疾ありというように末期がんにかかっているそうだ。
- 斯の人にして斯の疾ありっていうけど、まさかあんなできた人が重病を患うなんて。そんなの日頃の行いが悪い人がかかるべきなんじゃないか。










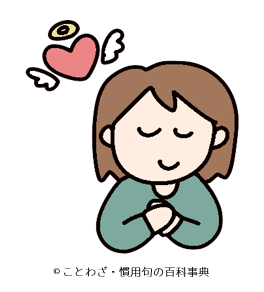


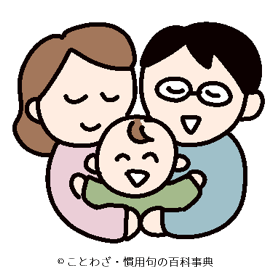
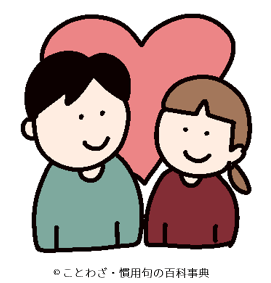









しかし、時が経つにつれ、この言葉は、見た目や立場は立派な人でも、人間的な弱さや欠点があることを指すたとえとしても使われるようになったんだよ。