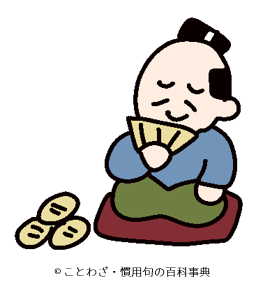目次
「鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる」の意味(語源由来・出典・類義語)
【ことわざ】
鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる
【読み方】
こうをぬすむものはちゅうせられ、くにをぬすむものはしょこうとなる
【意味】
道理に合わないこと。


それはまあ変やな。まるで、小さな悪はダメやけど、大きな悪はええって、なんか納得いかへんわ。ちょっと不思議な世界やな。
小さなものを盗む泥棒は死刑になり、国を奪いとる泥棒は領主になることから。
【出典】
「荘子」
【類義語】
・米食った犬が叩かれずに糠食った犬が叩かれる
・皿嘗めた猫が科を負う
「鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる」の解説

「鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる」っていう言葉、ちょっと難しいよね。でも、この言葉の意味は、社会の不公平や矛盾を表しているんだ。
これをもっとわかりやすく説明すると、小さな悪事をする人は、その罰を受けるけど、大きな悪事をする人は、かえって報われて、高い地位や権力を持つことがある、ということを言っているんだ。
たとえば、ちょっとした盗みをした人が捕まって、罰を受けるのに、大きな横領や詐欺をして国や大きな組織をだまくらかした人が、その地位や権力を持ち続けることがあるよね。それって、公平じゃないよね。
「鉤」は、尾留めや魚を釣るときの針のことを意味していて、「諸侯」は、昔の中国の封建時代において大きな領土や権力を持っていた人たちのことだよ。
要するに、この言葉は「小さな罪で罰されるのに、大きな罪を犯しても報われるのはおかしいよね」という、世の中の不公平や矛盾を指摘しているんだよ。
「鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる」の使い方

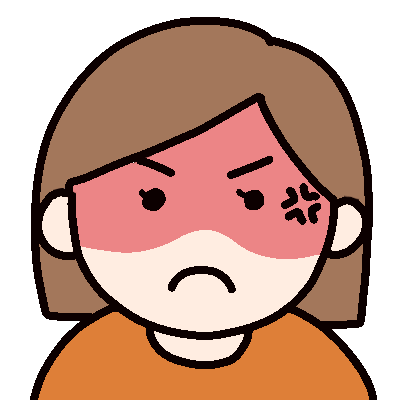


「鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる」の例文

- 時効がある限り逃げたもの勝ちだ。それでは鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となると同じだ。
- 議員の息子の交通違反はもみ消せるのに、庶民はそうはいかないとは鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となるようだ。
- テロリストの要求は鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となる物でのむわけにはいかなかった。
- 鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となるようなことを強引に推し進めることを、横車を押すという。
- 君の言っていることは鉤を窃む者は誅せられ、国を窃む者は諸侯となるようで、屁理屈だよ。