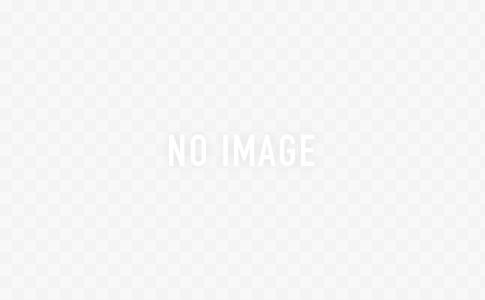「盗人にも三分の理」の意味(語源由来・類義語・英語訳)
【ことわざ】
盗人にも三分の理
「盗人」は「ぬすっと」とも読む。
【読み方】
ぬすびとにもさんぶのり
【意味】
盗人が盗みを働くにもそれなりの理屈があるということ。どんなことでも理屈がこじつけられるたとえ。


でも、それでその行為が許されるわけではないってことやね。これは、物事の背後にある理由や動機を理解することの大切さと、同時に行為の正当性を判断する必要性を示してる言葉やな。
【語源・由来】
「三分」は「十分の三」で、泥棒にも盗みをしなければならない理由や言い分が十分の三くらいはあるということから。
【類義語】
・柄の無い所に柄をすげる
・乞食にも三つの理屈
・泥棒にも三分の道理
・盗人にも五分の理
・盗人にも一理屈
・藪の頭にも理屈がつく
・理屈と膏薬はどこへでもつく
・盗人にも三分の理あり
【英語訳】
Even a thief has his reasons
The wrongdoer never lacks a pretext.
Every man has his own reason.
Give the devil his due.
「盗人にも三分の理」の解説
「盗人にも三分の理」という表現は、どんな不正や悪事を働いた人にも、その行動を正当化するための何らかの理由や論理があるということを意味しているんだ。この言葉は、「三分」という数字を用いているが、これは完全ではないものの、ある程度の根拠や論拠があることを示唆しているよ。この表現は、悪事を働いた人でもその行動には一定の動機や背景があり、全てが無根拠であるわけではないという事実を認識することの重要性を示しているんだ。しかし、それがその行為を正当化するものではなく、あくまで「理屈はつけられる」という程度の意味であることがポイントだね。
「盗人にも三分の理」は、人間の行動や心理には複雑な背景があること、そしてその背景を理解することが、問題の解決や対処のためには必要であることを教えてくれる言葉でもあるよ。このたとえを通じて、事象を多角的に見ることの大切さや、単純な善悪の二元論で物事を判断しないようにという教訓が含まれているんだ。
「盗人にも三分の理」の使い方
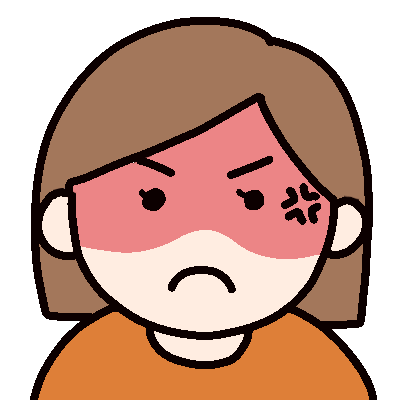

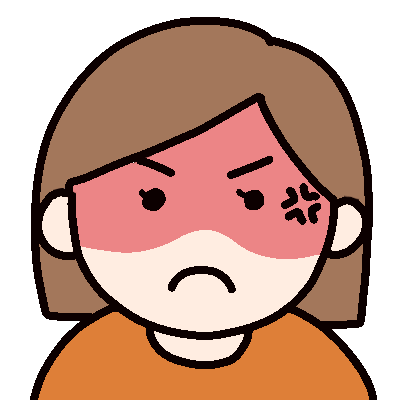

「盗人にも三分の理」の例文

- 盗人にも三分の理というけれども、この男のは、八分位の道理はあるようで、どうもとても大変な境遇で育ったようで。
- お前だって、伊達や酔狂で彼を殺したわけじゃあるまいし、盗人にも三分の理という言葉があるんだから、訳を言ってみろ。
- 盗人にも三分の理という言葉のように、彼は、盗んでもいいような悪人や、大金持ちの家にしか侵入していないと言っている。
- 盗人にも三分の理というように、あの役立たずで有名な社員の行動にも何か理由があるんだろうから、同期のよしみで話を聞いてこい。
- 盗人にも三分の理というように、私が留守の間に、なんでこんなに家が散らかってしまったのか理由を聞かせてもらおうかしら。