「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の意味(語源由来・英語訳)
【ことわざ】
盗人を捕らえて見れば我が子なり
【読み方】
ぬすびとをとらえてみればわがこなり
「盗人」は「ぬすっと」とも読む。
【意味】
盗人を捕らえたら意外にも自分の子だったということで、事が意外なために処置に困るたとえ。さらに、親しい者でも油断してはならないという意味もある。


これは、人との関係や信頼について深く考えさせられる教訓やな。身近な人でも、予期せぬ行動をする可能性があるってことや。
【語源・由来】
室町末期の連歌師、山崎宗鑑が「切りたくもあり切りたくもなし」という下の句に上の句を三句付けてみよといわれ「ぬすびとを捕へて見ればわが子なり」「さやかなる月をかくせる花の枝」「心よき的矢の少し長いをば」という三句を作ってみせた。親は自分の子を買いかぶることが多いが、いざ盗人を捕まえてみたら我が子だったということがある。犯人が我が子だとわかったときに、警察に出頭させることも胸が痛むし、黙って見過ごすわけにもいかないし、どうすべきか悩む親心をあらわしている。
【英語訳】
・the doting parent’s purse is plundered
・the thief caught turns out to be one’s own son
「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の解説

「盗人を捕らえて見れば我が子なり」という表現は、予期せぬ事態や意外な発見に直面した際の困惑や戸惑いを表している言葉だね。この言葉は、文字通りには盗みを働いた人物を捕まえてみたら、それが自分の子供であるという非常に意外な状況を描いているんだ。これは、自分が思ってもみなかった人物が問題の当事者であることを知り、どのように対応すれば良いのか判断がつかなくなる様子を示しているよ。
この表現は、人生で起こり得る予測不能な出来事や、親しい人であってもその人の全てを知っているわけではないという事実を浮き彫りにしているんだ。親子のように近い関係であっても、相手の行動や思惑を完全に理解することは難しいという教訓も含まれているね。
また、このたとえは、倫理的なジレンマや葛藤に直面した際の複雑さを表しているとも言えるよ。愛する人が悪事を働いた場合、その人をどう扱うべきか、どのように対応すれば正義と愛情の間でバランスを取ることができるのか、といった難しい選択を迫られる状況を象徴しているんだ。
このように、「盗人を捕らえて見れば我が子なり」という言葉は、人間関係の複雑さや、予期せぬ事態に対する心の準備の重要性を教えてくれる言葉なんだね。
「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の使い方


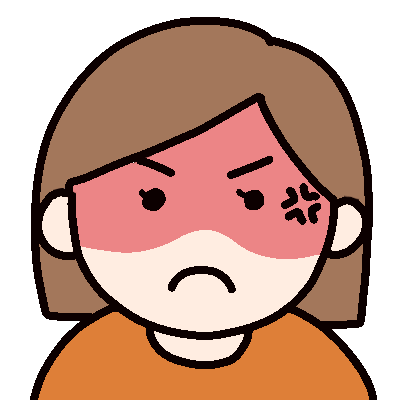

「盗人を捕らえて見れば我が子なり」の例文

- 盗人を捕らえて見れば我が子なりというように、犯人は自分の息子だったので、親心として悩んだ末に、息子をかばって警察に嘘をついてしまった。
- 盗人を捕らえて見れば我が子なりというように、犯人は一番身近にいた秘書だったので、人間不信になりそうだった。
- 盗人を捕らえて見れば我が子なりというように、僕の靴をいつも盗んでいたのは、僕の犬だったので唖然とした。
- 盗人を捕らえて見れば我が子なりというように、犯人は全幅の信頼を置いていた友人だったので、驚いた。






















