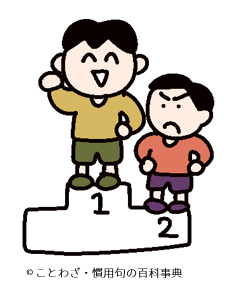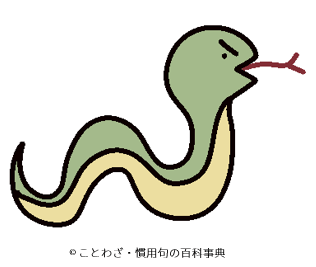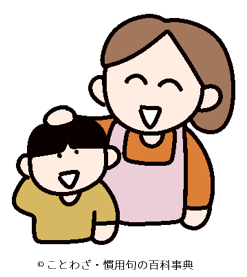「子貢が多言も顔子の一黙には如かず」の意味(語源由来・類義語)

子貢が多言も顔子の一黙には如かず
【読み方】
しこうがたげんもがんしのいちもくにはしかず
【意味】
無駄口をたたかず徳を養うことが最良だということ。


ちゃんとした意味や背後にある思いを大切にすることで、もっとも良い影響を与えられるんやね。言葉の量じゃなくて、質やな!
【語源・由来】
才人として知られる子貢の弁舌も、顔子(顔回)の沈黙に比べると徳の高さにおいては到底及ばないことから。
【類義語】
・雄弁は銀沈黙は金
「子貢が多言も顔子の一黙には如かず」の解説

「子貢が多言も顔子の一黙には如かず」っていうことわざは、たくさん話すより、黙ってる方が時々もっと価値があるっていうことを示しているんだよ。
実はね、このことわざには昔の有名な人たちの話が関係しているんだ。孔子というすごく賢い先生がいて、その先生の下で学んでいた生徒たちの中に「子貢」という人と「顔子」(または顔回)っていう人がいたんだ。
子貢はすごくよく話すことが得意な人で、いつも賢いことを言っていたんだよ。でも、顔子は寡黙で、あまり話さなかったけど、彼の沈黙の中には深い意味や徳があったんだ。
このことわざは、子貢のうまい話よりも、顔子の黙っている姿の方がもっと価値がある、っていうことを教えてくれているんだよ。つまり、言葉だけでなく、行動や態度にも大切なことが隠れていることを伝えているんだね。だから、いつもたくさん話すことがすごいわけじゃなくて、何を言わないか、どう行動するかも大切だよ。
「子貢が多言も顔子の一黙には如かず」の使い方




「子貢が多言も顔子の一黙には如かず」の例文

- 子貢が多言も顔子の一黙には如かずというから、僕は寡黙な男になる。
- 高倉健さんは、子貢が多言も顔子の一黙には如かずのように寡黙で人徳があった。
- 雄弁は銀沈黙は金といい、子貢が多言も顔子の一黙には如かずだから余計なことは言わない。
- 言わぬは言うに勝るし、子貢が多言も顔子の一黙には如かずなので、多くは語らない。
- 子貢が多言も顔子の一黙には如かずといい、言わぬが花ともいうが、無口な方が徳が高く趣がある。