「提灯持ち」の意味(語源由来・類義語・英語訳)
【ことわざ】
提灯持ち
【読み方】
ちょうちんもち
【意味】
①夜道や葬式などに、同行する人の前に提灯を持って立つ人。
②他人の手先に使われ、また頼まれもしないのに他人のためにその長所などを吹聴すること。また、その人。


道を照らす提灯持ちも大事な役割やけど、人をほめる提灯持ちも、その人のためになってるかどうかはよく考えなあかんな。どっちにせよ、自分でしっかりと物事を見て、考えることが大切やね。
【語源・由来】
提灯を持って人々の前に立ち、足元を照らして歩く意から。
【類義語】
太鼓持
【英語訳】
「蝋燭(ろうそく)を持つ」というところから、意味合いが違いますが I can’t hold a candle to him. (彼の足元にもおよばない。)という英語訳があります。
「提灯持ち」の解説

「提灯持ち」という言葉には二つの意味があるんだ。
- 最初の意味は、文字通り夜道や葬列などで提灯を持って先導する役、またはその人を指すんだ。夜道では明かりを提供し、安全に道を進めるように導く重要な役割を果たす。葬列などの儀式では、進行を円滑にし、適切な方向へと導くために提灯を持つ人がいる。この場合、提灯持ちは文字通り提灯を持っている人を指し、その役割は非常に具体的で実用的なものだね。
- 二つ目の意味は、比喩的な用法で、ある人の手先となってその人をほめたり、その人の意見や立場を支持してまわる人のことを指すんだ。この場合、提灯を持つことはその人の良い面を照らし出し、見せることを象徴していて、その人を良く見せるために動く人を指しているんだ。つまり、他人の利益のために自分の意見や立場を曲げる人、または誰かの影響力や地位を利用して自分の利益を追求する人を示しているよ。
このように、「提灯持ち」という言葉は、その使用される文脈によって、実際に提灯を持って先導する役割を果たす人を指すこともあれば、他人のために働く、特に他人を称賛し、その人の影響力や地位を高める役割を果たす人を指すこともあるんだね。
「提灯持ち」の使い方




「提灯持ち」の例文

- 会社の現状はそんな甘いものではありません。提灯持ちと馬鹿にされても契約を取ってくることが大事です。
- 一見提灯持ちのように見える人こそ注意する必要があります。心の中は分かりませんから、本当に信用できるまで、大事なことは話さない方が良いでしょう。
- いくつになっても自分の立場を理解して、例え上司が若い人でもしっかりと仕えることが大切です。提灯持ちになれといっているのではありません。
まとめ
相手の足元にも及ばないことから、素直に提灯持ちとなれる人がいます。嫉妬心からあえて提灯持ちとなって、その人が失敗することを待ち望んでいる人がいます。同じ立場でも、尊敬する心と媚(こ)びへつらう心では、得るものが違ってくるでしょう。











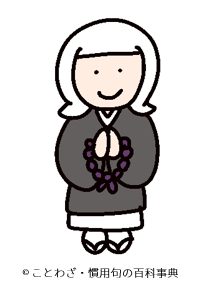

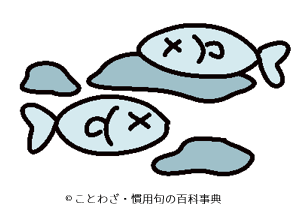




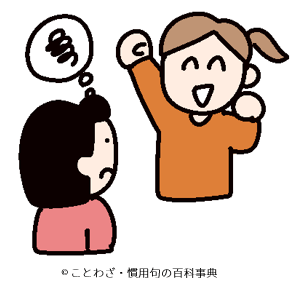






一つ目は文字通り、夜道や葬列などで先導するために提灯を持って歩く人のことで、二つ目は、ある人を盲目的に賞賛し、その人の意向に従って動くこと、またはそのような人のことを指すんだよ。この場合、批判的な思考をせず、ただ賛美することを表しているね。