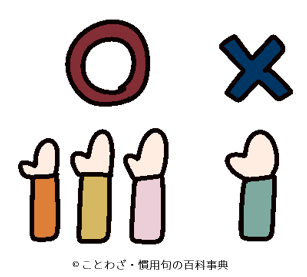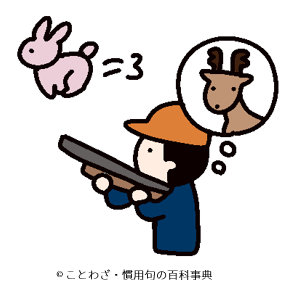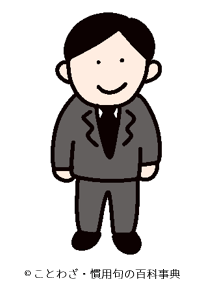「地震雷火事親父」とは

読み方・意味
- ことわざ:地震雷火事親父
- 読み方:じしんかみなりかじおやじ
- 意味:世の中でこわいもの、どうにもかなわない恐ろしいものを並べたもの。
「地震雷火事親父」とは?
この言葉は、「世の中で恐ろしいもの、抗いがたいもの」を順に並べた、恐怖の対象を列挙したことわざです。
特に昔の日本において、子どもや庶民が日常で強く恐れていたものを象徴的に表現しています。
各要素の意味と順序
地震(じしん)
→ 大自然の脅威の最たるもの。予測も回避も困難で、甚大な被害をもたらす。命の危険もあるため、一番恐れられていました。
雷(かみなり)
→ 落雷による死傷や火災の危険があり、昔は特に予測不能な天災として恐れられていました。
火事(かじ)
→ 江戸時代など、木造建築が密集していた時代では特に火事が大災害となり得たため、非常に恐れられた存在です。
親父(おやじ)
→ 父親のこと。ここでは単なる父親ではなく、「家父長(かふちょう)的存在」としての父、つまり家の中で絶対的な権力を持つ存在を指しています。家父制度のもとでは、父の命令は絶対であり、特に子どもにとっては恐怖の象徴でもありました。
現代との違い
現代では「親父」の権威は薄れ、家庭内でも対等な関係が尊重されるようになってきたため、「地震雷火事親父」という言葉のユーモア性やレトロさが目立つようになっています。
「地震雷火事親父」の語源・由来
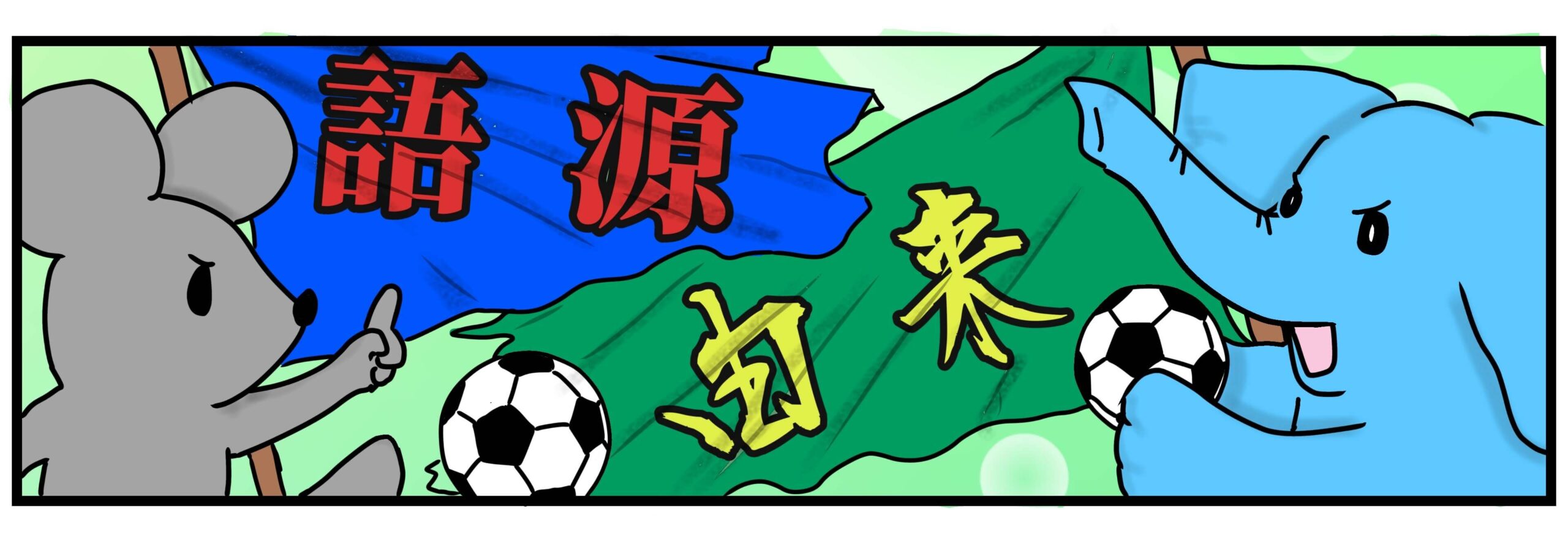
江戸時代後期の成立と文献初出
この言葉の最も古い記録は、1831年に成立した『尾張童遊集』という書物です。
これは名古屋周辺の子どもたちが当時遊びの中で使っていた言葉や歌を集めたもので、そこに「地震雷火事おやぢ」という表現が記載されています。
つまり、この言葉は江戸後期にはすでに子どもたちの口の中で流行していたと考えられます。
庶民の間で、親しみをこめつつも恐怖を表す言い回しとして根付いていたことがうかがえます。
なぜ「親父」が入るのか?── 諸説紹介
【説1】家父長制を反映した社会的背景説(有力説)
江戸時代から明治時代初期にかけて、日本では家父長制(家長制度)が支配的でした。この制度では、家庭の中で「父親(親父)」が絶対的な権限を持っており、特に子どもにとっては逆らえない存在でした。
この社会背景を反映し、「自然災害(地震・雷・火事)に並ぶほど、親父も恐ろしい」という比喩として「親父」が加えられたと考えられます。
特徴:
- 家庭内の絶対権力者としての「父」
- 自然災害と同列の恐怖の対象
- 子どもたちの素直な感覚が反映されたとも言える
【説2】名主・庄屋・親方など「権力者」を意味していた説
「親父」は実の父親ではなく、地域の有力者(名主・庄屋・親方など)を意味していたという説もあります。江戸時代には、町内や村落を取り仕切る役職に対しても「おやじ」と呼ぶことがありました。
この説では、「親父=地域社会における権威の象徴」として恐れられていた人物であり、法的・経済的な支配力のあった存在が「恐ろしいもの」として加わったとされます。
特徴:
- 「親父」=地域社会の支配者
- 「支配の怖さ」と「自然災害の怖さ」を並列化
【説3】「親父」は「大風(おおやじ/おおやまじ)」の転化説
非常にユニークな説として、「親父」は本来「大風(おおやじ)」または「大山嵐(おおやまじ)」だったというものがあります。つまり「台風」の古称です。
発音が似ていることから、「おおやじ」が「おやじ」に変化し、やがて漢字が「親父」と当てられたという音韻変化による言い換えです。
特徴:
- 語呂の良さ(「じ」で終わる)
- 災害の連続性を保ちつつ、ユーモアを加えた転換
- やがて実在の「親父」へ意味がすり替わった可能性
【説4】ユーモアと韻律を活かした創作説
この表現は、意外性と語感の面白さを活かした言葉遊びとして成立したとする「ユーモア説」もあります。
「地震・雷・火事」と重く恐ろしい天災が続いたあとに、「親父」という日常的な存在が出てくることで、軽妙なオチのようなユーモラスな構成となっているのが特徴です。
韻律の妙:
- 地震(じしん)
- 雷(かみなり)
- 火事(かじ)
- 親父(おやじ)
「かみなり・かじ・おやじ」はすべて「じ」で終わり、リズミカルな口調で覚えやすく、子どもたちの遊び言葉として広がったこともうなずけます。
江戸文化との関連性
江戸時代には、「地震雷火事親父」の感覚を視覚化した「鯰絵(なまずえ)」と呼ばれる瓦版や浮世絵も存在しました。
地震を鯰に、雷や火事を擬人化し、「親父」はその外側でそれらを律する存在として描かれているものもあります。
これは、「地震・雷・火事・親父」が諺(ことわざ)であると同時に、江戸人の自然観・権力観を風刺的に描いた民俗文化の一端だったことを表しています。
「地震雷火事親父」の使い方




「地震雷火事親父」の例文
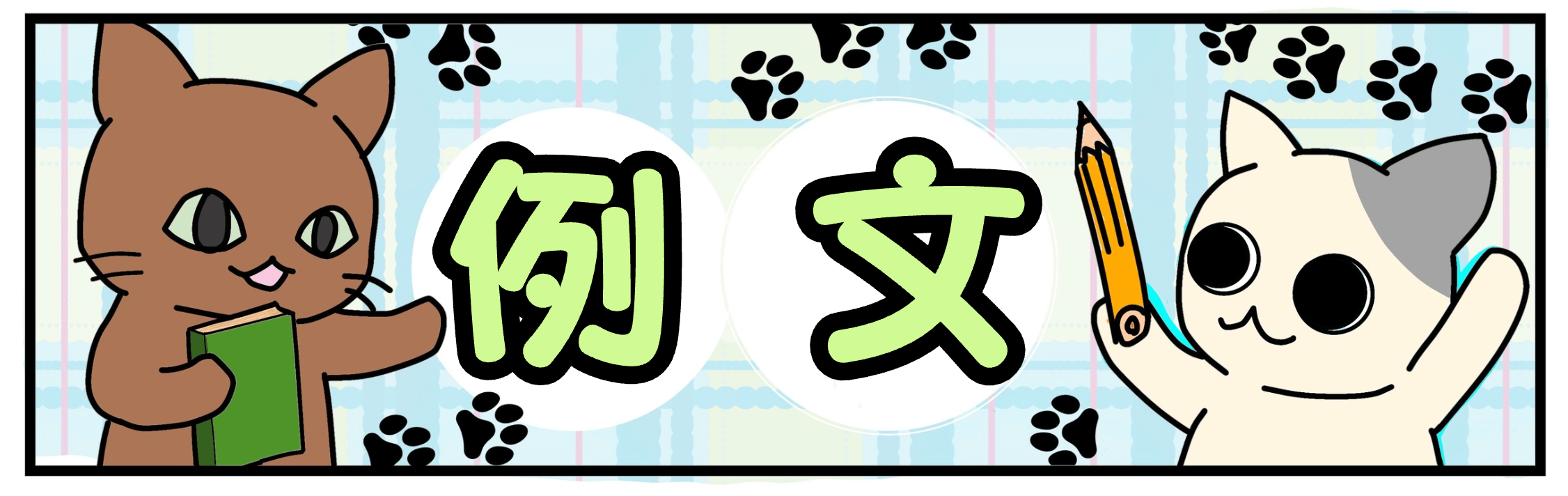
- 地震雷火事親父とはよく言ったもので、うちの父が怒ると、雷よりもよっぽど怖かった。
- 子どものころ、父の帰宅音が聞こえるとピシッと背筋が伸びた。まさに『地震雷火事親父』の親父だったよ。
- 「地震雷火事親父」とはいうけれど、最近の親父はすっかり家族の癒やし担当だね。時代は変わったよ。
文学作品などの用例
もし戦争が起ったなら。という題を与えられて、地震雷火事親爺(おやじ)、それ以上に怖(こわ)い戦争が起ったなら先(ま)ず山の中へでも逃げ込もう、逃げるついでに先生をも誘おう、先生も人間、僕も人間、いくさの怖いのは同じであろう、と書いた。(太宰治『苦悩の年鑑』)
「地震雷火事親父」の注意点
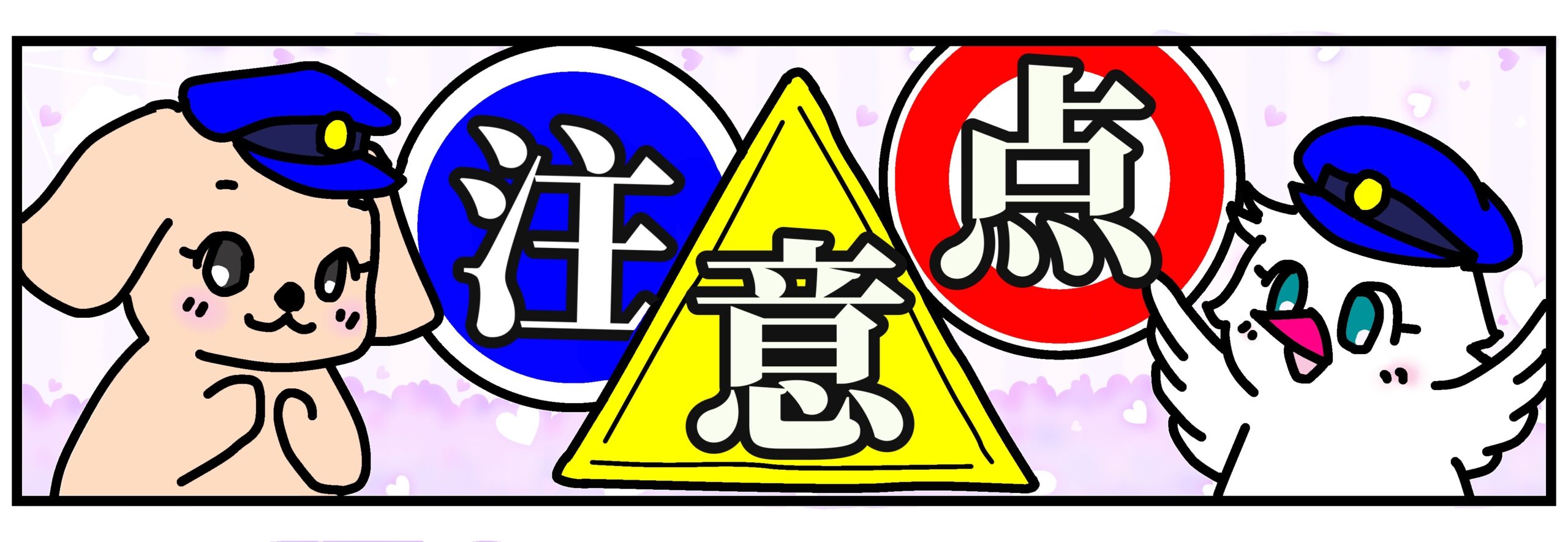
- 実際の災害や被害を軽く扱うと不適切
→ 被災者の前で冗談のように使うと、不謹慎に聞こえることがある。
(例:✕「昨日の地震、地震雷火事親父って感じだったね」→ 不謹慎な印象を与える) - レトロな雰囲気や昔話として使うと効果的
→ 昔の風習や家庭のあり方を紹介する場面では自然に使える。
(例:◎「地震雷火事親父ってことば、昔の人の感覚がよくわかるね」)
「地震雷火事親父」の専門家コラム


“地震雷火事親父”--ほとんどの人が知っている表現で、こわいもの、恐ろしくて抗(あらが)えないものを並べたてています。
「地震」の恐ろしさは、今年(2024年)の元日におきた能登半島地震でもあらためて思い知らされました。
大地震がおきると、建物が倒壊して死傷者が出たり財産が失われるばかりでなく、鉄道や道路も寸断され、水道や電気・ガスにも被害がおよんで、日常生活ができなくなってしまいます。
しかも、地震の後に津波が押し寄せたり、火事がおきると消火できなくなったりして、さらに被害が大きくなることもあります。
日本は国土が狭いのに、世界の大地震(マグニチュード6以上) の20%以上が日本でおきていて、昔から繰り返し大きな地震におそわれてきましたから、こわいものの筆頭に地震をあげるのは当然でしょう。
二番目は「雷」--これも、直撃されると命にかかわります。
昔は、夕立の季節に稲光がして、ゴロゴロと雷が鳴ると、雷さまにへそをとられると言って、子どもを家のなかに入れ、へそを押さえさせたりしました。
雷の正体が電気とわかり、避雷針やアースによって落雷による事故は少なくなりましたが、屋外では油断できません。
登山やグラウンドでの部活では、雷について正しい知識と警戒が必要です。
三番目の「火事」は、地震や雷が天災(自然による災害)であるのに対し、人災(人によっておきる災害)の要素が大きくなります。
落雷や火山の噴火によるものもありますが、大半は人間の不注意からおきるといってよいでしょう。
火は料理や暖房などに使われ、とても便利なものですが、火事になると、「盗人(ぬすびと)の取り残しはあれど、火の取り残しはない」というように、財産すべてを焼きつくし、自分の家だけでなく隣近所まで灰にしかねない恐ろしいものとなります。
最後の「親父(おやじ)」は、前の三つの災害とはちがって、意外性があります。
自分の父親、あるいは仕事場の親方や名主など年令や地位が上の人をさして言うこともありました。
こわいのもたしかですが、親しみもあって、ちょっと皮肉を込めた軽いユーモアでオチをつけたともいえます。
このことわざは、「地震雷火事親父」とただ怖いものを並べただけのようですが、声に出して読んでみると、とても口調がよく、自然に印象に残る表現です。
なぜ、そうなるのか、レトリック(表現技法)について少し考えてみましょう。
「じしん」は3音、「かみなり」は4音で、合わせて7音。
「かじ」は2音、「おやじ」は3音で、合わせて5音。
これは七五調といって、古くから詩や歌によく使われた形式で、日本人の耳に心地よく響くものです。
しかも、このことわざは、「雷」と「火事」の語頭(単語のはじめの部分)の音(頭韻)がともに「か」で、同じです。
「火事」と「親父」の最後の音(脚韻)もともに「じ」で、共通しています。
つまり、「地震雷火事親父」という短い文句のなかで、音声の面で二カ所韻を踏み、内容もちょっとした意外性があるので、一度聞いただけでも耳に残るのではないでしょうか。
このことわざは、古くは『尾張童遊集』(1831年)の「幼児口遊(くちずさみ)」に収録されていて、江戸後期には名古屋近辺の子どもたちがよく口ずさんでいたようです。
いまでは、全国どこでもよく知られていて、幼い子どもたちに世の中には怖いものがあることをさりげなく教える役割をはたしているといってよいでしょう。
©2024 Yoshikatsu KITAMURA