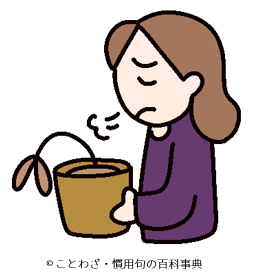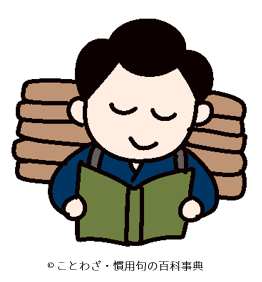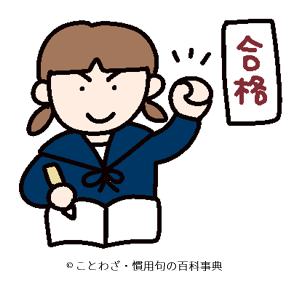「上手はあれど名人はなし」の意味(語源由来)

上手はあれど名人はなし
【読み方】
じょうずはあれどめいじんはなし
【意味】
一芸をきわめることは困難であること。


一つの技や芸術を極めることの困難さを示してるんやね。真の名人になることは、非常に高いレベルの技術や努力が必要ってことやな。
【語源・由来】
ある程度上手な人はたくさんいるが、格別優れた人は少ない。江戸時代、囲碁や将棋の段位の別称として、七段を上手、八段を半名人、九段を名人といった。
「上手はあれど名人はなし」の解説

「上手はあれど名人はなし」という言葉は、多くの人がある程度の技術や能力を持っていて「上手」と呼ばれることはあっても、特別に優れていて「名人」と呼べる人は非常に稀であるという意味を持っているんだよ。この表現は、ある分野で真に優れた技術や知識を持つことの難しさを示しているんだね。
江戸時代に囲碁や将棋において、七段を「上手」、八段を「半名人」、九段を「名人」と呼んだことに由来しているよ。このことわざは、一技に秀でて真の達人や名人になることは容易ではないということを表しているんだ。
たとえば、音楽、スポーツ、芸術などの分野で、多くの人があるレベルの技能を持っているが、その中で圧倒的な才能や技術を持つ「名人」はほんの一握りであるという状況が「上手はあれど名人はなし」と表現されることがあるんだ。
「上手はあれど名人はなし」という言葉は、高度な技術や知識を持つことの価値と、そのようなレベルに達することの難しさを教えてくれているんだよ。真の名人になるためには、長年の献身的な努力と深い熟練が必要であるというメッセージが含まれているんだね。
「上手はあれど名人はなし」の使い方




「上手はあれど名人はなし」の例文

- ピアノが上手な人は大勢いるけど、後世に残るような名人はおらず、上手はあれど名人はなしだ。
- 料理が上手な人は何万何千人といるが、上手はあれど名人はなしだ。
- 絵画が上手な人は老若男女問わずたくさんいるが、上手はあれど名人はなしとは本当だ。
- 名人は政府が与える称号ではなく自然と呼ばれるようになるものだ。なので名人になるにはより多くの人に認められる必要があり、上手はあれど名人はなしという。
- 上手はあれど名人はなしというように、長らく名人は輩出されていない。