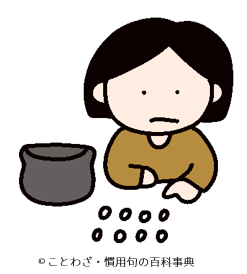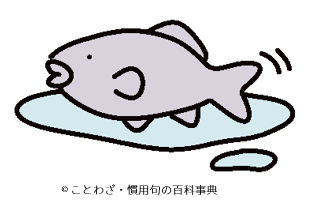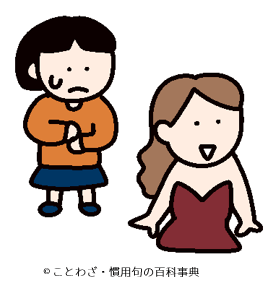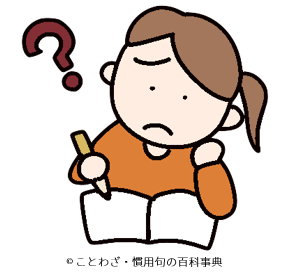【ことわざ】
無用の用
【読み方】
むようのよう
【意味】
役に立たないとされているものが、実は大事な役割を果たしていること。
また、役に立たないことが、有用であること。
【語源・由来】
「無用(むよう)」とは、役に立たないという意味。
また、「老子(ろうし)」には、
「埴(しょく)をうちて以(もっ)て器を為(つく)る。その無に当たりて器の用あり」
粘土をこねて器を作る。その器は一見無用の空間があるからこそ器として使えるのだ。
と、あることにも基づいているとされる。
「荘子」や「老子」に多く見られる論。
【出典】
「荘子」人間世(じんかんせい)
「人は皆有用の用を知りて無用の用を知ること莫(な)し」
人は明らかに役に立つものの意義は知っているけれど、一見無用のようなものが人生にとって真の意味があることだとは知らない。
と、あることに基づく。
【類義語】
・不用の用(ふようのよう)
・無駄方便(むだほうべん)
【英語訳】
Everything is good for something.
An unnecessary thing also becomes useful. Keep a thing seven years and you will find a use for it.
「無用の用」の使い方




「無用の用」の例文
- 無用の用ということもあるのだから、役に立たないと決めつけてはいけないよ。
- 実益は大切だけど、無用の用ということもあるかもしれないんだよ。
まとめ
無用の用というように、役に立たないと思われていたものが役に立つこともあるかもしれません。
すぐに諦めたり、投げ出したりしないことも、大切なのかもしれませんね。