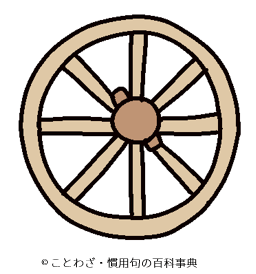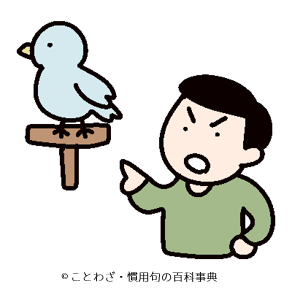「三顧の礼」の意味(出典・類義語・英語訳)
【ことわざ】
三顧の礼
【読み方】
さんこのれい
【意味】
地位ある人や目上の人が、何度も足を運んで、賢人(けんじん)に礼を尽くして仕事を引き受けてもらうために頼み込むこと。


たとえ自分がえらい立場にいても、相手の力を認めて、尊重するってことやな。人を大事にする心、大事やね。
【出典】
三国志で有名な劉備(りゅうび)について、諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい)が劉禅(りゅうぜん)に奏上(そうじょう=もうしのべること)した「出師表(すいしのひょう)」の文中に記したもので、「文選」等にも引用されています。
【類義語】
四字熟語では「草廬三顧(そうろさんこ)」といいます。
【英語訳】
直訳の一例は Three visits to Zhuge Liang(諸葛亮孔明の英語名)です。
「三顧の礼」の解説

「三顧の礼」という言葉は、中国の歴史の中での有名な話からきているんだ。ちょっと詳しく説明するね。
昔、中国の三国時代という時代があって、その中で蜀という国のリーダー、劉備という人がいたんだ。劉備は、賢い軍師、つまりアドバイザーとして、諸葛亮という人をぜひ自分のところに招きたかったんだよ。
そこで劉備は、諸葛亮の家を訪れることにしたんだけど、初めて行ったときは諸葛亮が家にいなかった。でも劉備は諦めずに再び訪れた。しかし、二度目も諸葛亮は不在だったんだ。それでも劉備はあきらめず、三度目に諸葛亮の家を訪れたところ、ようやく二人は会うことができた。
この話から「三顧の礼」という言葉が生まれたんだ。この言葉の意味は、自分がリーダーや上の立場の人であっても、大切な仕事を頼みたい人には、礼を尽くして、何度でも交渉すること。また、特定の人をとても信頼して、特別扱いすることを示しているんだよ。
つまり、「三顧の礼」は、どれだけ人を大切に思い、尊重し、頼りにしているかを示す言葉として使われることが多いんだ。
「三顧の礼」の使い方




「三顧の礼」の例文

- さすが三顧の礼をもって来ていただいたことだけのことはある。立派な人ですね。
- 三顧の礼のつもりでお願いしたが、どうしても首を縦に振ってくれない。
- 聞くところによれば、うちの社長が先方にわざわざお願いにいっているらしい、三顧の礼みたいなものでしょう。
- 私のようなもののために、三顧の礼のようなお願いをされると困ってしまいます。
「三顧の礼」の文学作品などの用例
藤吉郎が、その竹中半兵衛重治ひとりを麾下に迎えるため、かつては栗原山の山中に七日も通って行き、慇懃三顧の礼をとって、ようやく彼に出廬の決心をさせた、あの熱意を思い合わせれば――さもあろうかと、家臣たちは、むしろ彼があわてる様をたのもしくさえ見るのであった。(吉川英治の新書太閤記より)
まとめ
三顧の礼といえば誰でも「三国志」のことを思いうかべます。魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三国時代のことを述べた歴史書のことですが、実は私達になじみのものは後世になって、歴史書の「三国志」とその後の民間伝承(でんしょう)で、唐の時代から元にかけて流行した話をもとに、明の時代の初期に羅貫中(らかんちゅう)という作家が著作した「三国志演義(さんごくしえんぎ)」です。「三国志」の世界は「三国志演義」によって、日本だけでなく、世界中に広まったのです。