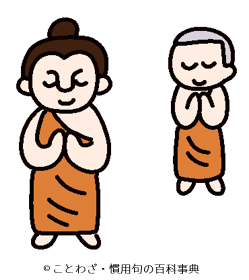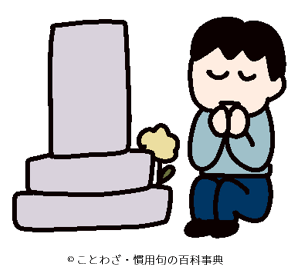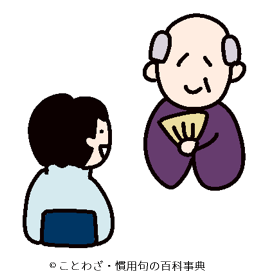「三尺下がって師の影を踏まず」の意味(語源由来・類義語・英語訳)

三尺下がって師の影を踏まず
【読み方】
さんじゃくさがってしのかげをふまず
【意味】
先生につき従ってゆくときには、先生を敬う心がけを忘れずに、先生から三尺下がって歩き、先生の影を踏むようなことがあってはならないよう説いたことば。
弟子は先生を敬い、礼儀を尽くすようにしなさいという教え。


先生の後ろを歩く時に、ちょっと距離をあけて、その影も踏まへんようにするくらいの気をつけて歩くべきやってこと。常に敬意を忘れんように、っていうのが大切なんやな。
【語源・由来】
もとは仏教の作法であり、師僧(しそう)に従って歩くときの心得(こころえ)で、本来は、「七尺去って師の影を踏まず(しちしゃくさってしのがげをふまず)」という。
【類義語】
師弟となって七足去る(していとなってしちそくさる)
【英語訳】
正式な英語訳はありません。一例として A student must never forget to honor their teacher. という訳があります。
「三尺下がって師の影を踏まず」の解説
「三尺下がって師の影を踏まず」っていうことわざはね、先生や大切な人の後ろを歩くときに、ちょっと距離を取って、先生の影に足を踏み入れないように気をつけることからきてるんだよ。
このことわざの背景には、昔の日本での敬意の表現の一つとして、先生や尊敬する人の影に足を踏み入れないようにするという習慣があったんだ。3尺っていうのは、おおよそ1メートルくらいの距離のことを指すんだよ。
このことわざの意味は、先生や大切な人をとっても尊敬して、礼儀を大切にして、失礼なことをしないように気をつける、っていうことなんだ。だから、簡単に言うと、尊敬する人の後ろを歩くときも、その人に対して敬意を持って接することの大切さを教えてくれる言葉なんだよ。
「三尺下がって師の影を踏まず」の使い方

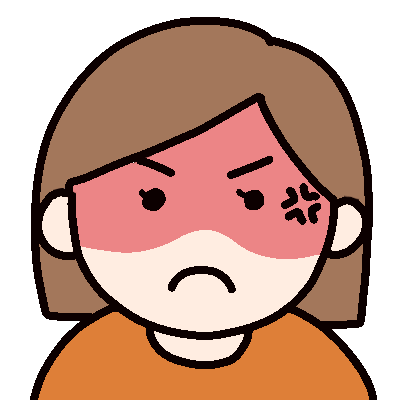


「三尺下がって師の影を踏まず」の例文
- 監督が来るまで待ちましょう。三尺下がって師の影を踏まず、親しくても礼は忘れないようにしましょう。
- 課長の行動を見習った方がいいでしょう。常に謙虚(けんきょ)に三尺下がって師の影を踏まず、なかなかできないですよ。
- 礼というものは形だけではありません。三尺下がって師の影を踏まずというのは心の持ち方を示しているのです。
- 三尺下がって師の影を踏まずといいます。教えをいただく人に対しては礼儀を忘れないようにしましょう。
まとめ
今はとても難しい時代です。会社でも学校でも上司や先生は友達のような存在です。厳しく接すると会社を辞めてしまう可能性が高く、学校では教師からのいじめとも取られかねません。先輩や上司を無条件で尊敬するというような昭和的な発想は歴史的遺産のようなものとなりました。古い人からすればひどい世の中になったとおもうでしょうし、若い人からすれば、まだ面倒くさい風習みたいなものが多く残っていると感じていることでしょう。どちらも正しく、どちらも間違った考え方をしている部分があります。メディアやSNSなどで情報は氾濫し、感情的表現が増えていますが、人と人が顔を見ながらコミュニケーションを取ることは人間という生き物としての基本です。お互いを思いやる心、お互いに三尺下がって師の影を踏まず、礼がコミュニケーションの潤滑油になるのではないでしょうか。