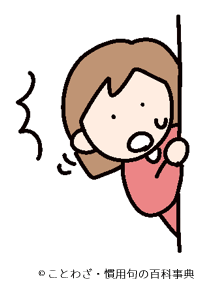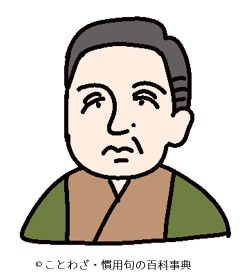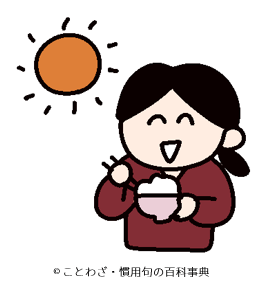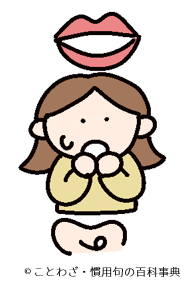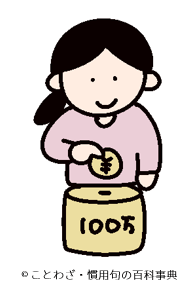【ことわざ】
敵は本能寺にあり
【読み方】
てきはほんのうじにあり
【意味】
真の目的は別のところにある意。
【語源・由来】
明智光秀が備中の毛利勢を攻めると称して出陣し、織田信長を本能寺に攻めた故事。
【英語】
直訳は Our Enemy is in the Honno-ji Temple. ですが、意味合いでいうと He that wipes the child’s nose kisses the mother’s cheek.(子供の鼻を拭くのは母親の頬にキスをすること)とい表現もあります。
「敵は本能寺にあり」の使い方




「敵は本能寺にあり」の例文

- 派遣で働いて2年目でまだつらいけど敵は本能寺にあり、我慢して努力するしかない。
- ここはひとまず相手の要求を聞いておこう、敵は本能寺にあり、最終目的を達成するためには影響はないでしょう。
- そんなに親切にしているのは別に目的があるんじゃないか、敵は本能寺にありだな。
- 敵は本能寺にありだ、少々のことで感情的に議論しても何も得るものはない。
まとめ
あまりにも有名な話です。なぜ明智光秀が信長を倒したのか今でも真相は不明ですが、本当の目的を明かさすまもなく秀吉に倒された明智光秀の心情はどうだったんでしょうか。ひとつだけ言えることは、事実として光秀の行動は表向きの目的外の行動をしたことは間違いありません。信長のことですからそうやすやすと奇襲に引っかかる武将ではなかったはずです。戦国の世ですから、味方の武将でも何を考えているのか常に情報は収集していたはずです。それでも討たれたということは、まったく予想外の行動だったのでしょう。奇襲作戦としては大成功でしたが、光秀にとっては戦略的には大失敗だったのかもしれません。さて、信長がいなくなって、誰が戦略的に成功を収めたのでしょうか、計算されたものかのでしょうか、そえとも偶然なのでしょうか。確たる証拠が出るまでは答えは分からないのでしょう。