「梅雨に降らぬと土用に降る」の意味(語源由来)
【ことわざ】
梅雨に降らぬと土用に降る
【読み方】
つゆにふらぬとどようにふる
【意味】
空梅雨になると、土用のころにたくさん降る。


天気も結局はバランスをとってるってわけやね。季節ごとの雨量の変化を表すことわざやな。自然のリズムって不思議やね。
【語源・由来】
土用は小暑から立夏までのこと。梅雨に雨が降らないと、土用のころ多雨になることが多いことから。
「梅雨に降らぬと土用に降る」の解説
「梅雨に降らぬと土用に降る」という言葉は、気象のパターンに関する昔からの観察を表している言葉だよ。
梅雨は、日本を含む東アジアの一部地域で毎年初夏に見られる、数週間にわたる雨の期間のことを指しているんだ。通常、この時期は多くの雨が降るんだけど、このことわざは、梅雨の時期にあまり雨が降らない場合、その後の土用の時期にたくさんの雨が降るという気象の傾向を表しているんだね。
土用は、夏と秋の間の期間を指していて、日本の伝統的な暦では、季節の変わり目に位置しているんだ。このことわざは、もし梅雨の時期に雨が少なければ、そのバランスが土用の期間に取り戻されるだろうということを示しているんだ。
このように、このことわざは、自然のバランスや季節の気象パターンに関する昔の人々の観察と経験に基づいているんだね。自然が持つ一種のリズムやバランスを示唆している言葉なんだ。
「梅雨に降らぬと土用に降る」の使い方




「梅雨に降らぬと土用に降る」の例文

- 梅雨に降らぬと土用に降るというから、立夏まで雨が降りそうだ。
- 梅雨に降らぬと土用に降るという、梅干しを干すタイミングがつかめない。
- 梅雨に降らぬと土用に降るというから空梅雨でも心配ない。
- 梅雨に降らぬと土用に降るというが、お盆になっても雨が降らない。
- 梅雨に降らぬと土用に降るといわれるが、ゲリラ豪雨にならなければいいな。





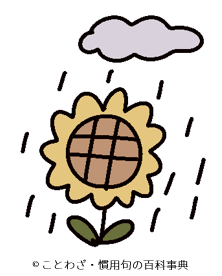









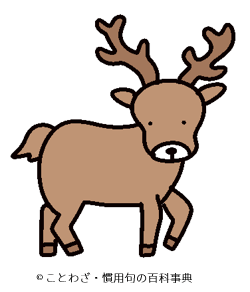



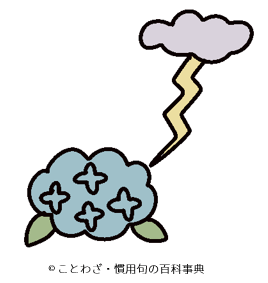






これは、天気のバランスが自然と取れることを示しているんだ。