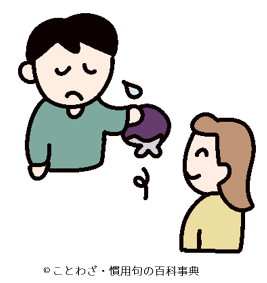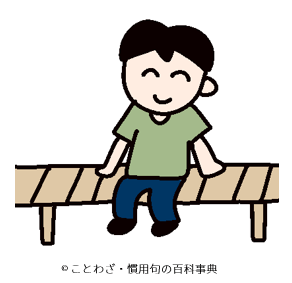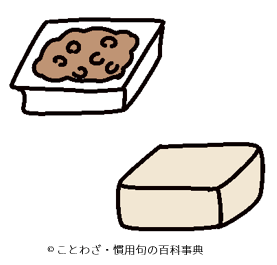「難波の葦は伊勢の浜荻」の意味(語源由来・類義語)
【ことわざ】
難波の葦は伊勢の浜荻
【読み方】
なにわのあしはいせのはまおぎ
【意味】
地方によって呼び名が変わることのたとえ。


難波で普通に「葦」って言ってるのが、伊勢では「浜荻」って呼ばれてるってわけか。これは、違う土地に行ったら、そこの風習や名前がちゃうっていうのを教えてくれるんやね。地域によって、物の見方や言い方が変わるってことやな。
【語源由来】
難波(大阪府)で葦と呼ばれている草は伊勢(三重県)では浜荻と呼ばれる。同じ物でも所によって呼び名が変わるように、風俗や習慣も土地土地で異なるということから。
【類義語】
・所変われば品変わる(ところかわればしなかわる)
「難波の葦は伊勢の浜荻」の解説

「難波の葦は伊勢の浜荻」ということわざはね、同じものでも場所によって名前が違うっていうことを表しているんだよ。
たとえばね、難波(今の大阪あたり)では、ある種の草を「葦」と呼んでいるけど、伊勢(三重県の方)ではその同じ草を「浜荻」と呼ぶんだ。これは、同じ植物でも、住んでいる地域によって名前が変わるっていう例なんだね。
このことわざは、ただ植物の名前だけではなくて、風俗や習慣、考え方なども場所によって違うっていうことを教えてくれているんだ。例えば、ある地域ではお正月に特定の料理を食べる習慣があるけど、別の地域では全く違う料理を食べることもあるよね。
だから、「難波の葦は伊勢の浜荻」っていうのは、「同じものや習慣でも、場所によって名前ややり方が変わる」という意味の言葉なんだね。それぞれの地域の文化や習慣を理解するのに役立つことわざなんだよ。
「難波の葦は伊勢の浜荻」の使い方




「難波の葦は伊勢の浜荻」の例文

- 難波の葦は伊勢の浜荻というけど、黒板消しはラーフルって呼ばれる所もあるんだ。
- ケンタッキーは有名だが、難波の葦は伊勢の浜荻のごとく、大阪ではケンチキと呼ばれ、東京ではケンタと呼ばれる。どっちも健太くんのあだ名じゃないか。
- 絆創膏は絆創膏でしかないと思っていたが、難波の葦は伊勢の浜荻というように、サビオ、カットバン、リバテープ、キズバンと呼ばれ、呼び方で生まれ故郷がわかる。
- 上履きは義務教育で使われる必須アイテムだが、難波の葦は伊勢の浜荻のようにたくさんの呼び方があるんだよ。文部科学省で統一すればいいのにね。
- 御座候って何だろう?って思って行列に並んで買ったら、難波の葦は伊勢の浜荻みたいに、大判焼きだった。