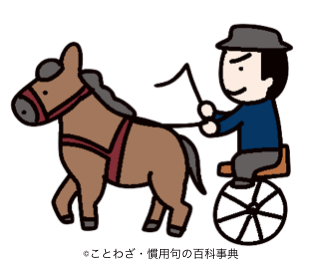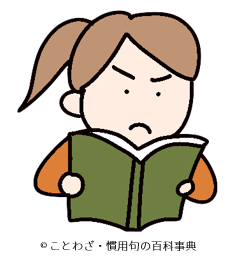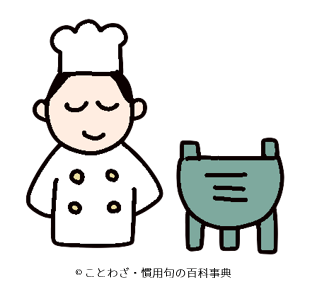「喪家の狗」の意味(語源由来・出典・故事・英語訳)
【ことわざ】
喪家の狗
【読み方】
そうかのいぬ
【意味】
痩せて衰えていて、元気のない人のたとえ。


それに、家を失った犬のように、宿なしの状態を表す意味もあるんや。これは、人生の逆境や悲しみがどれほど深い影響を与えるかを教えてくれてるんや。悲しい時には周りのものにも影響が及ぶってことやな。
【語源・由来】
葬式のあった家の犬は、家の人に世話をしてもらう余裕がなく、食べ物が与えられないで痩せ衰えることから。
【出典】
「史記」孔子世家
【故事】
諸国をまわりやつれ果てた孔子をみて、鄭(てい)の人が、
「纍纍(るいるい)として、喪家の狗の若(ごと)し」
すっかり疲れ果てて、見る影もなくやつれている。
と、評したとされる故事に基づく。
【英語訳】
It is the person who became emaciated without spirit.
「喪家の狗」の解説

「喪家の狗」という言葉は、「孔子家語」の「困誓」に由来しており、不幸があった家で、家族が悲しみに暮れて犬に餌をやることを忘れ、犬が元気を失ってしまった状態を指しているんだよ。この表現は、そのような状況にある犬を例にして、大きな悲しみや困難に直面している人々の状態を象徴しているんだね。
このことわざは、喪に服している家の中で、家族が悲しみに打ちひしがれているために、犬に十分な注意を払えなくなる様子を表しているよ。その結果、犬がやつれて元気を失ってしまうことから、大きな悲しみや苦難に直面している人々の心情を表現しているんだ。
また、一部の解釈では、「喪家の狗」は宿無しになった犬を意味するとされており、これは家族や居場所を失った犬の哀れな状態を示すことがあるんだよ。いずれにせよ、この言葉は深い悲しみや苦難の中にある人々、または見捨てられたり孤立したりしている状況にある人々や動物の状態を表すのに使われるんだね。このことわざは、困難な状況にある人々や動物に対する同情や理解を促す言葉と言えるよ。
「喪家の狗」の使い方



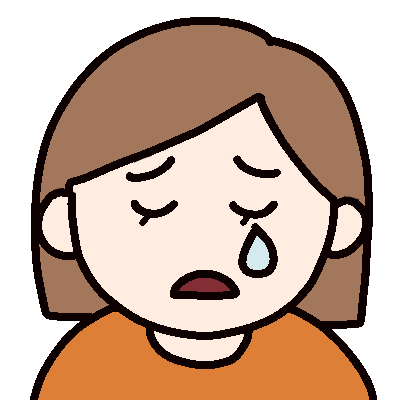
「喪家の狗」の例文

- 彼は意気込んで事業を始めたものの、どうやら失敗してしまって借金だけが残ったようだ。すっかり喪家の狗のようにやつれてしまっていたよ。
- 彼女は恋人の夢を応援するために、寝る間も惜しんで仕事をしていたようだけど、喪家の狗のような様子だった。
- 彼はとてもつらいことがあったと、毎日喪家の狗のようなやつれた姿で夜の街をさまよっているらしい。
「喪家の狗」の文学作品などの用例
その日一日中、小平太はどこをどう歩いていたのか、人も知らず、おそらく自分でも分らなかったに相違ない。兎に角、江戸の市中を、喰うものも喰わず、喪家の狗のように、雪溶けの泥濘を蹴立ててうろつき廻っていた。(森田草平の四十八人目より)
まとめ
喪家の狗のように、やつれて元気がなくなってしまっては、とても心配になりますね。
大変なことがあるかもしれませんが、元気を出したいものですね。