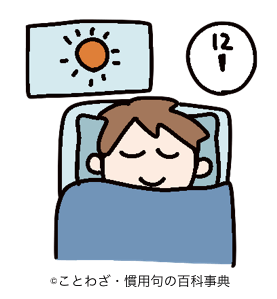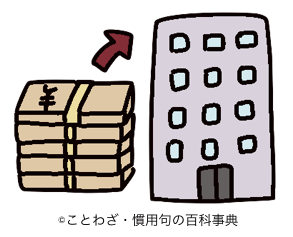「有りての厭い、亡くての偲び」の意味(類義語)

有りての厭い、亡くての偲び
【読み方】
ありてのいとい、なくてのしのび
【意味】
人が生きている間は悪い点が目につき疎ましく思うことが多いが、亡くなると良い点ばかりが思い出される。

「有りての厭い、亡くての偲び」ということわざは、人が生きているときにはその欠点ばかりが目立ち、疎ましく感じるけれど、その人が亡くなったときには良いところばかりを思い出して恋しくなるという人間の心情を表しているんだ。

なるほどな。つまり、人が健在なときはダメなとこばっかり目につくけど、いざその人が亡くなったら、ええとこばっかり思い出してせつなくなるってことやな。
生きてるときに、その人の良いところをちゃんと見て認めてあげることの大切さを教えてくれるわけやな。
【類義語】
・有っての厭い、亡くての偲び
【スポンサーリンク】
「有りての厭い、亡くての偲び」の解説
カンタン!解説

「有りての厭い、亡くての偲び」っていうことわざは、ねえ、人がまだ生きてるときは、その人の悪いところばっかり気になってしまうけど、その人が亡くなったときには、逆にその人の良いところばかりを思い出してしまって、その人が恋しくなっちゃう、っていう感情を表しているんだよ。
たとえば、友だちといつもケンカばかりしていたけど、その友だちが引っ越してしまった後、一緒に遊んだ楽しかった思い出ばかりを思い出して、その友だちが恋しくなるような気持ちを指しているんだよ。
だから、このことわざは、人が亡くなった後やいなくなった後になって、その人の大切さを改めて認識するっていう、ちょっと寂しいけど人間らしい感情を表しているんだね。
「有りての厭い、亡くての偲び」の使い方

あの先生が亡くなって半年だね。懐かしいなあ。

あんなに嫌っていたのに懐かしむのね。

有りての厭い、亡くての偲びっていうからね。無くなると惜しくなるのが人情だよ。

人間って勝手ね。
【スポンサーリンク】
「有りての厭い、亡くての偲び」の例文

- 有りての厭い、亡くての偲びといい、思い出は美化されていくものだ。
- 憎み合っていたはずなのに、有りての厭い、亡くての偲びというが、笑顔が素敵だったことしか思い出せない。
- 有りての厭い、亡くての偲びというように、嫌っていた部分は次第に忘れ、良いことだけが記憶に残っていくものだよ。
- 亡くなった人のことは悪く思えないのは、有りての厭い、亡くての偲びということか。
- 有りての厭い、亡くての偲びというが、亡くなると何故憎んでいたのかわからなくなった。