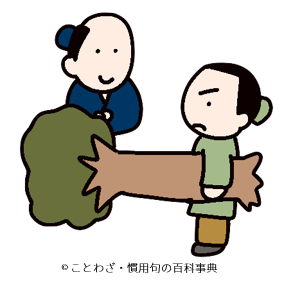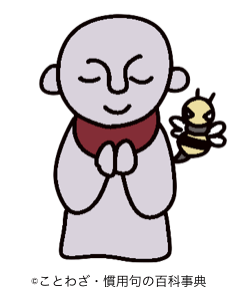【ことわざ】
一寸先は闇
【読み方】
いっすんさきはやみ
【意味】
たとえすぐ先の事でも、未来の事は誰にも全く予測できないという意味です。
【語源・由来】
昔は電気がなかったので、街頭も建物の灯りなどもなく、夜道は真っ暗でした。
灯り用の油を買うお金のない家庭なら、家の中も暗かったでしょう。
月が出ていなければ、一寸(約3㎝)先も見えないほどの暗闇でした。
現在では想像もできないほどの暗さです。
この事から、目の前が暗闇で何も見えないように、近い将来ですら何が起きるのか見通しがつかない、という意味で使われるようになりました。
長さの単位である「一寸」を、時間に置き換えたのですね。
「上方いろはかるた」の中の「い」です。
【類義語】
・一寸先は闇の夜
・食えや飲めや、明日は死ぬ身だ
・無常の風は時を選ばず
・面前に三尺の闇有り
「一寸先は闇」の使い方




「一寸先は闇」の例文

- 来年の今頃は会社が倒産しているかも、いや、一寸先は闇というから、明日会社が倒産する事だって考えられる。
- 厳しい現代社会を生き抜いていくには、楽観視はいかがなものか。むしろ一寸先は闇であると常に警戒しながら生きていく方が丁度良いと言える。
- 一寸先は闇なのに、彼は「この株は必ず大きく値上がりする」と意気込んで、借金返済のためにさらにお金を借りて株を大量に購入した。
コラム:暗喩が生きる「一寸先は闇」


「一寸先は闇」--これから先何が起こるか、未来のことはまったくわからないという意味で、現在もよく使われる表現です。
ことわざ全体がたとえ(比喩)になっていて、何をさしているのか明らかには示さない形の比喩(暗喩、メタファー)です。
「一寸」は、長く使われてきた尺貫法の長さの単位で、1尺(約30㎝)の10分の1、つまり現在のメートル法で約3㎝です。
しかし、だからといって、「一寸先は闇」をメートル法に換算して「3㎝先は闇」というわけにはいきません。
ことわざでは、いまも尺貫法が使われていて、その数値には、換算したのでは伝わらない象徴的な意味(この場合は、ほんの少しの意)が込められているからです。
このことわざは、ほとんど常識化しているのでつい見落としがちですが、短い表現の中に巧みなレトリック(修辞)が秘められています。
「一寸先は」と聞くと、まず空間をイメージしますが、「闇」と受けることによって、ことわざの聞き手は一気に時間軸に引き込まれます。
この「闇」は、目の前の光景として見えるわけではなく、現実に見えている光景の背後にあり、比喩の喚起する想像力によって感じ取ることが可能なものになっているのです。
このレトリックの威力は、類例の「未来のことは寸前も闇の夜」と比較してみると、よくわかるでしょう。
後者の表現は、「未来のことは」と主題を明らかにすることでわかりやすくなっていますが、「一寸先は闇」の説明にはなっても、たとえが果たす機能は大幅に低下し、魅力がうせているのではないでしょうか。
比喩は、意味や対象を明示しないことによって(つまり、暗喩によって)むしろ想像力を刺激し、大きな力を発揮するのです。
「一寸先は闇」の用法としては、何らかの予兆(きざし)を感じて、今後何が起きても不思議はないことを示す場合が多いといえますが、実際にまったく予想外のことが起きたときにその感慨を示すこともあります。
「一寸先は闇」の初出は、江戸時代初期の俳諧作法書(参考書)の『毛吹草』や『世話尽(せわづくし)』に収録された古いことわざで、おそらく戦国時代末期から使われていたものでしょう。
背景にあるのは、戦乱に明け暮れし明日の命もおぼつかない時代で、悲惨な記憶がなまなましく残り、この世をはかないものとする仏教的な無常観が広く浸透していました。
平和が訪れても、いつまた何が起こるかわからない不安を多くの人がかかえていたものと思われます。
そんな暗い世相のなかでも、人々はかならずしも意気消沈し、もっぱら消極的な生活をおくってきたわけではありません。
酒食の席では、「飲めや歌えや 一寸先は闇の夜」と音頭をとって歌い踊っていたようです(当時の俗謡については記録が乏しく、実証は困難ですが、江戸中期にはその痕跡を示すものがいくつも認められます)。
享楽的なことは否めませんが、「一寸先は闇」を前提としつつも、精一杯いまを生きようとしていたのではないか、と感じられます。
「一寸先は闇の夜」は、歌謡の韻律に合わせて使われた異形(いけい、バリエーション)と推測され、「闇の夜」は「闇の世」にも通じ、近代にいたるまで比較的よく見聞きするものでした。(2025/1/09)
©2025 Yoshikatsu KITAMURA