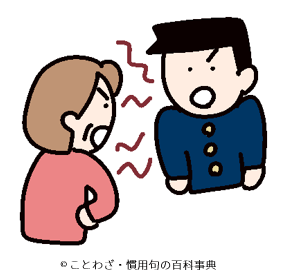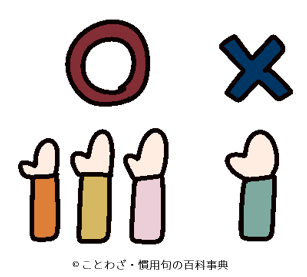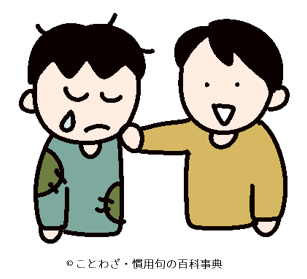「常山の舌」の意味(出典・故事)
【ことわざ】
常山の舌
【読み方】
じょうざんのした
【意味】
ひどい目にあっても屈せず、国や主に忠誠を尽くすこと。


どんな状況でも自分の立場を変えずに堅持することの価値を示してる言葉やな。信念を持って行動することの重要性を教えてくれるね。
【出典】
「新唐書」
【故事】
唐の顔杲卿は常山の太守だったが、安禄山を罵り続けたのでその舌を切られたが、なお喚き続け息絶えたという。
「常山の舌」の解説

「常山の舌」という表現は、たとえ危険な状況にあっても、正しいと信じることを主張し続け、それを曲げない強い意志を持つことを意味しているんだよ。この言葉の由来は、「新唐書」に記されている顔杲卿(がんこうけい)という人物のエピソードから来ているんだ。
安禄山の反乱の際、常山を守っていた顔杲卿は、善戦しても反乱軍に捕らえられてしまった。捕らえられた後も彼は安禄山を激しく非難し続けたため、反乱軍によって舌を切り取られるという悲劇に見舞われた。それでも彼は自分の信念を曲げず、最終的に命を落としたんだ。
「常山の舌」という言葉は、どんな困難や危険があっても自分の信念や正義を貫く強い意志の象徴として使われるんだね。この話は、真実や正義に対する強い信念がいかに重要であるか、そしてそれを貫くことがいかに難しいかを教えてくれるんだよ。信念を持ち続けることの大切さと、そのためには大きな犠牲が伴うこともあるという教訓が含まれているんだ。
「常山の舌」の使い方




「常山の舌」の例文

- 常山の舌というが、彼はまさにそれで忠義を貫いた。
- 彼は常山の舌だから信頼できる。
- 常山の舌のように忠誠を誓っても、日本の企業は終身雇用を保障できない。
- 舌を抜かれても常山の舌のごとく忠義を尽くす。
- 常山の舌の気概で、この会社のために身を粉にして働きますと宣言した。