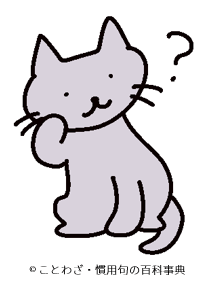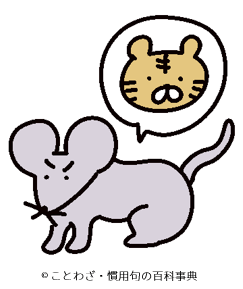【ことわざ】
寝耳に水
【読み方】
ねみみにみず
【意味】
思いがけない出来事が、突然起きてびっくりする様子。
【語源・由来】
寝ている時に、耳に水を突然注がれて、驚くことから。
【類義語】
・足下から鳥が立つ
・寝耳にすりこ木
「寝耳に水」の水とは?


「寝耳に水」は、今日でもよく使われることわざで、たいていの人が知っていて、自分でも使ったことがある人も少なくないでしょう。
突然、思いがけないことが起きて驚くことのたとえで、なぜそんなことになったのか、どうすればよいのか、まったくわからず、あわてふためいたり、困惑することを暗に示すものです。
たとえば、いつも元気にはたらき、スポーツも好み、健康になんの不安も感じていなかった人が、年に一度の集団検診を受けた結果、医者に精密検査が必要だから入院するようにいわれたら、寝耳に水でびっくりし、不安になりますね。ここでは健康の不安を例にしましたが、「寝耳に水」というのは、だいたい当人にとって不幸な事態、思わしくないことが起きたときのことです。
同じ驚くのでも、よいことの場合、この表現はほとんど使われません。強(し)いて幸運に結びつけて、「自分の作品が受賞作に選ばれたのはまったく寝耳に水だった」と言ってみても、どうもしっくりせず、違和感が残ります。
このように、ことわざに付きまとう不幸な、好ましくない雰囲気は、おそらく、このことわざの成り立ちにかかわるものと思い、その由来をあらためて考えてみました。
このことわざの由来については、大まかに二つの説があります。
一つは、驚いたことを形容する巧みなたとえで、寝ているときに突然耳に水が入ったとしたら、どんなにびっくりするか、誰でも想像がつくとする説です(たとえを比喩(ひゆ)というので、比喩説と呼ぶことにします)。眠っているときに耳に水が入ることは、実際にはまずないでしょうが、想像してみると、たしかにとてもびっくりして、どうしてそんなことが起きたのかまったくわからず、うろたえることでしょう。
もう一つの説は、ことわざの「水」を大水、つまり洪水とする説です。寝ているうちに雨が激しくなり、気がついたら洪水が押し寄せる轟音や危険を知らせる声などが聞こえ、あわてふためくということです(この説を洪水説と呼ぶことにします)。
比喩説と洪水説のどちらが正しいのでしょうか?
比喩説は、実際に寝ているときに耳に水が入るというのは、やはり不自然な感じがするのが難点でしょう。しかし、多くのことわざで、たとえ(比喩)が大きな力を発揮し、誇張(大げさにいうこと)も説得力を強めます。「船頭多くして船山へ上る」や「壁に耳あり」をみればわかるように、ことわざの比喩表現は、現実そのものである必要はなく、多くの人がなるほどと納得して使えば、フィクション(虚構)や極端な誇張であってもかまいません。比喩説はことわざのこのような性質を踏まえたものといえます。
洪水説は、比喩説の不自然さを指摘し、現実に水が耳に入ることはごく稀で、一般的ではないとします。「寝耳に入る」のは音声で、洪水(大水)の轟音(ごうおん)や危急を知らせる鐘などの音声とするのが妥当と考えます。たしかに眠っているときは、目をつむっているので見えませんが、耳はふさいでいないので、眠っていても一種の待機状態で、大きな物音や音声は耳に入り、聞こえることがあります。合理的な考え方ですが、洪水説の弱点は、これを裏付ける用例や伝承が十分に示されていないことです。ことわざの場合、論議の前提として用例は欠かせません。
二つの説はともに一長一短で、どちらが正しいと判定しかねる状況が続いていましたが、近年研究が進み、ようやく判断材料がととのってきました。これには、私も関与しています。私は洪水説に十分な用例がないことから比喩説を支持していましたが、しだいに疑問が大きくなり、二つの説をあらためて検討して、洪水説に理があると考え直しました。そして、この説を補強する用例を自分で探索してみたのです。
その結果、江戸前期の農業書『百姓伝記』に、日頃から川の堤(つつみ)を整備していれば水難から逃れられ、怠れば「寝耳に水の入る」こと疑いなし、とする用例が見つかりました。単に驚くことではなく、洪水の被害がおよぶことをはっきり示したものです。そのほか、井原西鶴『好色二代男』や『北越雪譜』、地方の災害記録などにも洪水に関連する用例をいくつも見出すことができました。さらに近代の災害資料にも、洪水(大水)をさすものがかなり出てきたのです。
ちなみに気象研究者の根本順吉氏は、「寝耳に水」について、この水を寝込んだ時にやってくる洪水と考えると理屈に合うとしています(『天候さまざま 風 土論ノート』)。 統計的に豪雨は午後10時から明け方6時までに降ることが多く、午前6時から午後10時までの約2倍になるという研究もあるとのことです(1時間あたりで比較すると約4倍になります)。
結論として「寝耳に水」の水は、元来は洪水(大水)をさしていたものと考えてよいでしょう。現代では、洪水をイメージするのは一般的でありませんが、地域によっては洪水の恐怖とともに伝承されることもあります。実際に台風による洪水被害にあった人が、「あっという間に水浸しになって、寝ている横の畳が浮きだすほどで、まったく寝耳に水というとおりでした」と語っている文献もありました(金指正三『海上社会史話』の聞き書きによる)。
(2025/4/12)
「寝耳に水」の使い方

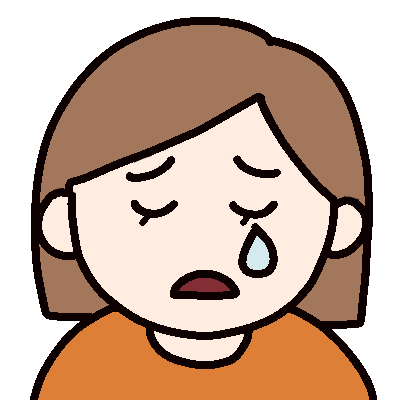


「寝耳に水」の例文

- 急に明日から会社をリストラなんて寝耳に水だ。
- 健太くんが明日引っ越しするなんて、寝耳に水だよ。せっかく仲良しになったばかりなのに。
- 両親から僕が実の息子ではないと聞かされて寝耳に水だよ。
- 君がまさかテストで100点とるなんて、寝耳に水だね。
「寝耳に水」を英語で言うと?

「寝耳に水」の英語表現をご紹介します。
※英語の声:音読さん
a bolt from the blue
- 直訳:青空から急に襲雷が出てくる
- 意味:急な出来事に驚く
pouring water into the ear while you are asleep
- 直訳:寝ている間に、耳の中に水が流れて来る。
- 意味:予期せぬ出来事が起こる。