「親に似ぬ子は鬼子」の意味(語源由来・対義語・英語訳)
【ことわざ】
親に似ぬ子は鬼子
【読み方】
おやににぬこはおにご
【意味】
子供は親に似ているので、親に似ない子供はいないということ。


子供が親に似てないっていうのは、その子の態度や言葉が悪いってことを表してるんやな。ちゃんと親子でふるまうことの大切さを教えてくれてる言葉やね。
【語源・由来】
狂言の二千石(じせんせき)に同じ台詞(せりふ)があります。
【対義語】
親に似ぬ子はなし(おやににぬこはなし)
【英語訳】
That which comes of a hen will scrape. (雌鶏から生まれたものは土を掘る=親に似ぬ子は鬼子)
「親に似ぬ子は鬼子」の解説

「親に似ぬ子は鬼子」っていうことわざは、子供が親に似ていなくて、悪いことばや態度を見せるときに使われるんだよ。
普通、親子って似ることが多いじゃない?だから、子供が親に全然似ていないと、昔の人たちは「この子は人間の子じゃなくて、鬼の子かもしれない」と冗談混じりに言ったんだよ。
でもね、本当は鬼の子なんていないから、このことわざは、子供が親の教えを全く受けず、悪い態度を見せるときに、親や周りの人が使うことがあるんだ。
たとえば、親が優しくて礼儀正しいのに、子供が言葉遣いが悪かったり、礼儀を欠いたりすると、このことわざを使うことがあるよ。
このことわざは、親が子供に対して期待するものと、子供の実際の態度とのギャップを表しているんだね。だから、このことわざからは、親の教育がどれだけ大切か、子供自身がどうあるべきかを学ぶことができるよ。
「親に似ぬ子は鬼子」の使い方




「親に似ぬ子は鬼子」の例文

- 親に似ぬ子は鬼子とはよくいったものだ、うりふたつだな。
- いい表現ではないかもしれませんが、親に似ぬ子は鬼子、一見して息子さんとわかりましたよ。
- 系列会社とはいいながら、親に似ぬ子は鬼子と言われるほど違いがあります。
- 親に似ぬ子は鬼子ですから、おとなしくしていなさい。
まとめ
鬼とは英語でdemon=悪魔、ogre=人食い鬼、gnome=地の神というふうに訳されています。日本では恐ろしい形をして人にたたりをする怪物、伝説の山男、地上の悪神などという意味があります。世界中に鬼がいるようですが、日本では仏教の影響で地獄の赤鬼と青鬼が代表的なイメージです。いずれにしても、ひと昔は子供のころにわがままをいったり、悪いことをすると先生から「鬼がくるよ」とはいわれて、おとなしくなった子供がいましたが、現在ではどうでしょう。リアルなデジタル映像やモンスター退治のゲームの発達などでちょっとやそっとの鬼ではおびえる子供はいないのではないでしょうか。逆にモンスターなんとかにびくびくしている先生がいますね。時代は変化しています。





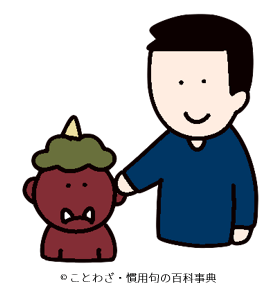









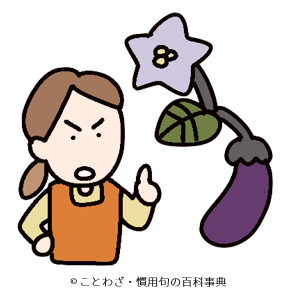
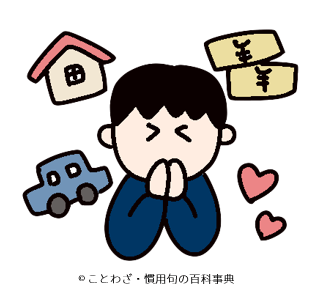
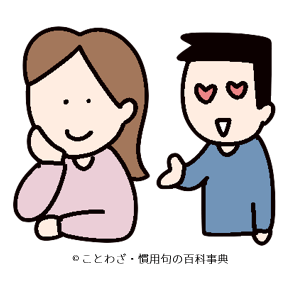
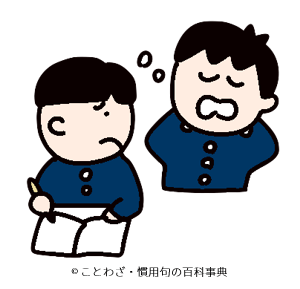






これは、子供の言動が親と大きく異なり、悪い方向に行っているときに使われることがあるんだ。