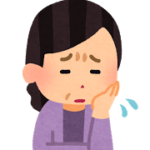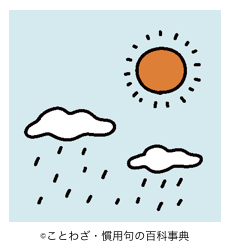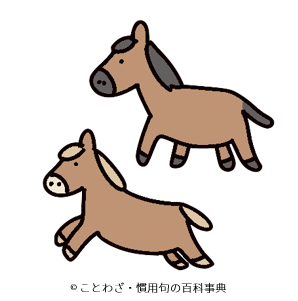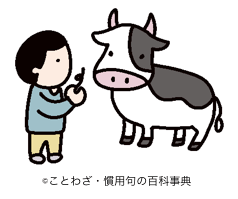「疑心暗鬼を生ず」の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)

疑心暗鬼を生ず
「疑心暗鬼を作る」「疑心暗鬼」ともいう。
【読み方】
ぎしんあんきをしょうず
【意味】
疑ってかかると、なんでもないことも不安になり、疑わしく思えるというたとえ。


考え過ぎて、ほんまは大丈夫なことも怖がっちゃうってわけか。疑う心ってこわいなぁ。
【語源・由来】
疑いの心で見ると、暗闇の中にいるはずのない鬼の姿が見えてくるということから。
【出典】
『列子』
【類義語】
・杯中の蛇影(はいちゅうのだえい)
・窃鈇の疑い(せっぷのうたがい)
・幽霊の正体見たり枯れ尾花(ゆうれいのしょうたいみたりかれおばな)
・落ち武者は薄の穂にも怖ず(おちむしゃはすすきのほにもおず)
・疑えば目に鬼を見る(うたがえばめにおにをみる)
【英語訳】
To fight with one’s own shadow.
An easy thing also looks doubtful if it sees with the mind of doubt.
「疑心暗鬼を生ず」の解説

「疑心暗鬼を生ず」っていうことわざは、ちょっと難しい言葉かもしれないけど、簡単に言うと、何かを疑い始めると、本当は大したことじゃないのに、とっても心配になったり、恐ろしく感じたりすることを言うんだよ。
たとえばね、友達と遊びに行く約束をしたけど、時間になっても友達が来ないとき。その時に、「もしかして怒ってるのかな?」とか、「僕のことを嫌いになったのかな?」って考え始めたら、どんどん不安になってしまうでしょ?でも、実はその友達はただ遅刻しただけで、怒ってもいないし、嫌いになったわけでもないんだ。そういう、疑ってばかりいると、小さなことが大きく不安に感じるっていうのが「疑心暗鬼を生ず」の意味なんだよ。
このことわざの元になったのは、「列子」という古い本の中の話で、そこに出てくる話や教えから取られているんだ。疑う心は、ちょっとしたことを大きく悪く感じる力があるから、気をつける必要があるんだね。
「疑心暗鬼を生ず」の使い方
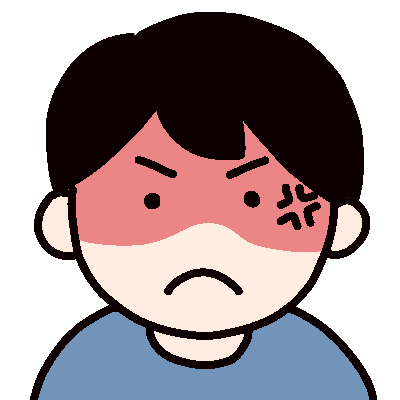

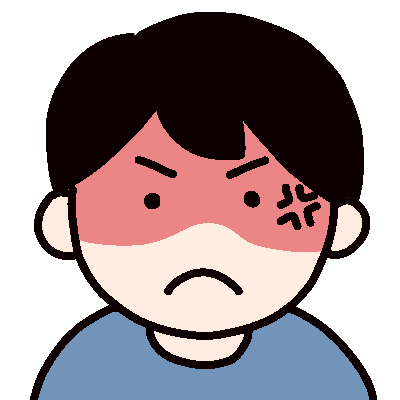
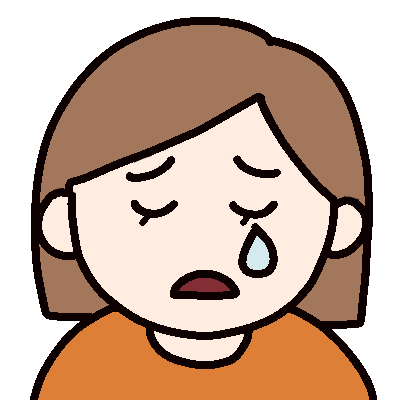
「疑心暗鬼を生ず」の例文

- 先生への密告が明らかになって、クラスメイトが疑心暗鬼を生ずことになった。
- 疑心暗鬼を生ずで、玄関に置いてあるバットまで凶器に思えてしまう。
- 疑心暗鬼を生ずというけれど、今回の事件の犯人はこのメンバーの中にいるとしか思えない。
- 近所でごみが荒らされていた。それ以来、疑心暗鬼を生ずで関係がぎくしゃくしている。
「疑心暗鬼を生ず」の文学作品などの用例
かの道なき所に道あるように覚え、水ある所に水なきように思い、狐に左右せられて進退するなどは、狐を恐るるより疑心暗鬼を生ずるに至り、一時の幻覚、妄境を現ずるのである。そのくわしき説明は、心理学を研究せねばならぬ。(井上円了の迷信解より)