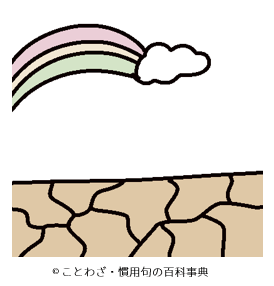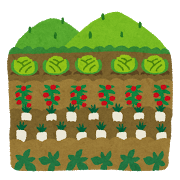【ことわざ】
花より団子
【読み方】
はなよりだんご
【意味】
花見などという風流なことよりも、食べるほうが大事というたとえ。外観よりも実質を、虚栄より実益を重んじること。また、風流を解さないことのたとえにも用いる。
【語源・由来】
花見に行っても、桜よりも茶店の団子を喜ぶことが由来。江戸版いろはかるたのひとつ。
【類義語】
・花の下より鼻の下
・一中節より鰹節
・詩を作るより田を作れ
・色気より食い気
・酒なくて何の己が桜かな
・見栄えるより頬張れ
・名を捨てて実を取る
・理詰めより重詰め
「花より団子」の使い方




「花より団子」の例文

- せっかくお花見に来たというのに、みんなお酒を買うためにずっと並んでいるんだ。これじゃあ花より団子だな。
- 花より団子というけれど、久しぶりの海外旅行なのに観光ではなく買い物ばかりに夢中になっているじゃないか。
- 映画もよかったけれど、ぼくは花より団子で、そのあとの食事の方が嬉しかった。
- この企画が通れば、社長に褒められると言うけれど、みんな昇進を狙っているなんて、まさに花より団子だ。
- 子供たちにとって初めて乗る飛行機は、景色を見るよりも機内食に夢中だ。花より団子とはこのことだろう。
- 花より団子といように、ぼくは美しいものよりも、実際に役に立つものの方がよい。
「花より団子」を英語で言うと?

「花より団子」の英語表現をご紹介します。
※英語の声:音読さん
Dumplings rather than flowers.
- 直訳:花よりもむしろ餃子。
- 意味:見た目が美しいものより実用性のあるものの方がいい。
Better have meat than fine clothes.
- 意味:美しい衣服よりも食べ物があるほうがよい。
Bread is better than the songs of birds.
- 直訳:鳥の歌声よりパンの方が良い。
- 意味:綺麗な思い出よりも実用的なものの方がいい。
People are more interested in the practical over the aesthetic.
- 直訳:人は美学よりも実用的なものにもっと興味を示す。
- 意味:美しいものよりも実用的のあるものの方がいい。
Pudding before praise.
- 直訳:賞賛の前にプリン。
- 意味:褒め言葉をもらうよりも食べる方が大事。
コラム:「花より団子」に込められた思い


毎年春になると、桜がいつ咲くか話題となり、天気予報では「桜前線」ということばも使われます。
南北に長い日本列島では地域によって桜の開花が1カ月以上ずれ、期日は異なりますが、各地で花見が盛んに行なわれます。
花見は、学校や職場、ご近所などの気の合う人たちと桜が見頃の場所をおとずれ、いっしょに食べたり、飲んだり、歌ったりして楽しむもので、春の国民的行事といってよいでしょう。
そんなときによく耳にし口にするのが「花より団子」です。
いろはかるたの文句にもあり、子どもでも知っているものですが、あらためて見直すと、日本のことわざの特徴がよくあらわれていて、じっくり味わってみたい表現です。
まず、表現がごく短いこと--「ハナヨリダンゴ」と、わずか7音です。
ことわざは短いのが特徴のひとつですが、ことわざのなかでも「糠に釘」の5音や「猫に小判」、「寝耳に水」の6音などに次いで、かなり短いものです。
しかも、短いけれど、聞いたときに具体的で鮮明なイメージ(映像)が浮かんできますね。「花」はお花見の花、つまり桜の花です。
私たちは梅や菊など、季節の旬(しゅん)の花を見に行くこともありますが、ふつうは「花見」といわず、「梅見」や「菊見」などといいます。
「団子」は、やはり花見の団子で、串(くし)にさした団子を思い浮かべるでしょう。
「花」と「団子」のイメージは、具体的なものの映像だけでなく、シンボル(象徴)としても重要な役割をはたし、比喩(たとえ)としての意味を大きくひろげてくれます。
桜の「花」は、比喩として美しいものや趣(おもむき)のある風流(ふうりゅう)なもの、「団子」は食べて満足できるものをそれぞれ意味します。
そして、さらにこの二つの対照的なものは、比喩の意味をひろげ、見た目や品位に対する実質や実利、ということにもなるのです。
ことわざは、文を最後まではっきり示していません(これも日本のことわざによくみられる特徴のひとつです)が、わかりやすくいうと、「花」より「団子」〔がよい〕ということです。
美や風流よりお腹を満たすものがよい、見かけや品位より実質・実利がよいということにもなります。
ただし、このことわざにこめられた思いはかなり複雑で、こうした意味を全面的によしとして使うとはかぎりません。
使いようによってニュアンス(意味あい)が大きく変わり、むしろ逆に好ましくないものとして使うことがあるので、注意が必要です。
たとえば、他人を「あいつは花より団子だ」と言った場合、風流のわからない不粋(ぶすい)な者という皮肉をこめることも少なくないのです。
このことわざが使われはじめたころの古い用例をみてみましょう。
室町時代の終わりころ(1569年)、京都近辺の国々を制圧した織田信長は、将軍足利義昭の二条御所を堅固な石垣づくりにし、自ら音頭をとってお祭り気分で笛や太鼓、鼓ではやしたてながら大人数で藤戸石(ふじといし)という大きな名石を運びこみました。
そのころの落書(らくしょ。だれが書いたわからないもの)の狂歌(風刺する和歌)がつたえられています(「寒川入道筆記」による)。
(花よりも団子の京となってしまったことよ、今日もいしいし明日もいしいしだ)
「いしいし」は、女房詞(にょうぼうことば。宮中の女性たちのことば)で団子をさし、「石々」とかけています。
風流のわからない者(信長)が支配し、連日石を運ぶために騒々しくなった京都を嘆かわしく感じたものといってよいでしょう。
もちろん、ことわざは肯定的に使ってもよく、幼い子どもが無邪気に花より団子がいいという場合もあれば、大人が風流だけでは食べていけないという本音で口にすることもあります。
ただ、花見に「花」と「団子」がともに必要なように、多くの人にとっては、生きていくために実利が欠かせませんが、同時に美しいものに心ひかれるのも真実で、どちらか一方だけではない複雑な思いがあるといってよいでしょう。
俳人の一茶は、その微妙な思いを次のように詠(よ)んでいました。 「有りやうは我も花より団子かな」

©2024 Yoshikatsu KITAMURA