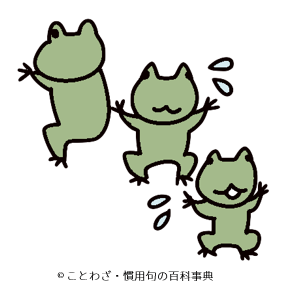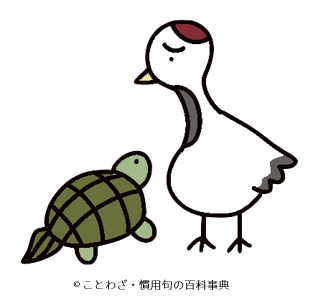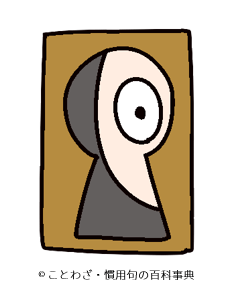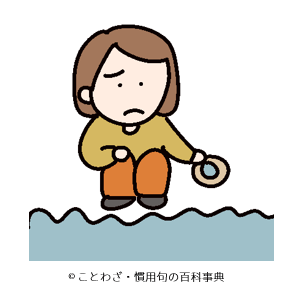「鼎の軽重を問う」の意味(語源由来・出典・英語訳)
【ことわざ】
鼎の軽重を問う
【読み方】
かなえのけいちょうをとう
【意味】
統治者を軽んじ、これに代わって支配者になろうとする野心のあること。転じて、ある人の実力を疑ってその地位を覆そうとすることのたとえ。


そんな鍋の重さを問うてみるってことは、要するに「お前、本当にええのか?」って疑うことやね。こういう態度は、ちょっと危険やな。人を落とそうとする心は、うまくいかんことが多いから、注意せなあかんね。
【語源・由来】
周の定王の時、楚の荘王が、天下を取ったときに運ぶことを考えて、周室伝国の宝器である九鼎の大小・軽重をたずねた故事から。
【出典】
『春秋左氏伝・宣公三年』
【英語訳】
・to call one’s ability into question
・to weigh one’s ability
「鼎の軽重を問う」の解説

このことわざ「鼎の軽重を問う」も少し難しい言葉が使われているね。でも大丈夫、一緒にわかりやすく説明してみよう!
まず、「鼎の軽重を問う」の背景には、昔の中国の話があるんだよ。楚の荘王という人が、周という国を見下して、その国の宝物である九鼎という大きな鍋のサイズや重さを問いただしたことから来ているんだ。
「鼎」というのは、大きな三本足の鍋で、昔の中国ではとても重要なものだったんだよ。九鼎は特に価値のあるもので、国の権威や力を象徴していたの。
このことわざが言いたいことは、自分より上の人や権威ある人の能力や力を疑って、その人の地位から引きずり下ろそうとする態度を表しているんだ。
例えば、クラスで先生の言うことに反抗して、先生の指示を無視したり、先生の能力を疑ったりすること。そういう態度が「鼎の軽重を問う」に当たるんだよ。
これは、人の上に立つ人や大切な人に対して、尊敬の気持ちを持たないで、かえってその人を倒そうとするような態度がどれだけよくないか、教えているんだね。
だから、先生や親、リーダーなど、自分より上の立場にいる人に対しては、ちゃんと尊敬の気持ちを持って、協力的な態度を取るようにしよう。そうすることで、自分も成長できるし、みんなと仲良くやっていけるんだよ。
「鼎の軽重を問う」の使い方




「鼎の軽重を問う」の例文

- 彼はいつも人によって態度を変えている。部下にあの姿が露呈したら鼎の軽重を問われてしまうだろう。
- あまりにも不甲斐ない政策ばかりを打ち立てていては、内閣が国民から鼎の軽重を問われる日もそう遠くないだろう。
- あの社長に対して不満を抱いているだなんて。君は鼎の軽重を問うつもりかね。
- 鼎の軽重を問うというどころか、全員があのリーダーに対しての疑念が確信に変わっている。
「鼎の軽重を問う」の文学作品などの用例
もし、この二人が坂田に敗れるとすれば、折角争い獲った名人位も有名無実なものとなってしまうだらう。つまりは、坂田対両八段の対局は名人位の鼎の軽重を問うものであった。花田・木村としては負けるに負けられぬところであつた。(織田作之助の聴雨より)