【ことわざ】
我が身を抓って人の痛さを知れ
【読み方】
わがみをつねってひとのいたさをしれ
【意味】
人の痛みや苦しみを自分のことのように考えて、相手を思いやるようにしなさい、ということ。自分がされていやなことは、相手にするなということ。
【類義語】
・己の欲せざる所は人に施す勿れ
【英語】
Judge of other’s feeling by your own.
「我が身を抓って人の痛さを知れ」の使い方

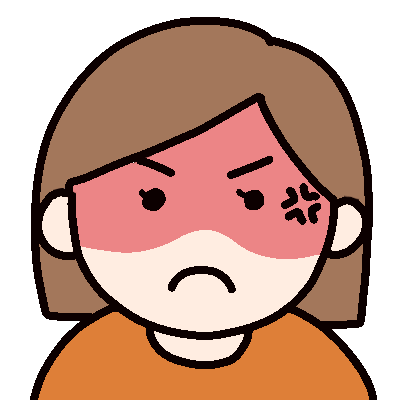


「我が身を抓って人の痛さを知れ」の例文

- グループ全員が相互に助け合うことが大切です。我が身を抓って人の痛さを知れというようにほかの人のことを思いやりましょう。
- 逆の立場で考えて見ることが大事です。別な言い方をすれば我が身を抓って人の痛さを知れということです。
- 我が身を抓って人の痛さを知れとはいわれますが、自分では気付かずにいる場合が多くあります。
- 健太くんと喧嘩をして、つい健太くんの悪口を言ったけれど、自分が同じことを言われたらとても悲しいだろうと思って反省した。我が身を抓って人の痛さを知れ。明日健太くんに謝ろう。
- 相手の気持ちを理解するためには、我が身を抓って人の痛さを知れということをもう一度真剣に考えて見る必要があります。
北村孝一コラム:“わが身をつねって人の痛さを知れ” と北条重時


“わが身をつねって人の痛さを知れ” と北条重時
「他人の痛みがわかる人になれ」と、よく言われます。これは人間として、とても大切なことです。でも、どうすれば、人の痛みがわかるのでしょうか。
ことわざは、「わが身をつねって人の痛さを知れ」といいます。たしかに自分の体をつねってみれば、つねられた人がどれほど痛いか、よくわかるはずです。
しかし、私もそうですが、本当にわが身をつねることは、実際にはなかなかできません。ほんのわずかでも痛ければ、無意識のうちにすぐ手をゆるめてしまうからです。それくらい人間は自分の痛みには敏感で、逆に他人の痛みには鈍感なのです。
もしも君がだれかをつねったり、たたいたり、乱暴なことをしたら、相手がどんなに痛いか、どんな思いをするか、考えてみましょう。自分がそんなことをされたら、もちろん痛いし、いやですね。
自分が相手と同じ立場だったら、体が痛いだけでなく、どんなつらい思いをするか、心の痛みもよく考えて、人を思いやらなくてはいけませんね。
このことわざは、多くの人が幼いころ耳にしたことのある表現でしょう。時には他の子どもに乱暴してしまい、母親にしかられ、少しつねられたこともあったかもしれません。ことわざそのものを引かなくても、同じ発想がいまも子育てのなかで生きているといってよいでしょう。
鎌倉幕府の連署(れんしょ。執権を補佐する)という要職にあった北条重時(ほうじょうしげとき、1198~1261)は、仏教のとても熱心な信者で、引退後に出家し、鎌倉の郊外に極楽寺を開きました。晩年の重時は極楽寺殿と呼ばれ、子孫に「極楽寺殿御消息」という家訓(家の教え)をのこしていて、その中に次のような一節があります。
★「わが身をすこしなりとも、切りも突きもして見るに、苦なき事あるべからず。女などのたとえに、身をつみて人のいたさをしると申(もうす)。本説ある事也」(自分の体をほんのすこしでも切ったり突いたりしてみれば、苦痛がないことはありえない。女性などが口にすることわざに、身をつねって人の痛さを知るということがある。根拠のあることである。)
この「たとえ」はことわざのことで、「身をつむ」は身をつねる、「本説ある」は道理にかなっているということでしょう。750 年余り前から現在とほぼ同じことわざがあり、当時の女性たちが口にしていたことがわかります。
このことわざは北条重時の家訓に由来するとしているものがありますが、そうではなく、その時代に女性などが口にしていたことわざを重時が家訓に引いて、書きのこしていたということです。女性の地位が低かった時代に、重時は女性のことばにもきちんと耳をかたむけ、正当に評価できる器(うつわ)の大きな、心のひろい人物でした。
格言では、「己(おのれ)の欲(ほっ)せざるところを人に施(ほどこ)すなかれ」(論語)といいます。自分が望まないことを人にしてはいけないということですが、中国から入ってきた漢文によるもので、少しかしこまった、むずかしい表現ですね。これに対してことわざは幼い子どもにもわかる、やさしい言い方で共感を引き出し、相手を思いやる心が大切なことを教えてくれています。(2025/7/1)























