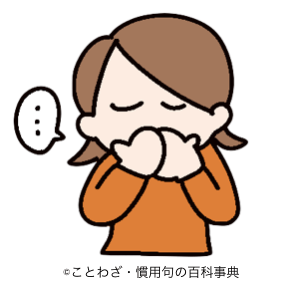「和して同ぜず」の意味とは?(出典・類義語・対義語・英語訳)

【ことわざ】
和して同ぜず
【読み方】
わしてどうぜず
【意味】
人と争わず仲良くするが、自分の意見はしっかり守っていてむやみに人に同調したりしないという意味。


【出典】
「論語」「子路」
【類義語】
・君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
【対義語】
・同じて和せず
【英語訳】
One must draw the line somewhere.
harmonize but not agree (harmonise)
「和して同ぜず」の故事
【故事】
「論語」「子路」から。「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」君子は人と協調するが、安易に同調したり雷同したりすることはない。主体的に人とつき合うべきであるという言葉。

「和して同ぜず」の由来は、孔子の教えから来ているんだ。孔子は、人々との関わり方について「和」(調和)と「同」(同調)という二つの概念を提唱したよ。
「和」は、主体性を保ちつつ他人と親しく交流し、互いに助け合うことを指している。つまり、他人との関係を大切にしつつ、自分自身の考えや意見もしっかり持つことだよ。
一方、「同」は、自分の考えがないままに他人の言動に無意識に同調することを指している。これは、ただ他人に従って行動するだけで、自己の主体性や意見がない状態を示しているんだ。
孔子は、君子(道徳的に優れた人)のふるまい方として、「お互いに助け合いながらも、無闇に同調して従ったりはしない」と述べている。これが「和して同ぜず」の語源となっているよ。つまり、他人と協調しながらも、自己の主体性を保つことの重要性を示しているんだ。
「和して同ぜず」の使い方

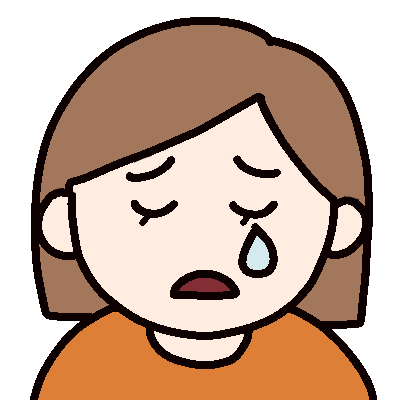

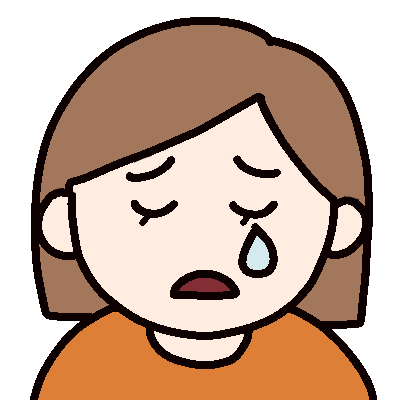
「和して同ぜず」の例文

- 和して同ぜずという言葉があるように、僕はこの会社が好きだから、会社の存続のためにその企画に反対する。
- 彼は、和して同ぜずという言葉のような人で、僕が悪いことをしたときはちゃんと諫めてくれるし、うれしいときは一緒に喜んでくれるかけがえのない友である。
- 僕は、この店が長く続いてほしいと思っているので、和して同ぜずの精神で、おいしくない時はそう伝える。
- 父も母も、和して同ぜずという言葉のように、相手の悪いところは、はっきり伝え、そして伝えられた方はそれを真摯に受け止め、とてもいい関係を築いている。
- 和して同ぜずという言葉が好きだし、そうなりたいが、同ぜずを貫くことでいじめられることが怖いとも思う。