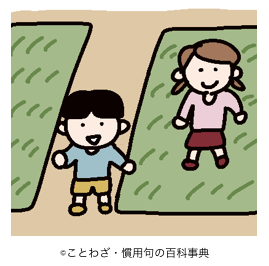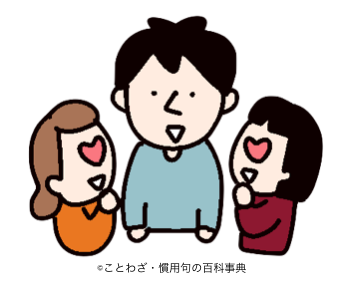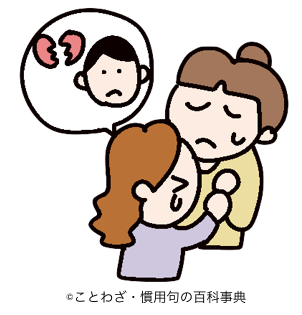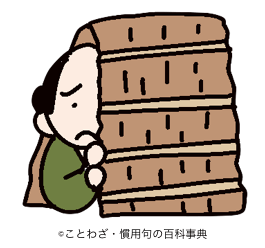【ことわざ】
秋茄子は嫁に食わすな
【読み方】
あきなすはよめにくわすな
秋茄子は「あきなすび」と読む場合もある。
【意味】
秋にできるなすは美味しいから嫁には食べさせるなという、姑から嫁への意地悪なことば。または、茄子は体を冷やすので嫁には食べさせないほうがよいというお嫁さんを大切に思う言葉。二つの意味がある。
【語源・由来】
秋茄子はおいしいから嫁に食べさせないという意地悪な意味。秋茄子は身体を冷やすため、または種子が少ないため、子宝に恵まれなくなるため食べさせないという思いやりのことばとする説もある。
【類義語】
・秋魳は嫁に食わすな
・秋鯖は嫁に食わすな
・五月蕨は嫁に食わすな
【対義語】
・秋茄子嫁に食わせよ
【英語】
Don’t feed your wife autumn eggplant.
Don’t let your wife have autumn eggplant.
【スポンサーリンク】
「秋茄子は嫁に食わすな」の使い方

うちのおばあちゃんが、「秋茄子は嫁に食わすな」って言ってるのを聞いたんだけど、どういう意味なんだろう?

昔からあることわざだよね。いろんな説があるみたいだけど、体を冷やしやすい茄子を大事なお嫁さんに食べさせないほうがいい、っていう優しさの意味もあるんだって。

へえ、じゃあ嫁いじめのことばじゃないんだ? おいしいから食べさせたくないっていう、ちょっと意地悪な意味かと思ってた。

実際には「おいしい秋茄子をあげたくない」って説もあるみたい。だから、体を気づかう優しさなのか、意地悪なのか、どちらとも取れるところがおもしろいよね。
【スポンサーリンク】
「秋茄子は嫁に食わすな」の例文

- 秋茄子は嫁に食わすなというように、おいしいものを食べさせるのはもったいない。
- うちの嫁はとても優しくていい娘だから、秋茄子は嫁に食わすなと体を気遣うように伝えた。
- あれほど意地が悪い嫁には、秋茄子は嫁に食わすなというように、うまいものは食べさせないようにしている。
- 秋茄子は嫁に食わすなといいますが、なすがおいしい季節になりましたね。