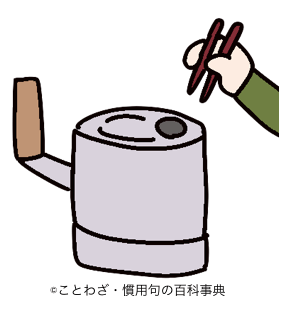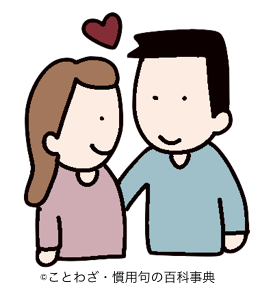【ことわざ】
一馬の奔る、一毛の動かざるは無し
【読み方】
いちばのはしる、いちもうのうごかざるはなし
【意味】
ある集団の中心になる人物が行動を起こすと、それと一緒に周りの人も動き出すこと。
【語源・由来】
庾信(ゆしん)、中国は南北朝の時代、南朝より使者として北朝に赴いて故郷の国が滅亡し、やむを得ず北方王朝で仕官し続けたまま生涯を終えた亡国の詩人で、数ある書のうちのひとつ「擬連珠(ぎれんじゅ)」の中の一文「一馬の奔る、一毛の動かざるは無し。一舟の覆(くつがえ)る、一物として沈まざるは無し」が語源です。
【スポンサーリンク】
「一馬の奔る、一毛の動かざるは無し」の使い方

東京マラソンの放送見た?

見たよ。すごい人波だったね。

一馬の奔る、一毛の動かざるは無しっていうスタートシーンだったわ。

僕も大きくなったっら挑戦してみたいな。
「一馬の奔る、一毛の動かざるは無し」の例文
- 新しい携帯電話が発売されて、多くの人が一馬の奔る、一毛の動かざるは無しがごとく店頭にあふれた。
- 流行とは恐ろしいもので、消費者は今日売れていたものから離れて、明日には一馬の奔る、一毛の動かざるは無しと新製品に走る。
- 選挙は予想どうりにはいかない。ちょっとしたことで一馬の奔る、一毛の動かざるは無しというように票がなびく。
- 一馬の奔る、一毛の動かざるは無し、我々がいくら止めようとしても無理でしょう。
まとめ
南朝から北朝に派遣され、その間に母国が滅ぼされ、その後優秀なために北朝に仕えることとなった庾信は、最後まで亡国の悲しみと望郷の思いと自己の悲劇を詠み続けたといわれています。大変難しいことわざです。皆さんはどう解釈しますか。