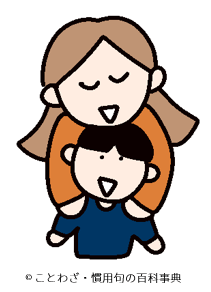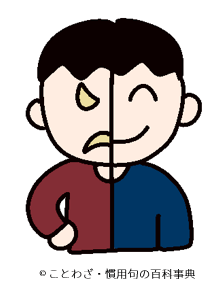目次
「船頭多くして船山に上る」とは

読み方・意味
- ことわざ:船頭多くして船山に上る
- 読み方:せんどうおおくしてふねやまにのぼる
- 意味:指図する人が多すぎると混乱して、ものごとがうまく進まず、とんでもない結果になりかねないというたとえ。
このことわざは、一隻の船に船頭(かじを取る人)が多すぎると、それぞれが好き勝手に指示を出すため、船は正しい方向へ進めず、ついには海ではなく山の方へ行ってしまう、というありえない結末をたとえた表現です。
つまり、指図をする人間が多すぎると、意見がバラバラになり、物事がまとまらず、とんでもない方向へ進んでしまうという意味です。
特にチームや組織で何かを進めるとき、リーダーシップが複数存在して対立すると、全体が混乱しやすく、最終的には失敗や見当違いな結果を招くという教訓が込められています。
このことわざは、学校でのグループ活動や仕事など、誰かがリーダーシップを取るべき場面で特に役立つ戒めとして使われることが多いです。
「みんなが自分の意見ばかり主張していては、物事は前に進まないよ」というニュアンスを含んでおり、適切な指揮系統の大切さを説いています。
「船頭多くして船山に上る」の語源・由来
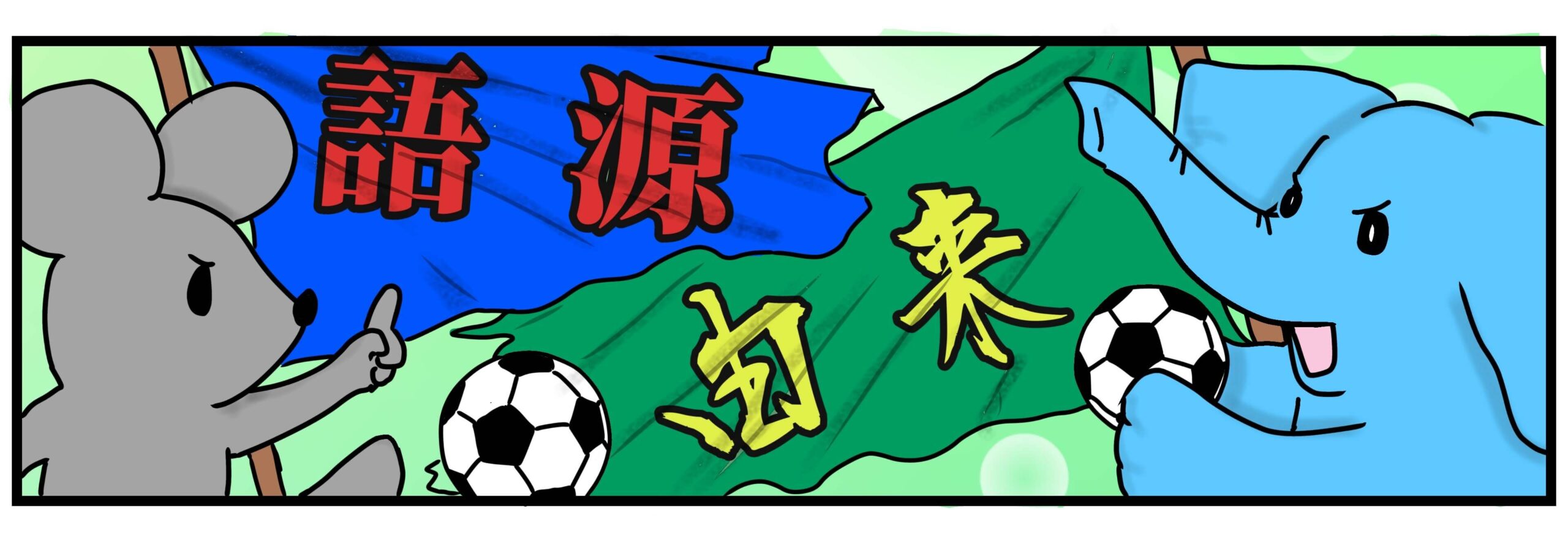
ことわざの構造と比喩の特徴
「船頭多くして船山に上る」は、一見すると現実離れした光景――船が山にのぼるというありえない出来事――を描いていますが、これは意図的な誇張表現(誇張法)によって、意味を強く印象づけるために工夫された比喩です。
この「船頭」とは、単なる渡し舟の漕ぎ手ではなく、大型の和船などを指揮する船長クラスの存在を指します。
本来一人であるべき指揮官が複数いたらどうなるか、という仮定の話に基づいています。
そしてその結果、目的地であるはずの「海」ではなく、まったく不適切な方向、つまり「山」に船が上る、という不条理な結末をもって、統率の欠如による混乱と失敗を象徴しています。
歴史的背景と用例
このことわざは16世紀頃の用例が確認されており、日本でも非常に古くから使われていた表現のひとつです。
時代を経てさまざまな形で語られており、語尾の「多くして」は「多うて」や「多くて」とも言われ、「上る」は「着く」「参る」などのバリエーションも存在します。
船と山という、だれにでもわかりやすい日常的な語彙を使って、強烈なイメージを喚起するこの表現は、庶民の間にも広く浸透してきました。
そのため、今日では「船頭多くして」だけで意味が通じるほど、ことわざとしての認知度が高いものです。
語源とされる中国の故事成語
明確な由来が特定されているわけではありませんが、古代中国の故事成語に類似の考え方が見られます。
それが「木匠多、蓋歪房」という言葉です。
意味は、「大工が多すぎると、家の屋根が歪んでしまう」というもので、指示や意見が多すぎると、かえって物事がうまくいかなくなるという教訓を含んでいます。
このように、日本独自の比喩表現でありながら、中国の思想や文化の影響を受けて成立した可能性が高いと考えられています。
「船頭多くして船山に上る」の使い方




「船頭多くして船山に上る」の例文
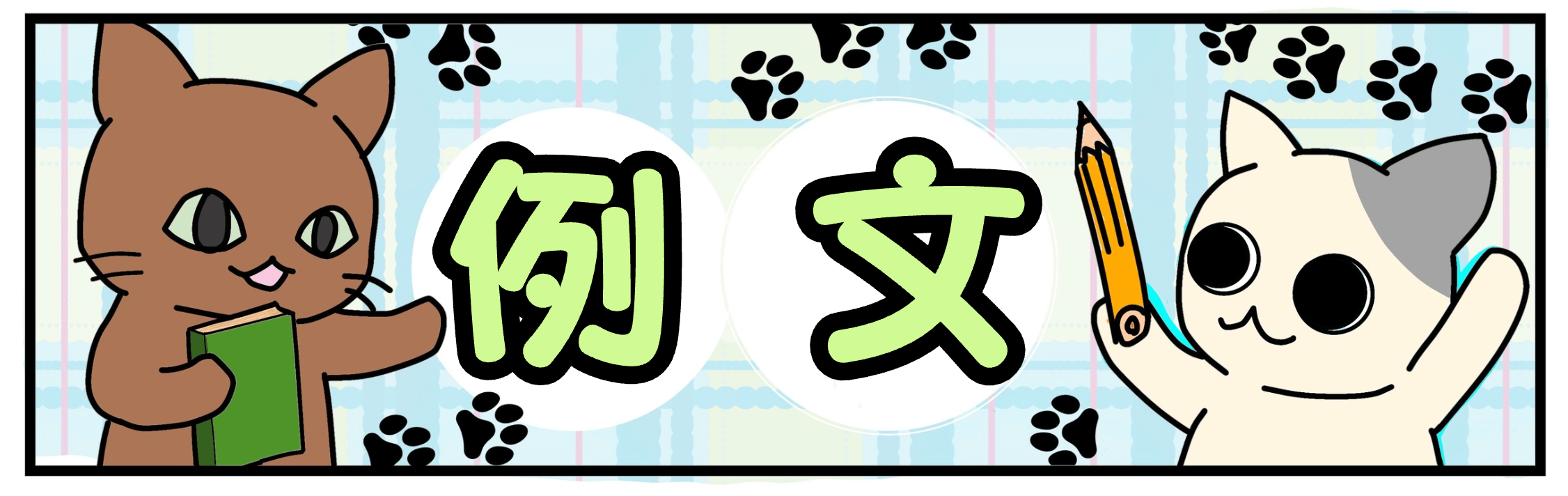
- 文化祭の出し物を決める会議で、みんなが勝手に意見を言いすぎて、結局まとまらなかった。まさに船頭多くして船山に上るだね。
- チームにリーダーが3人もいたら、誰の言うことを聞けばいいかわからなくて混乱するよ。船頭多くして船山に上るってやつさ。
- 晩ご飯のメニューを家族みんなで決めようとしたけど、意見が割れて決まらない。これじゃ船頭多くして船山に上るよ〜。
- みんなが自分のやり方で進めようとしていたら、案の定トラブルになった。やっぱり誰か一人が指揮しないと、船頭多くして船山に上るってことだ。
- デザイン会議で全員が細かく口を出してきて、結局どんなコンセプトかも分からなくなった。船頭多くして船山に上る、とはこのことだね。
文学作品などの用例
多作して駄作を作らぬ方法として、私は探偵作家に合作をすすめたい。
外国には二人、三人合作して一人名前の探偵作家はかなり存在するのであるが、日本にはまだ現れないようである。
推理小説ぐらい、合作に適したものはないのである。なぜなら、根がパズルであるから、三人よれば文殊の智恵という奴で、一人だと視角が限定されるのを、合作では、それが防げる。智恵を持ち寄ってパズルの高層建築を骨組堅く組み上げて行く。
十人二十人となっては船頭多くして船山に登る、という怖れになるが、五人ぐらいまでの合作は巧く行くと私は思う。(坂口安吾『探偵小説とは』)
「船頭多くして船山に上る」の類義語・似たことわざ

- 築室道謀
- 家を道端に作れば三年成らず
- 下手の大連れ
- 役人多くして事絶えず
- 舎を道辺に作れば三年にして成らず
「船頭多くして船山に上る」の対義語

「船頭多くして船山に上る」の注意点
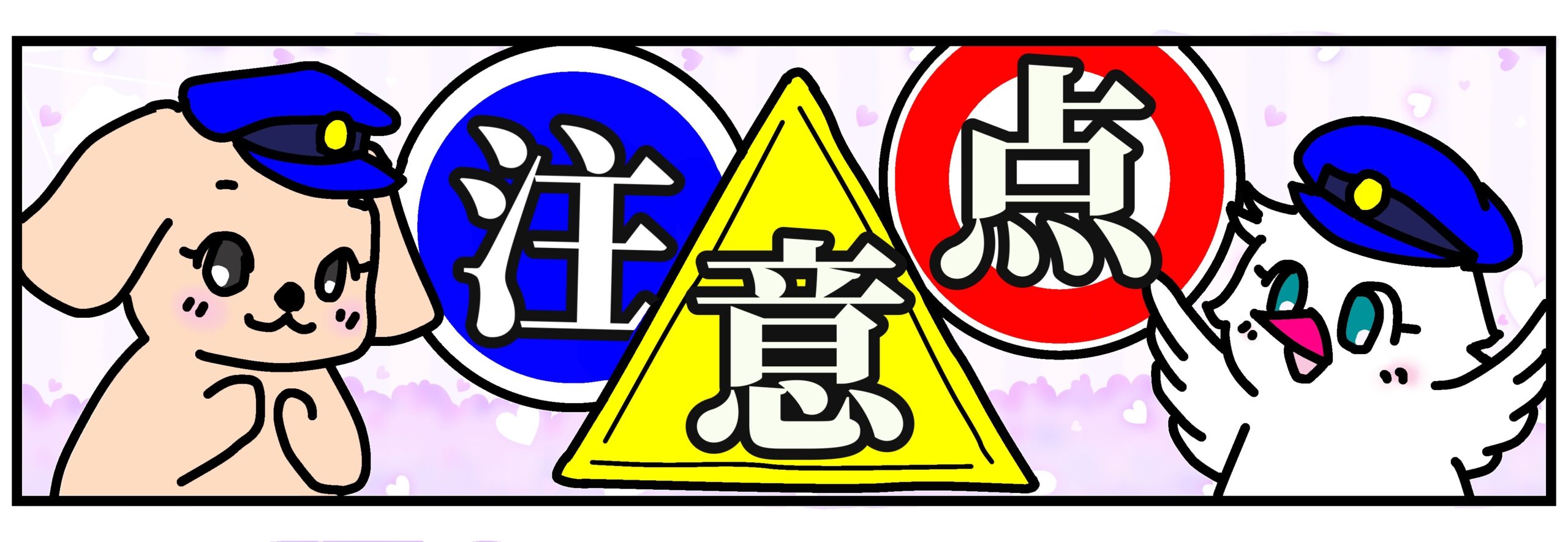
- 協力やチームワークを褒める場面には使わない
→ みんなで力を合わせて成功したときに使うと、意味の取り違いになる。
(例:✕「難しい課題だったけど、みんなが意見を出して成功した。まさに船頭多くして船山に上るだった!」→ 本来は混乱や失敗を表すことわざ) - 指導役が多すぎて方向性が定まらない場面で使う
→ 誰が中心になるべきか曖昧なときに「まとめる人が必要だね」という提案とセットで使うと、建設的な印象になる。
「船頭多くして船山に上る」の英語表現
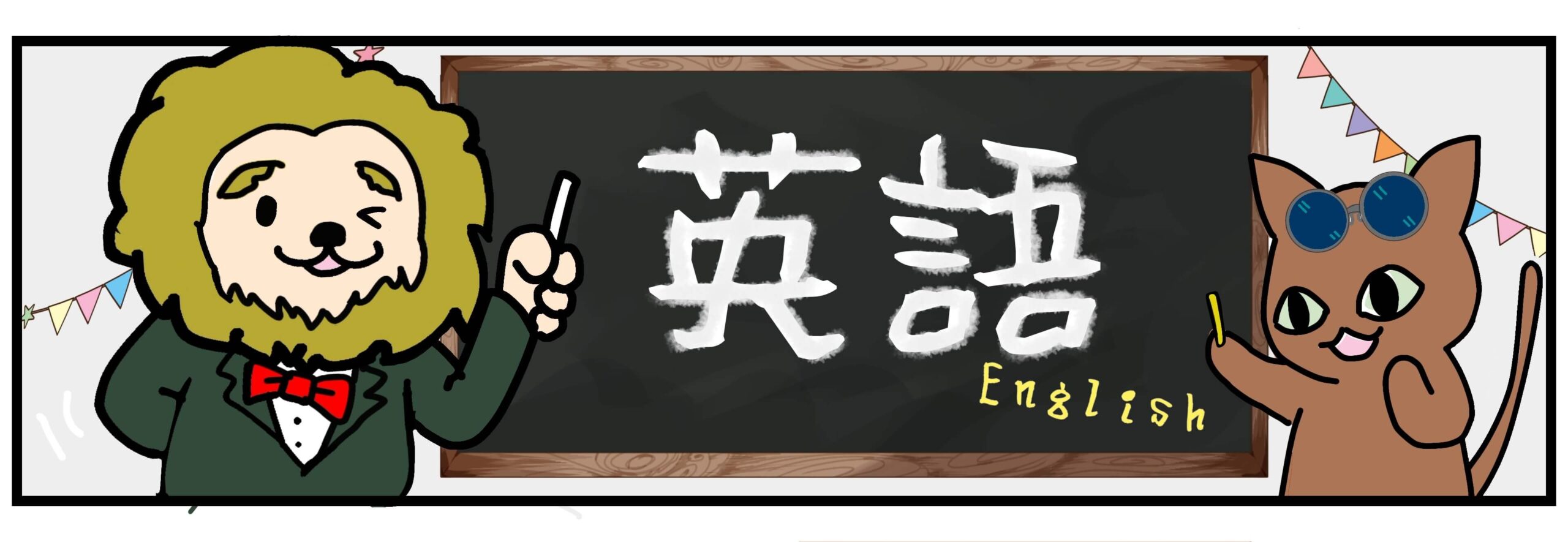
Too many cooks spoil the broth.
直訳:コックが多すぎるとスープがまずくなる。
意味:指図する人が多すぎると、物事がうまくいかなくなるというたとえ。
(※日本語の「船頭多くして船山に上る」に相当)
例文:
Everyone wanted to lead the project, but nothing got done. Too many cooks spoil the broth.
(みんながプロジェクトを仕切ろうとして、結局なにも進まなかった。指図する人が多すぎたんだよ。)