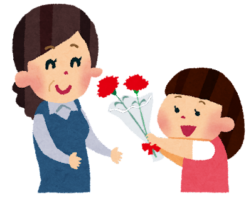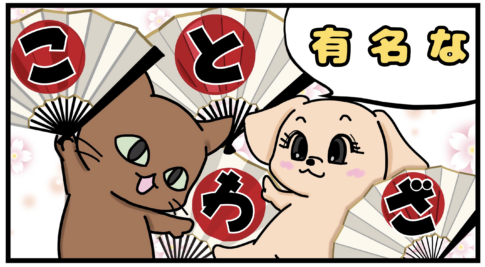犬は古来より様々な文化において、私たちの生活や心に寄り添ってきました。その結果、日本には数多くの犬に関することわざや慣用句が生まれています。
ことわざは、時代や地域の背景に基づいた独特な知恵や考え方を伝える言葉の宝庫です。それぞれのことわざには、人間の生活や心理を犬を通じて示唆する意味が込められています。
この記事では、犬にまつわることわざ一覧をご紹介します。
また、それぞれのことわざの背後にある意味や教訓も解説していきますので、犬好きならずとも、人間関係や自己理解のために役立つことでしょう。どうぞお楽しみに!
日本以外の世界の犬のことわざは、「海外の犬のことわざ一覧」をご覧ください。
猫のことわざは、「猫のことわざ・慣用句一覧(意味付き)」をご覧ください。
犬や猫以外にも、様々な動物のことわざに関しては、「動物のことわざ一覧」をご覧ください。
目次
人の生活に役立つ!犬のことわざ・慣用句

犬に論語
わからないものに何をいっても、なんの効果もなく無駄なことのたとえ。
また、何の役にもたたないということ。どのように説いて聞かせても無駄なことのたとえ。
犬にも食わせず棚にも置かず
気前よく犬に与えるわけではないけど、棚に置くわけでもない。ケチったせいで、結局、何の役にも立たせないまま、無駄にしてしまうということ。
犬も歩けば棒に当たる
①出しゃばって何かをしようとすれば、思いがけない災難にあうということ。
②行動すれば、思いがけない幸せにめぐり会うことがある。
犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ
三日飼ってもらった犬はその恩を三年間も覚えているということから、恩を忘れてしまいがちな人間への戒めに使うことば。
猫の子はなぶると痩せ、犬ころはなぶると肥ゆる
猫は人間にかまわれるとストレスが溜まって痩せてしまうが、犬は喜んで懐いてくる。犬と猫の習性の違いを表現した慣用句。
犬こ戻り
昔の犬は仲が良い近所の家に少しだけ立ち寄る習性があったことから、行ってすぐ帰ることを指す。
犬骨折る
物事が徒労に終わること。労力を惜しまずに頑張ったのに、何の結果も残らなかったという意味。
犬の川端歩き
所持金がないのに店の前をぶらつくこと。また、いくら奔走しても得られるものがないこと。
犬の道中口食って一杯
食べ物を漁る野良犬がその日を生きるだけでも精一杯なように、ちゃんと毎日食べるだけも大変な状況を意味する。
浦場の犬は鰯を食わぬ
漁村で暮らす犬は、魚肉ばかり食べているため、イワシのような普通の魚は食べない。贅沢が身につくと、生活スタイルが変わるということ。
犬猿の仲
犬と猿のように仲の悪いことのたとえ。
犬は犬を食わない
「仲間同士で争っていてどうするんだ」というイギリスのことわざ。
主憂うれば犬痩す
主人が悩んでいると、その飼い犬も心配のあまり痩せてしまうということ。
影も無いのに犬は吠えぬ
根拠なしに噂が立つことはない。
杖の下に回る犬は打てぬ
尻尾を振って杖の下からじゃれついてくる犬は、打とうと思っても情が湧いてしまってできない。自分を慕ってくれる者に非道な仕打ちはできないという例え。
吠える犬は打たれる
吠えてばかりいる犬が飼い主に打たれるように、人の悪口や威勢の良いことばかり言っていると、周囲の反感を買ってひどい目にあうという意味。
吠える犬は噛みつかぬ
噛み付く勇気のない犬ほど吠えることから、威勢のいい者に限って実力がないこと。
吠える犬にけしかける
勢いのある者をけしかけて、余計に調子づかせること。
食わぬ犬をけしかける
気のすすまないものをそそのかすこと。
殿の犬には食われ損
殿様の飼い犬に噛まれても文句が言えないため、我慢するしかない。直接の利害がある偉い人には、何をされても泣き寝入りせざるを得ないという意味。
飼い葉桶の中の犬
自分には必要のないのに他人に使わせない意地悪な人のこと。飼い葉桶の中で犬が横になって、牛たちが干し草を食べようとすると邪魔をしたという話から。
盗人が犬に食われた
泥棒が番犬に噛まれたとしても文句が言えないということから、自分が正しくなければ、他人に責められても何の反論もできないという例え。
乳狗虎を博ち、伏鶏狸を博つ
子供への愛情によって、弱者が強くなることの例え。中国の故事から。子犬に乳を飲ませている母犬は虎にも立ち向かい、卵を温めている鶏は狸にも飛びかかっていくことから。
老犬虚に吠えず
老犬が吠えるのには何か理由がある。老人の忠告には素直に耳を貸すべきという意味。
ビジネスで活用できる!犬のことわざ・慣用句

居候は犬にも可愛がられよ
居候は非常に立場が弱いため、その家の飼い犬にも好かれておいた方がいいということ。
犬威しの意見で行かず
犬を脅すように、ただ大きな声で叱ったぐらいでは、全く効果がないという例え。
犬ことわらしは物こさ付く
青森県のことわざで、犬と子供は物をくれる人に懐くということ。
犬の逃げ吠え
臆病な犬が逃げながらも吠える様子から、論争に負けたくせに減らず口や負け惜しみを言って逃げることの例え。
能なし犬の高吠え
大した実力のない者に限って、大げさな発言をしたり、ちょっとしたことで大騒ぎするということ。
犬は骨で叩けば吠えない
肉が付いた骨で叩かれると、犬は後で食べられると期待して逆らうことはないということから、利益が絡むと侮辱されても我慢するという意味。
犬が熱湯を浴びせられる
タイのことわざで、犬が餌を探しに家の中に入ってきた時、お湯をかけて追っ払うと、あわてて走り出すことから、遊びに行った場所で苦労をするという意味。そこから転じて、不意に緊急の仕事をすることになったという例え。
犬、骨折って鷹にとられる
鷹狩りでは、犬が頑張って追い込んだ獲物を鷹が軽々と奪っていくことから、苦労して得たものを横取りされてしまうという意味。
犬を飼うとも枕児を飼うな
枕児とは、子犬たちが一緒に寝る時、いつも一番下になってしまう弱い犬のことで、犬にしろということ。
飼い犬に手を噛まれる
日頃から人一倍目をかけ、可愛がっていた人から、酷く裏切られたり、歯向かわれることのたとえである。
犬兎の争い
争いに夢中になっていたら第三者に利益を奪われてしまったことを指す。犬がウサギを追いかけて走り回っているうちに、両者とも疲れ果てて倒れてしまい、それを農夫が手に入れたということから。
犬、塊を逐う
愚かな人は結果だけを見て、原因を探ろうとしないという意味。土のかたまりを投げられた犬は、そればかり追って、投げた人を追うことはないことから。
犬に肴の番
犬に食べ物の番をさせるのは、油断がならない。間違いが起こりやすい状況のこと。
犬の尾を食うて回る
自分の尻尾をくわえようとした犬がグルグルと回ってしまい、いつまでもくわえられないよう、苦労が報われないこと。
犬のかけ尿
歩いている犬が尿によるマーキングをあちらこちらにするように、どこでも構わずにしたり、手当たり次第に手を出すこと。
犬の手も人の手にしたい
犬ですら人の代わりに手伝わせたいということから、非常に忙しくて余裕がない様子、多忙で人手が足りない状況のこと。
犬の糞で敵を討つ
憎い相手に卑劣な手段で報復すること。
犬の子の徒歩き
子犬が意味もなくじゃれながら走り回る様子から、あてもなく奔走するばかりで効果がないこと。
犬は門を守り、武士は国を守る
みんなそれぞれの役割があるという意味。
犬の遠吠え
臆病な人が、威張ったりかげで悪口をいったりすること。弱い犬は怯えて遠くから吠えることから。
犬馬の労
人のために、犬や馬のように私心なく、ひたすら尽くして働くこと。へりくだって言うことば。
犬も朋輩鷹も朋輩
鷹狩りで使われる鷹と犬は、役割や待遇が違っても、同じ主人に仕える仲間だということ。仕事の内容や立場が違っても、同僚であることに変わりはないという例え。
犬になるとも大所の犬になれ
もし犬になるなら、しっかりした大きい家の飼い犬になれということ。人に仕えるなら、立派な主人を選べという意味。
落ち込んだ時に元気が出る!犬のことわざ・慣用句

叶わぬ恋に心を尽くすより犬猫を飼え
相手が振り向いてくれない恋に情熱を費やして疲れてしまうよりも、犬や猫を飼った方が愛情に応えてくれる。愚かなことにいつまでもこだわるのはやめた方が良いということわざ。
垣堅くして犬入らず
家庭円満でしっかりしていれば、外から変な人が入ってきたりすることはないという意味。
犬に擲ち目に涙
つい犬に石を投げてしまったが、可哀想になって涙を流すということから、他人にひどい仕打ちをした後、深く反省するという意味。
犬の病も回り年、薮の煩いも六十年目
いくら丈夫な犬でも何年かごとには病気になるし、藪に生えている竹も60年経てば実がなって枯れることから、生きている限り、災いは避けられないという意味。
犬も人を見れば尾を振る
犬だって可愛がってもらおうと尾を振るのだから、人間も愛想よくした方が良いという意味。
兎を見て犬を放つ
ウサギを発見してから猟犬を放っても、捕らえることができる。手遅れだと思っても諦めるのはまだ早い、状況を見極めてから対策を立てても間に合うということ。手遅れという反対の意味で使われることもある。
馬に乗って犬に吠えられたよう
馬に乗っていると、いくら吠えても犬は何もできないことから、痛くもかゆくもないことの例え。
門の犬にも用あり
普段は気にも留めないような者でも、いざという時に役立つことがあるということ。どんなものでも役に立つという例え。
小村の犬は人を噛む
世間慣れしていない人は、何かとひがんでしまうという意味。
頼むと頼まれては犬も木へ上る
木登りができない犬ですらも、お願いされると登ってみる気になるということから、熱心に頼まれれば心が動くものだという意味。
尾を振る犬は打たれず
尻尾を振って懐いてくる犬を叩く人はいないということから、従順な人は非道い仕打ちを受けないという意味。
尾を振る犬も噛むことあり
普段は大人しく見える人でも、意外な反抗を見せることがあるという意味。
食うた犬は打たれずほめた犬が打たれる
大きな悪事を働いた主犯格の人間が逃げおおせて、ちょっと手伝っただけの小物が捕まるという意味。
いぬにも豊年あり
どんな犬にも全盛期があるように、誰でも成功の機会があるという意味。
飢えたる犬は棒を怖れず
飢えている犬は、棒を食べ物だと思って恐れなくなるように、人間も困窮すれば法律を破ることも怖がらなくなるという意味。
我を愛する者は我が犬をも愛す
真剣に人を愛すると、その人の家族やあらゆる物に対して好感を持ってしまうという例え。
生きている犬は死んだライオンに勝る
旧約聖書に基づいた言葉。いくら百獣の王と呼ばれるライオンでも、死んでしまっては価値がない。平凡な人間でも生きていた方がマシだという意味。
「犬の糞」にまつわる!ことわざ・慣用句
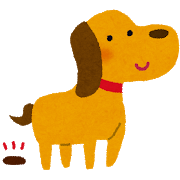
従兄弟はとこは道端の犬の糞
従兄弟やはとこは数が多いだけで、親兄弟などとは違って、「道端の犬の糞」のように役に立たないということ。
犬と糞
青森県の上北地方で言われている言葉で、いつも一緒にいて、悪いことをするような友人を指す。
犬の糞説教
他人の説教を自分が考えたかのように披露すること。
犬の糞に手裏剣
どうでも良いものに貴重なものを使ってしまうこと。
犬の糞も所びいき
どんなにくだらないものでも、自分のところにあると自慢したくなる人間の心理を皮肉ったことわざ。
犬の糞も一盛り
どんなに大したことがない人間でも、人生に一度は全盛期が訪れるという意味。
犬の糞にもならぬ
まったく役に立たないという意味。
江戸の名物は火事・喧嘩・犬の糞
江戸でよく見られるものを挙げた言葉。当時は犬の糞を処理するマナーがなく、野犬も多かったため、かなり見られたことから。
糞の出ぬ犬
糞をしようとしてなかなか出ない犬のように、腰をかがめている人をバカにした語句。
暗がりの犬の糞
自分の失敗を誰も気づかないことに便乗して、隠蔽して素知らぬふりをすること。
佐藤斎藤犬の糞
佐藤や斎藤の名字が多いことをいう。
夜歩きすると得て犬の糞を踏むもの
夜中に出歩くとロクな目に遭わないという言葉。
「犬も食わぬ」にまつわる!ことわざ・慣用句

犬も頼めば糞食わず
普段は気にせずにやっていることも、他人がお願いすると中々やってくれないということ。ケチな性格の人に限って、もったいぶるという意味。
兄弟喧嘩は犬も食わぬ
兄弟が喧嘩をするのは一時的なもので、すぐに仲直りするのだから、相手にしなくて良いということ。
五月坊主は犬も食わぬ
5月は農家が田植えが忙しい時期なので、僧侶は誰も気にしないほど役に立たないという意味。みんなが忙しいからと言って、無駄扱いされてしまうお坊さん。
三月鯛は犬も食わぬ
3月になると旬がすぎて鯛の味が落ちることから。
質屋のした糞は犬も食わぬ
人から物を預かってお金を貸す質屋は、それほど嫌われる商売だということ。(あくまでもことわざであり、立派なお仕事です)
自慢の糞は犬も食わぬ
自慢ばかりする人は周囲から疎まれて相手にされないという意味。
夏の牡丹餅は犬も食わぬ
暑い夏に風邪を引くと、大抵は長引いて厄介なことになる。そんなバカバカしいことはないという意味。
夏の風邪は犬も食わぬ
暑い夏に風邪を引くと、大抵は長引いて厄介なことになる。そんなバカバカしいことはないという意味。
夏の蛤は犬も食わぬ
夏の季節は産卵後でハマグリの味が格段に落ちるため、犬ですら食べないとい意味。ハマグリの旬は、冬から春先と言われています。
舞舞と鮨の飯は辻の犬も食わぬ
「舞舞」とは、武士の世界を語り踊る舞曲のことで、「鮨の飯」は酢飯ではなく、自然発酵させる時に使う飯のこと。舞舞がそれほど廃れたことを表す語句。
名聞は身に余る自分高慢は犬も食わぬ
真に名声を得るに値する人は控えめだが、そうではない者は少し評判が上がった程度で高慢になるから、誰も相手をしなくなるという意味。
猟禽尽きて走狗煮らるる
鳥を捕え尽くしてしまうと、そのために使われていた猟犬も不要になって、煮て食われてしまうということ。
納得して感心する!犬のことわざ・慣用句

赤犬が狐を追う
赤犬も狐も毛色や姿が似ていて、区別がつきにくい。優劣や善悪の判断がつきにくいことを指す。
悪しき人に順って避けざれば繋げる犬の柱を巡るが如し
悪い人と一緒に行動することは、繋がれた犬が柱の周りをグルグルと回るうちに、ヒモで自分の首をしめるようなものだということ。素行が悪い人と付き合っていると、いつか自分の身に災いが降りかかってくるという意味。
油樽に犬が付く
油が入った樽には、それを舐めようと犬が集まる様子から、儲け話があるところに人が群がるということ。不正をしている人には悪人が集まるという意味もある。
犬の蚤の噛み当て
犬がノミを噛み当てるのは非常に難しくて成功の確率が低いことから、まぐれ当たりのことを指す。
一犬形に吠ゆれば百犬声に吠ゆ
一匹の犬が何かの拍子に吠えると、他の犬たちもつられて一斉に吠え出すことから、一人が何の根拠もなく言い出したデタラメでも、多くの人がそれを真実だと広めてしまうという例え。
犬の子を屋根に上げたよう
屋根にあげられた犬は自分で降りられずにウロウロすることから、場違いな場所に来て落ち着かない様子、手も足も出ないことを指す。
犬一代に狸一匹
犬がタヌキのような大きな獲物を獲るのは一生に一度あるかないかの出来事である。非常に珍しいことの例え。
犬の一年は三日
犬の一年は人間にあてはめると3日程度という意味。犬の成長の早さを表した語句。さすがに「1年=3日」というのは大げさですが、人間と犬の成長を比べると、犬の方がはるかに早いというのは昔の人もわかっていました。
犬の寒いは三日だけ
犬は寒さをまったく苦にしないということ。(確かに昔の日本人は屋外で飼うのが基本であり、飼っていた犬も秋田県や芝犬など、日本固有の丈夫な犬種だったため、そう見えたのかもしれませんが、今の日本にいる犬は全てが寒さに強いわけではありません。)
犬が西向きゃ尾は東
疑う余地もないくらいに当たり前すぎるほど当たり前の事を、さらに強調して言った言葉です。
犬は人に付き、猫は家に付く
犬は家人になつき、引っ越しにもついて行くが、猫は人よりも家の建物・場所になじむという意味。犬と猫の違いを表した言葉で、犬は飼い主である人間から受けた恩を一生忘れないというたとえ 。
犬も町びいき
犬ですらも自分の住む町を贔屓にするのだから、人間は誰でもお国自慢をしたがるものだという意味。犬が町を贔屓するのは、自分のテリトリーを守ろうとする習性を表していると思われます。
戌の日に腹帯をすれば安産
妊婦5ヶ月目に入った妊婦さんが最初の「戌の日」に腹帯を巻くと安産になるというまじない。戌の日とは、十二支に基づいて12日に1度巡ってくる日のこと。犬はお産が軽く多産であることにあやかって、古来から行われている日本独自の風習。
尊客の前には狗をだに叱らず
尊敬する客の前では犬さえも叱るべきではない。大事な人の前では慎んだ行動を心がけて、横柄な態度をとってはいけないという中国の儒教の教え。
馬は赤馬、牛は黒牛、猫は雉猫、犬は白犬
それぞれの動物の中で最も良いとされている毛色のこと。
えのこ道知る
えのことは、「犬子」と書くように子犬のこと。子犬でも家までの帰り道を知っているという意味。
豪家の門に痩せたる犬なく、農夫の倉に肥えたる鶏あり
裕福な家で飼われている犬は痩せていないし、農家の倉に住む鶏は太っている。それなりの場所にいる者はそれなりの暮らしができるという例え。
噛み合う犬は呼び難し
争っている犬は飼い主が呼びかけても耳を貸さないことから、何かに熱中している者は他者から言われたことが耳に入らないという意味。
雪は犬の伯母
雪が降ると犬が興奮して走り回る様子に、子供が伯母に会って喜んではしゃぐ姿を重ねた語句。
夫婦喧嘩は犬も食わない
夫婦喧嘩は、つまらない原因であったり、一時的なものであったりするから、他人が間に入って仲裁したり心配する必要がないという事。
眠っている犬は寝かせておけ
必要もないのに眠っている犬を起こすと噛みつかれたりするので、そのまま寝かせておけということから、余計なことを言ったりやったりするなという警句。
失礼・かわいそう!犬のことわざ・慣用句
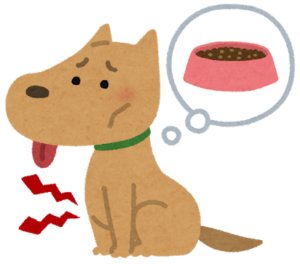
犬のよう
人の道から外れた恩知らずという意味。朝、寝起きでそのまま食事をするような人を指すこともある。
犬よりまし
頼りなく見えても犬よりは役に立つ。子供が家の手伝いをちゃんとこなした時などに使う語句。
犬と寝る者は蚤をしょって起きねばならぬ
犬と一緒に眠ると、犬についていたノミが自分にもついてくることから、つまらない人間と付き合っていると、いつしか同じようになってしまう。良い友人を選ぶことが大事という例え。
犬さ投げる土もない
青森県のことわざ。犬に対して投げる土もないほど、落ちぶれたという意味。
犬とわらしは痛いうち泣く
犬と子供は痛みを感じている間はいつまでも泣いているということから、グズグズしていて諦めが悪いという意味。
犬の死んだも行って見る
犬が死んだなんてどうでも良いことですらわざわざ見に行くことから、些細なことを気にして動き回るという意味。(ことわざが作られたのは昔ですから、現在人の目線では犬の命を軽く扱うことは絶対にしてはいけません。)
犬の年寄ったよう
ダラダラと年をとっただけで何の成長もしていない人のこと。
犬犬三年人一代、人人三年犬一代
犬のように哀れな生活を辛抱して過ごしたことで、残りの人生を裕福に楽しく過ごせる人もいれば、はじめに贅沢に遊んでしまったため、その後は犬のように軽蔑されて一生を終える者もいる。何事も最初のうちは我慢して節約しなくてはならないという意味。
犬が星をまもる
この「まもる」は「見つめる」という意味で、犬が星を見つめているということから、身の程を知らずに高望みをすること。
家の前の痩せた犬
痩せていて、普段は弱々しく見える犬でも、自分の家の前では勇ましく吠えることから、臆病者が他人の力を借りて偉そうな態度をとることの例え。
女の涙と犬の跛を
争いに負けた犬が足を引きずって見せるように、自分の立場が不利な時に女性が泣くのはウソであるという意味。「跛(ちんば)」に関しては、現在は足が不自由な人への差別用語として扱われています。
関東の犬這い
江戸時代、京都所司代に就任した者は、まず朝廷に参内して天盃を賜ったそうです。その時に這いつくばって受ける様子がまるで犬のようだと、公家たちが「這い」と「杯」をかけてバカにした言葉。
忌中の家の犬のよう
忌中は、バタバタしていて世話を忘れられたりして、犬がやせ衰えて貧弱に見える体の人をからかう言葉。
食うだけなら犬でも食う
単に食べて生きるだけなら犬だってできる。人間は漫然と生きるのではなく、目的を持つべきではないかという意味。
毛の無い犬
違いは全身に毛が生えていないくらいで、犬のような心の持ち主だということ。人情がわからない最低の人間という意味。
鶏犬雲に吠ゆる
仙薬の残りをたまたま舐めた鶏と犬が天に昇ったという中国の故事から、たいしたことのない人物が突然の栄誉を受けることを指す。
心の無い人に物を食わせても犬に劣る
感謝する気持ちがない人に何かを与えても、犬のように懐いてくるわけでもない。無駄であるということ。
出家侍犬畜生
昔の人が僧侶と武士を罵った慣用句。「犬畜生」とは、「犬などのけだもの」という意味で、不道徳な人を罵る時のことば。
外孫飼うより犬の子飼え
外孫とは、自分の娘が嫁ぎ先で産んだ子のことであり、夫の方の家族になってしまう外孫に愛情を注いでも、将来は当てにできないため、犬の子を可愛がった方がマシという意味。
旅に女と犬は連れぬもの
ただでさえ旅をするのは大変なことなのに、そこに女や犬といった足手まといになりそうなものは最初から連れて行かないものだという意味。
鷹の無い犬
鷹狩りは、まず犬が獲物を追い出して、それを鷹が捕らえることから、パートナーがいなければ役に立たない者という例え。
年寄れば犬も侮る
老人になると多くの人からバカにされるという意味。(これは現代ではかなり酷いなことわざですので使用時は注意が必要です)
夏孕みは犬より劣る
妊婦が夏に暑がっている姿は、暑さにバテて息を切らしている犬よりも見苦しいということ。
煩悩の犬は追えども去らず
煩悩は付きまとってくる犬のようで、追い払おうとしても、中々上手くいかないという意味。
水に落ちた犬を打つ
敗北した相手に追い打ちをかけて徹底的に叩くこと。
飯食ってすぐ寝ると犬になる
行儀の悪い様子をたしなめる警句。