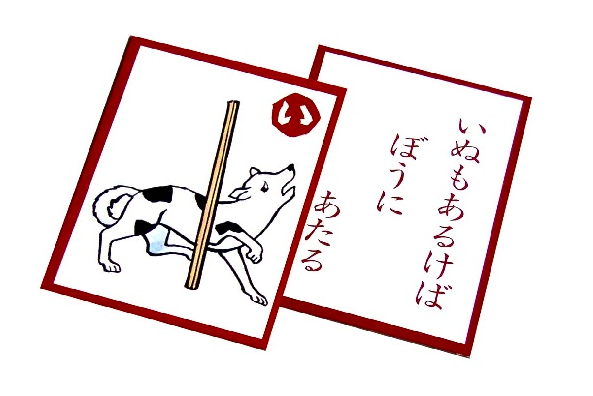「さ行」の小学校で習うことわざ

猿も木から落ちる(さるもきからおちる)
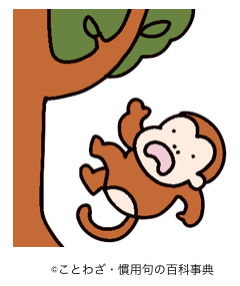
- 意味・教訓
どんなに得意なことでも、ときには失敗することがあるという教え。完璧な人はいないので、失敗を恐れず挑戦することが大切。 - 使用例
「一流のピアニストだって演奏を間違えることがあるよ。猿も木から落ちるって言うし、失敗を気にせず次に進もう!」
触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)
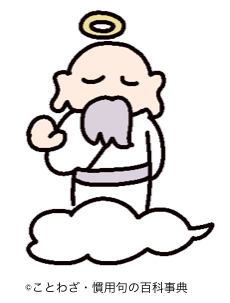
- 意味・教訓
余計なことに関わらなければ、余計なトラブルに巻き込まれることもないという教え。面倒ごとには近づかないほうが賢明である。 - 使用例
「あの話題に首を突っ込むと厄介だから、黙っておいたほうがいいよ。触らぬ神に祟りなし、って言うだろ?」
山椒は小粒でもぴりりと辛い(さんしょうはこつぶでもぴりりとからい)

- 意味・教訓
体が小さかったり見た目が目立たなくても、優れた才能や力を持っていることがあるという教え。小さくても侮れないという意味。 - 使用例
「彼は小柄だけど、サッカーの試合では誰よりも素早く動けるんだよ。まさに山椒は小粒でもぴりりと辛いって感じだね!」
三人寄れば文殊の知恵(さんにんよればもんじゅのちえ)

- 意味・教訓
一人では良い考えが浮かばなくても、三人集まれば優れた知恵が出るという教え。協力することでより良い解決策が見つかることを示している。 - 使用例
「この問題、一人じゃ解決できそうにないけど、みんなで考えればいい案が出るはずだよ。三人寄れば文殊の知恵って言うしね。」
地獄の沙汰も金次第(じごくのさたもかねしだい)

- 意味・教訓
どんな厳しい状況でも、お金があれば解決できることが多いという教え。現実社会では金銭の力が大きな影響を持つことを示している。 - 使用例
「VIP待遇で病院に入院できるなんて、やっぱり地獄の沙汰も金次第だね。」
親しき中にも礼儀あり(したしきなかにもれいぎあり)

- 意味・教訓
どんなに親しい間柄でも、礼儀や節度を忘れてはいけないという教え。親しいからといって無礼な態度をとると、人間関係が壊れることもある。 - 使用例
「長年の親友でも、頼みごとをするときはちゃんとお願いすべきだよ。親しき中にも礼儀あり、って言うだろ?」
失敗は成功の基(しっぱいはせいこうのもと)

- 意味・教訓
失敗を経験することで学びが得られ、次の成功につながるという教え。大切なのは、失敗を恐れずに挑戦し続けること。 - 使用例
「最初のプレゼンはうまくいかなかったけど、その経験が次に活きるよ。失敗は成功の基って言うし、諦めずに頑張ろう!」
朱に交われば赤くなる(しゅにまじわればあかくなる)

- 意味・教訓
人は周囲の環境や付き合う人によって影響を受け、良くも悪くも変わっていくという教え。良い環境に身を置くことが大切。 - 使用例
「最近、彼が前向きになったのは、意識の高い友達と付き合うようになったからだろうね。朱に交われば赤くなるって言うしね。」
少年老い易く学成り難し(しょうねんおいやすくがくなりがたし)

まだ若いと思って油断していると、すぐに年をとってしまう。ところが学問はなかなか進まないものだから、若いうちから時間を大事にしてしっかり勉強に励みなさいという教え。
勝負は時の運(しょうぶはときのうん)

勝つか負けるかはその時の運によるもので、強い者が必ず勝つとは限らない。
将を射んと欲すれば先ず馬を射よ(しょうをいんとほっすればまずうまをいよ)
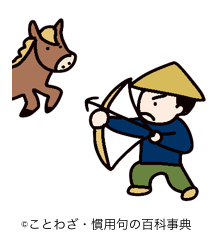
人を自分の思う通りにさせようと思ったら、直接その人を狙うより、その人が頼りにしているものをまず狙うとよいという例え。
初心忘るべからず(しょしんわするべからず)

勉強や仕事などは、慣れてくるとだらけてなまけ心が起きてしまうものだが、始めようと思った時の真剣な気持ちを忘れてはいけない。
知らぬが仏(しらぬがほとけ)

知っていれば気になったり、驚いたり怒ったりするだろうが、何も知らなければ平気でいられるという例え。
白羽の矢が立つ(しらはのやがたつ)

人身御供を求める神が、その望む少女の家の屋根に人知れず白羽の矢を立てるという俗伝から。多くの人の中で、これぞと思う人が特に選び定められる。また、犠牲者になる。
上手の手から水が漏る(じょうずのてからみずがもる)

どんな上手な人でも、時には失敗することもあるものだ。
人事を尽くして天命を待つ(じんじをつくしててんめいをまつ)

できる限りの努力をしたら、後は成り行きに任せる。
好きこそ物の上手なれ(すきこそもののじょうずなれ)

自分が好きですることは面白くて一生懸命にやれるので、いつの間にか上手になるものである。
住めば都(すめばみやこ)
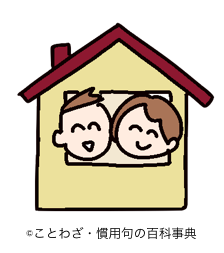
住む前は、どんなに暮らしにくいと思われる土地でも、そこに長く住んで慣れてしまうと良いところと思うようになるものだという例え。
急いては事を仕損じる(せいてはことをしそんじる)

物事を焦って急ぐと、失敗しやすいというたとえ。
栴檀は双葉より芳し(せんだんはふたばよりかんばし)

香木の栴檀は双葉が出たころから芳香を放つということで、大成する人物は幼時から優秀な素質を示すたとえ。
善は急げ(ぜんはいそげ)

よいことをするのにためらうなの意。
千里の堤も蟻の穴から(せんりのつつみもありのあなから)
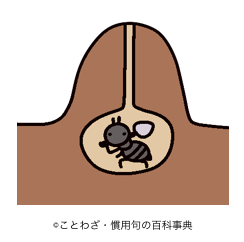
ちょっとした手違いから、大事に至るものだから、どんな小さいことでも軽んじてはいけないという教え。
前門の虎後門の狼(ぜんもんのとらこうもんのおおかみ)

一つの災いを防いだと思ったら、すぐ次の災いがふりかかる。
袖振り合うも多生の縁(そでふりあうもたしょうのえん)

どんなささいなことでも、偶然に起こっていることではなく、前世からの因縁によるものだから、道で見知らぬ人と袖が振れあうようなことでも、大切にせよというたとえ。
損して得取れ(そんしてとくとれ)

損をしないことばかり考えていては、あまり儲からない。はじめに損をすることによってその損よりもずっと大きな儲けを得るようにしなさいという教え。