「白羽の矢が立つ」の意味(語源由来・類義語・英語訳)

【ことわざ】
白羽の矢が立つ
【読み方】
しらはのやがたつ
【意味】
多くの人の中から特別に選び出されること。


白羽の矢が立つって言われると、なんだか特別感があるけど、最初は犠牲者を選ぶための表現やったんやな。
【語源由来】
人身御供を求める神が、その望む少女の家の屋根に人知れず白羽の矢を立てるという俗伝から。多くの人の中で、これぞと思う人が特に選び定められる。また、犠牲者になる。
【類義語】
・白羽の矢を立てる
【英語訳】
He was surrounded by foes.
The choice falls on some one.
「白羽の矢が立つ」の解説

「白羽の矢が立つ」っていうことわざはね、誰かが特定の人物を選び出すときに使われるんだよ。その出元は、昔の神への供え物、人間を神に捧げる「人身御供(ひとみごくう)」という儀式に由来しているんだ。
昔、神々に対するお供えとして、人間が選ばれて生贄になることがあったんだよね。選ばれた人の家の屋根には、その人が選ばれたことを皆に知らせるために白羽の矢が立てられたんだ。それが「白羽の矢が立つ」っていう表現の由来なんだよ。
でもね、昔は生贄として選ばれるっていう意味が強かったけど、今ではちょっと意味が変わってきていて、良い意味でも悪い意味でも使われるようになったんだ。たとえば、学校の運動会でアンカーを務める選手を選ぶときや、特別な仕事を任せる人を選ぶときなどにも使われるようになったんだよ。選ばれた人は、その仕事を成功させるためには大変な努力が必要だけど、それと同時に大きな名誉を得ることができるんだよね。
「白羽の矢が立つ」の使い方




「白羽の矢が立つ」の例文

- ピンチ・ヒッターとして僕に白羽の矢が立ったんだけど、急だったので大いに困った。
- 一年生を歓迎する会の進行係は、学校で面白いといわれる生徒の中から彼に白羽の矢が立てられた。
- 今度のドラマの主演者には、無名の新人ともこちゃんに白羽の矢が立った。
- あみだくじの結果、あろうことか健太くんに白羽の矢が立った。
- 捜査には、この町の地理に明るい人物が良いということで、僕に白羽の矢が立った
一口メモ

日本古来の風習で、昔は日照りや水害などの天災が続くと、神様の怒りを鎮めるために「人身御供」というものが求められた。この人身御供というのは神様のために人間の身体を奉げるというもので、多くの場合生贄として選ばれるのはまだ大人になっていない少女だった。そして生贄として選ばれる少女の家の屋根には神様が目印として白羽の矢を立てた。神様に選ばれたということで名誉なことと思われていた。そこから、現代では「犠牲者」という意味ではなく良い意味で使用される。朝、起きてみて屋根に白羽の矢がたっていても、今では犠牲者の意味はないのでご安心を。
「白羽の矢が立つ」の文学作品などの用例
妹は姉さんよりも遥かに美しかったので校長が大へん力を入れて、お聟さんを捜し、遂に某青年に白羽の矢が立って、いよいよ見あいする迄に事が進んだのだ。(小酒井不木の段梯子の恐怖より)








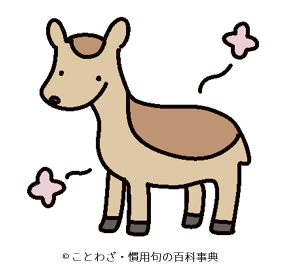

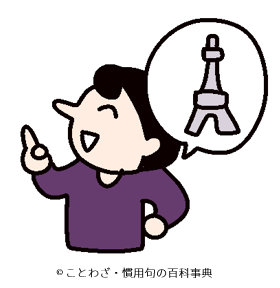

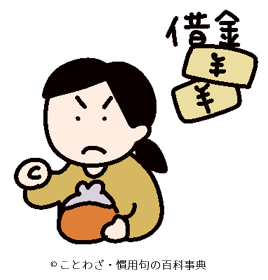

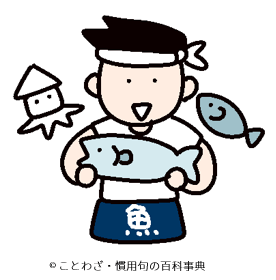




これはもともと、犠牲者を選ぶための表現だったんだけど、今では特に選ばれた人のことを指すようになったんだ。