「火箸を持つも手を焼かぬため」の意味

【ことわざ】
火箸を持つも手を焼かぬため
【読み方】
ひばしをもつもてをやかぬため
【意味】
物事には、目的に適した手段があるということ。道具には、それを使う理由があるということ。


ほな、つまり「正しい道具を使えば、安全に仕事ができる」ってことやな。火箸みたいに、ちゃんとした道具を使えば、火を扱っても手をやけどせずに済むってわけや。
これって、「物事をするときは、そのための正しい方法や道具を選ぼう」ってことを言いたいんやな。なるほどな~、賢いこと言うなぁ、ことわざ博士!
【スポンサーリンク】
「火箸を持つも手を焼かぬため」の解説
カンタン!解説

「火箸を持つも手を焼かぬため」っていうことわざはね、火箸っていう特別なはさみで火を扱っても、その道具のおかげで手が火傷しないっていうことから、物事を上手くやるためには、その目的にぴったりの道具や方法があるっていう意味なんだよ。
たとえばね、絵を描くときに、指で描くこともできるけど、絵の具と筆を使ったほうがもっときれいに、思った通りの絵を描けるでしょ? それと同じで、火箸を使うことで、安全に、上手に火を扱うことができるんだね。
このことわざは、どんなことをするにも、そのための正しい道具や方法があるって教えてくれているんだ。適した道具を使うことで、仕事が楽になったり、結果がずっと良くなるってわけだよ。だから、何をするにも「この仕事にはどんな道具が一番いいんだろう?」って考えるのが大事だね。
「火箸を持つも手を焼かぬため」の使い方

明日の理科の実験、めちゃくちゃ難しそうだよね。火を使うって聞いて、ちょっと怖いよ。

うん、でも、先生が使い方をちゃんと教えてくれるし、安全な道具も用意してくれるって言ってたよ。火箸を持つも手を焼かぬためってことわざがあるじゃん。ちゃんと道具を使えば、怖がることないよ。

へえ、そういうことわざがあるんだ。確かに、火箸を上手に使えば、直接火に触れることなく、安全に火を扱えるもんね。

そうそう、だから、明日はちゃんと実験の説明を聞いて、道具の使い方を覚えよう。そうすれば、難しい実験も上手にできるようになるよ。
【スポンサーリンク】
「火箸を持つも手を焼かぬため」の例文

- 彼はプロジェクトの期限に間に合わせるために無理なスケジュールを組んだが、結局品質が低下してしまった。火箸を持つも手を焼かぬため、時には外部の専門家を雇うほうが賢明かもしれない。
- 新しいソフトウェアを使うことに慣れていない社員が多く、トレーニングに時間がかかってしまった。火箸を持つも手を焼かぬため、事前に使い方を学ぶセミナーを開くべきだった。
- 彼女は手作業でレポートをまとめるのに時間を費やしていたが、同僚からのアドバイスで効率的な管理ツールを導入した。火箸を持つも手を焼かぬため、時代に合ったツールを使うことの大切さを学んだ。
- DIYで家の修理をしようとしたが、専門的な知識がなくてさらに悪化させてしまった。火箸を持つも手を焼かぬため、最初からプロに頼むべきだった。
- チームのコミュニケーション不足がプロジェクトの遅延を引き起こしていた。火箸を持つも手を焼かぬためには、定期的なミーティングと透明な情報共有が必要だった。














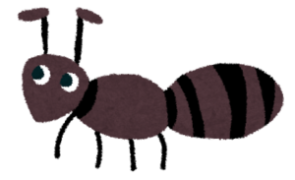







適切な道具を使えば、危険や困難を避けながら目的を達成できる、ということを意味しているよ。