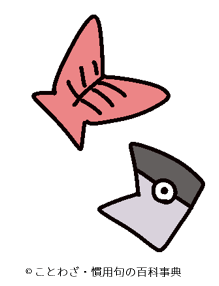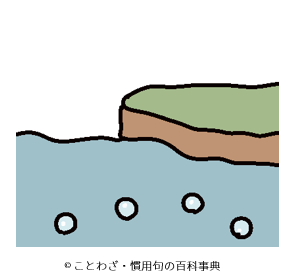「大疑は大悟の基」の意味(出典・類義語)

【ことわざ】
大疑は大悟の基
【読み方】
たいぎはたいごのもとい
【意味】
大いに疑問を持つことは、悟りをひらくもとになる。

「大疑は大悟の基」ということわざは、たくさん疑問を持つことが、後に大きな気づきを得るための基礎になるという意味があります。

あーなるほどな。つまり、「たくさん疑問を持つことは、後で大きな気づきを得るための大切な基礎になる」ということやな。
たくさん考えたり疑問を持ったりすることで、いろんなことが分かってくるんやね。疑問は大事なんや、ちゃんと考えることが大切やな。
【出典】
「大慧普説」
「大疑の下。必ず大悟有り」という禅のことば。
【類義語】
・迷わぬ者に悟りなし
・疑わぬ者に悟りなし
【スポンサーリンク】
「大疑は大悟の基」の解説
カンタン!解説

「大疑は大悟の基」という表現は、深く疑問を持つこと、つまり物事に対して深い疑念や探求心を持つことが、最終的には大きな理解や悟り(大悟)に繋がるという意味のことわざなんだ。
この言葉は、知識や真理を追求する過程において、疑問を持つことが非常に重要であるという考えを反映しているんだ。疑問を持つことは、既存の理解や信念に挑戦し、より深い洞察や新たな発見に導くことができる。つまり、大きな疑問や問題に直面し、それに対して深く考え探求することが、結果的にはより高いレベルの理解や啓発につながるということなんだよ。
「大疑は大悟の基」は、特に宗教的、哲学的、学問的な探求においてよく引用される表現で、真理を求める旅において疑問や批判的思考が重要な役割を果たすことを示しているんだ。それは、単に受け入れるのではなく、疑い、質問し、深く掘り下げることで、真の理解や悟りに近づくことができるというメッセージを伝えているんだね。このたとえは、知的な探求の過程で疑問を恐れずに抱くことの重要性と価値を強調しているんだ。
「大疑は大悟の基」の使い方

これって何でこうなっているのかな。

大疑は大悟の基よね。疑問に思う事は大事よ。でも、それを自分で調べることも大事よ。

人に聞くばかりじゃだめなんだね。

自分で調べて初めて自分の知識になるのよ。
【スポンサーリンク】
「大疑は大悟の基」の例文

- 色んなことに疑問を持って、大疑は大悟の基というように悟りを得る。
- 大疑は大悟の基というように、疑問は学びの扉を開く。
- 大疑は大悟の基というから、宇宙の始まりについて真剣に考える。
- 賢くなれば視野が広くなり悟りを開くことができるが、大疑は大悟の基といい、疑いを持つことが賢くなるための一歩だ。
- 質問ばかりでうるさいと子供を叱る親がいるけど、大疑は大悟の基というのでどんどん疑問を持った方がいい。