目次
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の意味(語源由来・類義語・英語訳)

桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿
【読み方】
さくらきるばか、うめきらぬばか
【意味】
桜と梅の剪定(せんてい)法に違いがあることを教える言葉。


一つの方法が万能じゃないってことを教えてくれる言葉やね。何事もその特性や性質を考えて、ベストな方法を選ぶのが大事やな!
【語源・由来】
「桜」はへたに切ると、切り口から木材腐朽菌が入り込みだんだん枯れていく。「梅」は切ることにより、枝数がふえ、枝数が増えるとともに花も多くつくので、切ることをすすめるという両者の特性から。
【類義語】
・梅は伐れ、桜は伐るな
・桜折る馬鹿、柿折らぬ馬鹿
・桃を切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿
【英語訳】
The fools who cut cherry trees, the fools who don’t cut plum trees.
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の解説

「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」っていうことわざは、色んなものや状況によって、正しい方法が違うっていうことを教えてくれる言葉なんだよ。
考えてみてね。桜の木と梅の木、どっちもきれいな花を咲かせる木だけど、両方の木の手入れの方法は違うんだ。桜の木は、大きな枝や幹を切っちゃうと、その部分が弱くなっちゃって、あまり元気がなくなることがあるよ。だけど、梅の木は、不要な枝をちゃんと切らないと、綺麗な花や実がなかなかつかなくなるんだよ。
だから、この言葉は、何事も一緒くたに考えちゃダメってこと。それぞれの状況やものに合わせて、適切な方法で対応しないと、上手くいかないことがあるんだね。物事には、それぞれの「正しいやり方」があるってことを、このことわざが教えてくれてるよ!
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の使い方




「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」の例文

- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿という言葉が、植物に水をあげすぎて、枯らしてしまう私の胸に突き刺さった。
- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿というのは、余計なことばかりして、大切なことはしない人に似ている。
- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿というが、花見のときに健太くんが枝を折った桜は本当に枯れてしまった。
- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿というが、桜は剪定が難しく、梅は剪定が容易ということでもある。
- 桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿という言葉を先人は残してくれたが、枯らす前に知りたかった。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」を深掘り
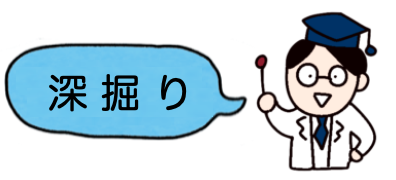
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という諺は、桜と梅の樹に対する異なる取り扱いを示す日本のことわざです。この諺は、それぞれの樹が持っている特性と、それに対する最適な手入れ方法を教えています。
桜の木は、切られるとその切り口がなかなかふさがらず、病原菌の侵入を許してしまい、木が腐りやすい性質を持っています。
このため、桜の木を不必要に切ることは避けるべきで、特に太い幹は慎重に扱わなければなりません。もちろん、病気の枝は早めに切り取るべきですが、その際も切り口にはペンキやコールタールを塗るなどの処理が必要です。
一方、梅の木はその性質が桜とは大きく異なります。梅の木では、花のもとである花芽は短い枝に多くでき、長い枝にはほとんど花芽が形成されません。このため、梅の木の長い枝は積極的に切るべきです。この切り取りによって、梅の木はより美しい樹形に整えられ、花の生育も促されます。
この諺は、これら二つの木の特性と、それぞれの適切な手入れ方法を示しており、桜の木を無闇に切ってしまうことの危険性と、梅の木の長い枝を適切に切ることの重要性を教えています。
同時に、この諺は植物の手入れにおいて、一律の方法が適用できないこと、各植物種の特性を理解し、それに適したケアが必要であることを示しています。
参考文献
植物ことわざ事典 | 足田 輝一











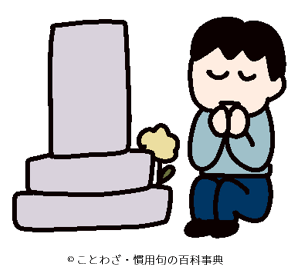
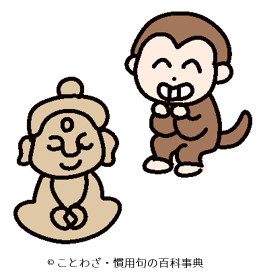




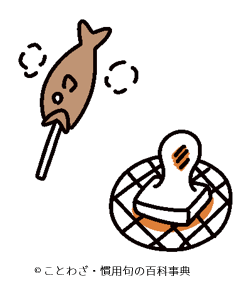





桜は枝を切ると衰弱するが、梅は不要な枝を切らないと良い花や実がつかなくなる。これは、物事にはそれぞれ適切な方法があるという教えなんだ。