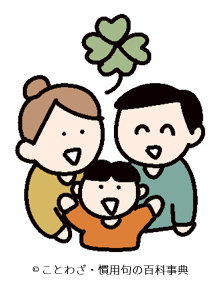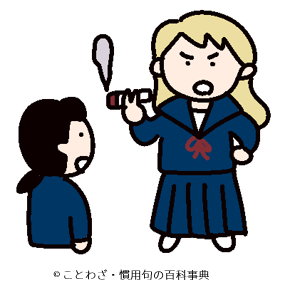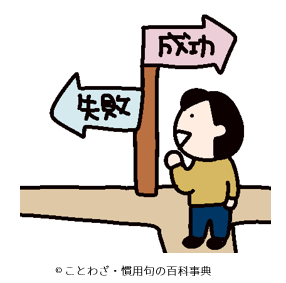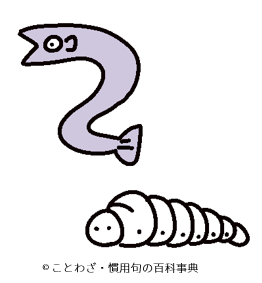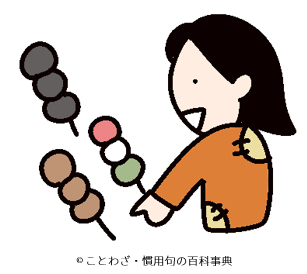「積善の家には必ず余慶あり」の意味(出典・類義語)

積善の家には必ず余慶あり
「積善の余慶」ともいう。
【読み方】せきぜんのいえにはかならずよけいあり
【意味】
善い行いを積んできた家には、その報いで子孫にまで幸福が及ぶということ。
「余慶」は、先祖の善行のおかげで子孫が受ける幸福。

「積善の家には必ず余慶あり」という言葉は、善い行いを積み重ねた家族には、その良い行いの結果として後世の子孫にも幸福が訪れるという意味なんだよ。

ほなら、善いことをたくさんしてきた家には、その善行のおかげで子孫にも幸せが訪れるってことやな。善行が積み重なって、それが報いとして後の世代にも良い影響を与えるってことやね。
善い行いが長い間、家族に幸せをもたらすことを表してる言葉やな。
【出典】
「易経」
【類義語】
・善には善の報い、悪には悪の報い
【スポンサーリンク】
「積善の家には必ず余慶あり」の解説
カンタン!解説

「積善の家には必ず余慶あり」という表現は、「易経」の坤卦に由来しており、善い行いや徳を積み重ねた家族には、その報いとして後の世代にも幸福や恩恵が訪れるという意味を持っているんだ。このことわざは、善行を行うことが将来の幸福に繋がるという考えを示しているんだよ。
「積善」とは、良い行いや善行を積み重ねることを指し、「余慶」とは余分な喜びや幸福、つまりその善行の結果として訪れる喜びや幸せを意味しているんだね。
たとえば、親が社会に対して善行を行い、誠実に生きることが、子孫に良い影響を与え、家族全体に幸せや恩恵をもたらすことが「積善の家には必ず余慶あり」に当てはまるんだよ。
このことわざは、良い行いがただちに報われなくても、長い目で見ればその効果が自分や家族、さらには子孫にまで及ぶという教えを含んでいるんだね。それは、個人の行動が家族や未来の世代に及ぼす影響を意識し、善行を積むことの重要性を示しているんだよ。
「積善の家には必ず余慶あり」の使い方

あの家は幸運に恵まれているよね。

積善の家には必ず余慶ありというからね。

先祖代々良い人ばかりということ?

心の清らかな人が多いわね。家族全員で日本中の善行に匹敵するくらいの善行を積んでいるかも。
【スポンサーリンク】
「積善の家には必ず余慶あり」の例文

- 子孫のためにも善行を積もう。積善の家には必ず余慶ありだ。
- 清らかな心で過ごせば積善の家には必ず余慶ありといい、おだやかに過ごせる。しかし邪心があると不安で穏やかに過ごせなくなる。
- 人が見ていない所でも良い行いをして、積善の家には必ず余慶ありというように家族みんなで幸せになる。
- 普段の行いが良いと良いことがあるものだ。積善の家には必ず余慶ありだから、どんどん良いことをする。
- 貧乏神がいる家は悪行を重ね、福の神がいる家は積善の家には必ず余慶ありというように善行を重ねているはずだ。