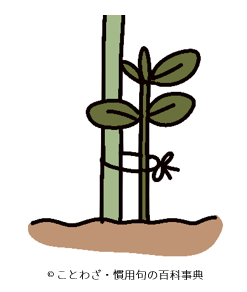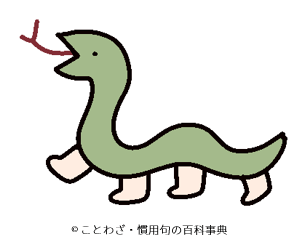「矯めるなら若木のうち」の意味(語源由来・類義語・英語)
【ことわざ】
矯めるなら若木のうち
【読み方】
ためるならわかぎのうち
【意味】
欠点や悪い癖を矯正しようと思ったら、若いうちのほうが柔軟性があってよいということ。


悪い癖や欠点も、早いうちに気付いて矯正しておけば、後々大きな問題にならずに済むやろうし。若いうちの経験や教育が、その後の成長に大きく影響するってことやな。
【語源・由来】
木の枝ぶりを直すには、若木のうちに直すとやわらかくてよいけれど、硬くなってしまってからでは、思い通りに直らないということから。
「矯める」とは、曲げたり伸ばしたりして形を整える、または悪い性質を直すという意味。
【類義語】
・鉄は熱いうちに打て(てつはあついうちにうて)
・老い木は曲がらぬ(おいきはまがらぬ)
・二十過ぎての子の意見と彼岸すぎての肥は聞かぬ(はたちすぎてのこのいけんとひがんすぎてのこえはきかぬ)
【英語】
Best to bend while it is a twig.(小枝のうちに曲げるのがいちばんよい)
「矯めるなら若木のうち」の解説

「矯めるなら若木のうち」という言葉は、樹木の枝や形を整えるのに、若くて柔らかい時期に行う方が良いという意味で使われるんだ。これは、樹木がまだ若く柔軟なうちに形を整えた方が、望む形に成長しやすいということから来ているよ。
この表現は、樹木だけでなく、人間の教育や性格形成にも当てはまるんだ。人の悪い癖や欠点も、若いうちに矯正する方が根付く前に修正しやすいということを示している。つまり、若い時は学習能力や柔軟性が高いため、望ましい行動や思考のパターンを身につけるのに適しているということなんだ。
「矯める」という言葉は、曲がっているものをまっすぐにする、または、不適切なものを適切な形に修正するという意味を持っていて、このことわざは、若いうちに良い習慣や行動を身につけること、または問題を修正することの重要性を教えているんだ。それは、若い時期の教育や指導が、その人の将来に大きな影響を与えるという考えを示しているんだね。
「矯めるなら若木のうち」の使い方




「矯めるなら若木のうち」の例文

- 年齢を重ねると、人の意見を聞くこともむずかしくなってしまうね。矯めるなら若木のうちというから、若いうちに悪い癖は直しておきたいね。
- 矯めるなら若木のうちというのだから、その癖は早く直すように対策を考えよう。
まとめ
年齢を重ねると、知識や経験も豊富になるのではないでしょうか。
しかし、知識や経験が豊富になってしまったせいで、柔軟性を失ってしまうことがあるのかもしれません。
矯めるなら若木のうちというように、悪い癖や欠点は早めに直すように心掛けたいものですね。