「智に働けば角が立つ」の意味(語源由来)
【ことわざ】
智に働けば角が立つ
【読み方】
ちにはたらけばかどがたつ
【意味】
理知的に動こうとすれば人間関係がぎすぎすして穏やかに暮らしづらくなる。


難しいバランスやけど、うまいこと両方考えながらやっていかなあかんってことか。ほんま、人との付き合いって、ややこしいけど、大事やね。
【語源・由来】
夏目漱石の「草枕」の冒頭にあることば。
「智に働けば角が立つ」の解説

「智に働けば角が立つ」という言葉は、夏目漱石の小説「草枕」に出てくるフレーズで、非常に深い意味が含まれているんだ。
この言葉は、物事をただ理知(智)だけで考えて行動すると、つまり頭でっかちになってしまうと、他人との間に摩擦や衝突が生じやすくなる、ということを教えているんだよ。これは、自分が正しいと思っていることや、合理的だと思う方法だけを押し通そうとすると、人とぶつかりやすくなり、「角が立つ」つまり人間関係に角が生じるということを表しているんだ。
また、この言葉の続きには、他人の感情に気を遣いすぎると、逆に自分が行動を起こしにくくなる、つまり「自分の足をすくわれる」とも言われているんだ。これは、他人の気持ちを尊重しすぎて、自分の意見や行動が抑えられてしまうという状況を表しているよ。
夏目漱石は、この言葉を通じて、ただ頭で考えるだけではなく、感情や周りの人との調和も大切にしながら、バランスよく行動することの重要性を伝えているんだね。
「智に働けば角が立つ」の使い方

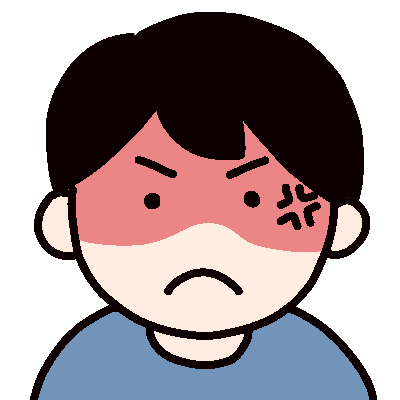


「智に働けば角が立つ」の例文

- 理論で相手に勝っても、心情的には理解してもらえないのが現実です。智に働けば角が立つ、そこは百歩譲って頭を下げるのがベストです。
- いくら見識があるからといって、その人の行いがすべて正しいとは限りません。智に働けば角が立つというじゃありませんか、もっと緩(ゆる)い目で見てあげましょう。
- 知識があることを相手に見せても何の得にもなりません。人間が生きていくための知識はひとそれぞれ違いますから、貴方の知識などたいしたことはないのです。智に働けば角が立つのは当然でしょう。
- なぜ智に働けば角が立つのでしょうか。人は馬鹿だと思われるのは我慢できても、相手が俺は賢いといえばいうほど、つい逆らいたくなるものなのです。
まとめ
夏目漱石を知っている人は少ないのかもしれません。「草枕」が発表されたのは日露戦争の頃です。日本とロシアが戦争したことも忘れられているのかもしれません。ただ忘れてはいけないことは、今考えれば良くない時代であったとしても、今の自分があるのは、その時代を生き抜いてきた生命、智だけでは生き抜けなかったはずです。その生命のリレーがあったのは否定できせん。










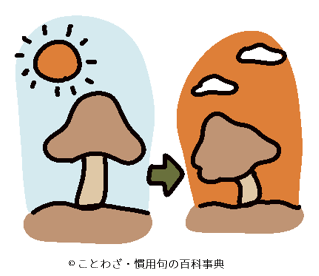




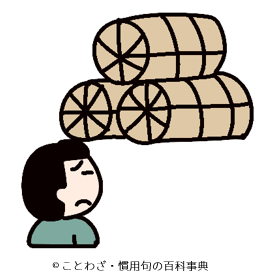







また、他人の感情をあまりにも気遣うと、自分の立場が弱まることもあると警告しているんだ。