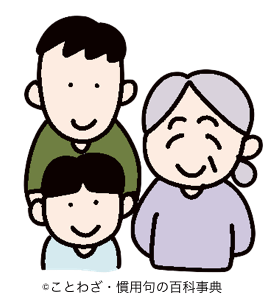「商人の元値」の意味(類義語)

商人の元値
【読み方】
あきんどのもとね
「商人」は、しょうにんとも読む。
【意味】商人は元値がきれる(元値が割れる)ということが多いが、客は元値が分からないから信用ならないということ。

「商人の元値」ということわざは、商人が商品を売るときに「これが元値だ」と言うものの、実際には駆け引きや交渉が含まれていることが多いため、言われた通りにすぐ信じてしまうのは危険だという教訓を示しているんだよ。

ああ、そういうことか。つまり、「商人の言う”元値”はすぐには信用できへん」ってことやな。
商人は商売のために色々な話をするから、元値を言われたときもそれが本当に元値かどうか、しっかりと自分で考えて判断することが大事やな。これは、物の値段を鵜呑みにせず、自分で考えて判断することの大切さを教えてくれてるんやな。
【類義語】
・商人の空値
・商人の泣き言
【スポンサーリンク】
「商人の元値」の解説
カンタン!解説

「商人の元値」っていうことわざは、商人が商品を販売するときには、どれくらいで仕入れたのか、本当の元の値段がどれくらいかっていうのはよく分からないんだよね。だから、客はその商人の言ってることを信じにくいっていう意味だよ。
つまりね、商人は商品を売るとき、もともとの値段より高く売ったりすることがあるんだ。でも、客はその元の値段を知らないから、商人が正直に言っているのか、もっと安いのに高く言っているのか分からない。だから、「本当にそれでいいの?」って疑問に思うことがあるんだ。
このことわざは、人の言葉や行動を鵜呑みにしないで、ちょっと疑ってかかる方がいいよ、って教えてくれているんだね。
「商人の元値」の使い方

商人の元値っていうけど、このアイスはもっと安くできるんじゃないかしら。

物価が高くなったからと言って、どんどん内容量が少なくなっているよね。
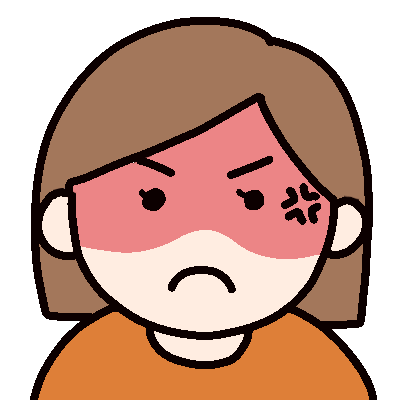
物価高のせいにしているだけで、絶対儲けてるわよ。

一部にはそういう企業もあるだろうね。
【スポンサーリンク】
「商人の元値」の例文

- 商人の元値という。限界価格という言葉に騙されないぞ。
- 商人の元値といわれるように、本当の所は客には分からないからこわい。
- 商人の元値という。商人はうそつきだと思って消費者が賢くならなければいけない。
- 商人の元値というが、これはもっと仕入れ値が安いはずだ。ぼったくり過ぎだろう。
- 商人の元値というけれども、大阪人は値切るから、最初から高めに設定しておかないと大変なんだ。