「門前の小僧習わぬ経を読む」の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳)

【ことわざ】
門前の小僧習わぬ経を読む
【読み方】
もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ
【意味】
いつも見たり聞いたりしていると、習わなくてもいつの間にか覚えるようになるというたとえ。


それはつまり、子供のころの環境が、その子の性格や知識に大きく影響するってことやな。なんてったって、経を読んでない小僧でも、毎日聞いてると経を覚えちゃうくらいやもんな。
【語源由来】
寺の門の前に住んでいる子供は、毎日お坊さんたちがお経を読むのを聞いているので、自然にお経を覚えてしまうということから。
【類義語】
・勧学院の雀は蒙求を囀る
【対義語】
・習わぬ経は読めぬ
【英語訳】
A saint’s maid quotes Latin.
「門前の小僧習わぬ経を読む」の解説

「門前の小僧習わぬ経を読む」っていう言葉はね、寺の近くに住んでいる子供や、お坊さんの近くにいる子供たちは、毎日お坊さんが読経を読んでいるのを聞いているから、気づかないうちに般若心経とかを読めるようになっちゃうことを表しているんだよ。
これはね、自分がいつもいる場所や、周りの環境から、自分でも気づかないうちに色々なことを学んでいるっていうことを教えてくれるんだ。
例えばね、お父さんが毎日料理をしている家に住んでいたら、自分でも気づかないうちに料理の作り方を覚えちゃうようなものだよ。自分がいつもいる場所や、見ているもの、聞いているものから、自分でも意識しないで色々なことを学んでいくんだね。
そしてね、このことわざは『江戸いろはかるた』という遊びの中にも出てくるんだよ。このカルタ遊びは、色々なことわざや教えを楽しみながら覚えることができるんだよ。
「門前の小僧習わぬ経を読む」の使い方




「門前の小僧習わぬ経を読む」の例文

- 母がいつも練習していたので、私も門前の小僧習わぬ経を読むようなもので、いつのまにかピアノを弾いていました。
- 門前の小僧習わぬ経を読むと同じように、少しながら私も囲碁が打てるようになりました。
- 健太くんはとても空手が強い。小さいときから、空手の先生をしているお父さんのそばで見ているうちに、自然に覚えたそうだ。まさに門前の小僧習わぬ経を読むだ。
- たいして練習もしていないのに、その技をよく習得できた。門前の小僧習わぬ経を読むとはたいしたものだ。
- 門前の小僧習わぬ経を読むとはいうものの、普段から心がけないとそう簡単にはいきません。









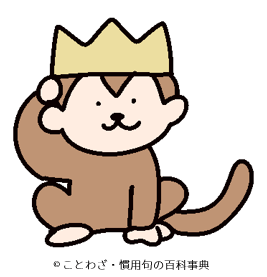

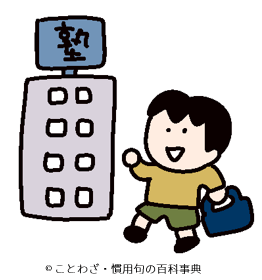
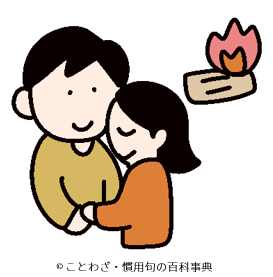


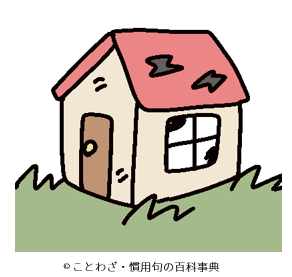






また、幼い頃に経験した環境が人格形成に大きな影響を与えるということを示しているんだ。