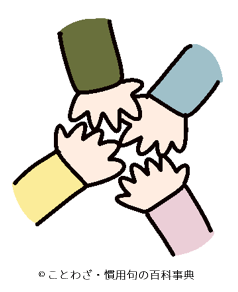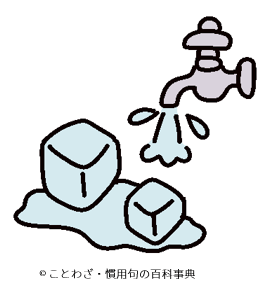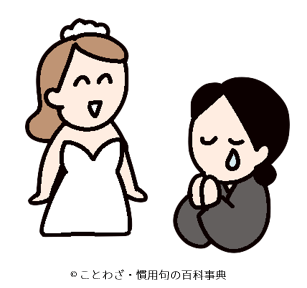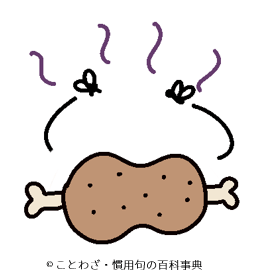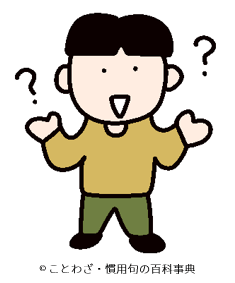【ことわざ】
六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わず
【読み方】
りくばわせざればぞうほももってとおきをいたすあたわず
【意味】
何事でも、ひとりひとりが心をひとつにして、協力しなければ、成し遂げることはできないということ。
【語源・由来】
「六馬(りくば)」とは、天子が乗るための馬車を引く六頭の馬のこと。
「造父(ぞうほ)」とは、周の穆王に仕えた名御者のこと。
【出典】
荀子「用兵の要は民衆を統一することにある」。
「弓矢調わざれば則(すなわ)ち羿(げい)も以(もっ)て微に中(あ)つる能(あた)わず。六馬和せざれば則ち造父も以て遠きを致す能わず」
弓矢がうまく調整されていなければ、羿のような弓の名人でも小さな的にあてることはできない。車を引く六頭の馬の気持ちが揃っていなければ、名御者の造父でも遠くまで馬車を走らせることはできないということから。
【英語訳】
What cannot be finished to the last, if people’s feeling is not set to one.
【スポンサーリンク】
「六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わず」の使い方

合唱コンクールの練習は、なかなかうまくいかないね。
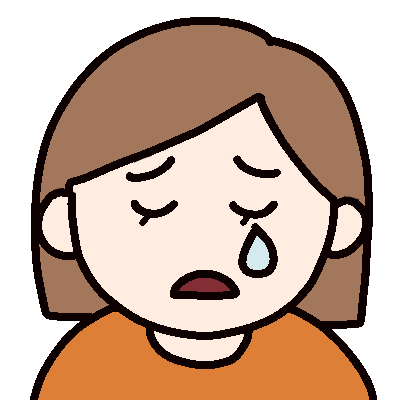
私の指揮が悪いのかしら。

いいや、ともこちゃんはとてもがんばっていると思うよ。みんなで心を合わせなきゃいけないよね。

六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずというものね。
「六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わず」の例文
- 六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずというように、この計画はとてもむずかしいものだ。
- この演劇はなんとしても成功させたいから、六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずということを忘れないで欲しい。
まとめ
六馬和せざれば造父も以て遠きを致す能わずということは、とてもむずかしいことかもしれませんね。
しかし、成し遂げることができるように、協力し合いたいものですね。