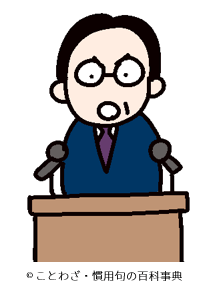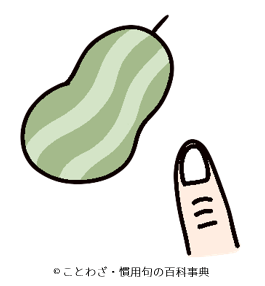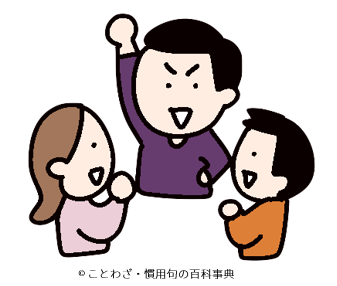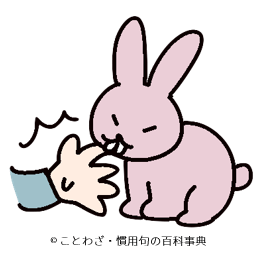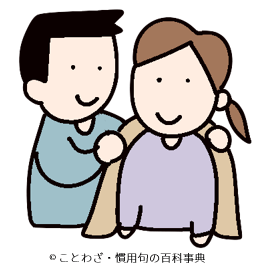「恨み骨髄に徹す」の意味(出典・英語訳)

恨み骨髄に徹す
【読み方】
うらみこつずいにてっす
【意味】
・心の底から非常に深く恨むこと。
・人を恨む気持ちが骨の奥までしみ通ること。


自分の骨の中まで恨みがしみ込んでるって、よっぽどのことやないとそんなことにはならへんやろうな。これは、深い怒りや恨みを表す強烈な言葉やな。
「史記」。故事(こじ)は難しいので簡単に説明すると、中国は春秋の時代、秦(しん)の将軍達がある国を攻め負けて捉えられます。将軍達を処刑しようとした国の王の母は秦の王の娘であったことから、「この将軍達に対して秦王の恨みは骨髄まで入っているので、いっそ解放して秦王に好きなようにさせた方がいいでしょう。」といい、将軍達は解放されます。秦王はこの将軍達には恨みどころか罪はなく、自分のミスであるとして、長くこの将軍達を重用(ちょうよう)したというお話です。
【英語訳】
Rancor sticks long by the ribs.(怨みは長くあばら骨にくっついている。)
「恨み骨髄に徹す」の解説
「恨み骨髄に徹す」っていうことわざはね、自分が感じている恨みや怒りが、体の一番奥深いところ、つまり骨の中心の髄までしみ込むほど深い、っていう意味なんだよ。
例えばね、仲良しの友達に大切な秘密を教えたけど、その友達が他の人にその秘密をバラしてしまった。その時の悔しさや怒りは、ちょっと時間が経ってもすぐには消えないよね。それを「恨み骨髄に徹す」って表現するんだ。
この表現は古代中国の歴史書「史記」から来ていて、とても深い恨みや悔しさを感じる時に使われるんだよ。つまり、このことわざは、感情がどれだけ強く、深く、長く続くかを表しているんだね。
「恨み骨髄に徹す」の使い方
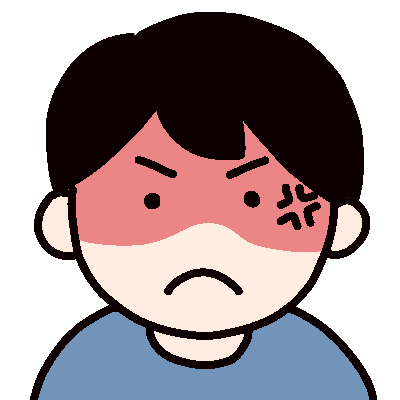

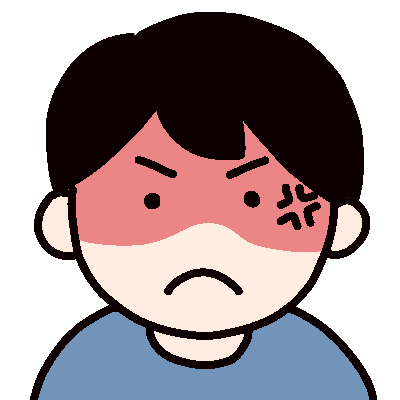

「恨み骨髄に徹す」の例文

- 明智光秀(あけちみつひで)が織田信長(おだのぶなが)を本能寺(ほんのうじ)で討ったのは恨み骨髄に徹していたからなのでしょうか。
- どんなに恨み骨髄に徹すといっても無実の市民を対象にしたテロ活動は許されるものではありません。
- 世界中の人が恨み骨髄に徹することを忘れれば、人が人を殺すことはなくなるのしょうか。
- 恨み骨髄に徹するとしても許す心を持つことが大切だとは分かっていても相手によります。
まとめ
法治国家ですから、恨み骨髄に徹する殺人事件でも罪は裁判により決定しそれに従うことが大切です。ただ犯罪を犯した方だけの人権を主張する活動にはどうも納得がいかないのは、お亡くなりになった人の人権については語られないからなのではないでしょうか。亡くなった方ですから人権を守る必要がないからでしょうか。難しい問題です。残された人達の恨み骨髄に徹する気持ちを癒やすのはどうすればいいのでしょうか。