「柔能く剛を制す」の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳)

柔能く剛を制す
【読み方】
じゅうよくごうをせいす
【意味】
柔軟なものが、そのしなやかさでかたいものの矛先をそらし、結局は勝つことになるというたとえ。
ときには、弱いものが強いものを倒すことがあるというたとえ。


柔軟な思考や行動が、硬い力に対して有利に働くこともあるんやね。力だけじゃなくて、どう対応するか、どう動くかが大事やってことや。柔らかさや機敏さが、時には強さよりも重要になるって教えてくれる言葉やね。
【語源・由来】
「軍しん」という、戦についての予言書から引用された句で、「三略」はそれに続けて、
「柔は徳で、剛は賊である。弱は人が助け、強は人が攻撃するものである」と説いている。
【出典】
「三略」「柔能く剛を制し、弱能く強を制す」とある。
【類義語】
・柳に雪折れなし
【対義語】
・堅い木は折れる
【英語訳】
Soft words win hard hearts.
「柔能く剛を制す」の解説

「柔能く剛を制す」ということわざは、「三略」の上略から来ていて、柔らかくてしなやかなものが、硬くて強いものを上手に制御して勝つという意味なんだよ。この言葉は、直接的な力ではなく、巧みさや柔軟性が最終的に勝利をもたらすことを表しているんだ。
たとえば、小さくても賢い動物が、大きくて力強い動物を賢さで上回るようなことがこれに当てはまるね。また、柔道などの武道で、相手の力を利用して勝つ技も「柔能く剛を制す」のいい例だよ。
このことわざは、物理的な力だけが強さではなく、状況に応じて柔軟に対応することや、賢さを使うことが重要だと教えてくれているんだね。力だけでなく、頭を使って物事を解決する方法も大切なんだよ。
「柔能く剛を制す」の使い方




「柔能く剛を制す」の例文
- 柔能く剛を制すというように、今回は強硬な手段は取らないほうがいいかもしれない。
- まさに柔能く剛を制すだね。あんなに小さな体で、身体の大きな選手に相撲で勝つなんて。
- 相手が大人しそうだからといって、侮ってはいけない。柔能く剛を制すということもある。
- 柔能く剛を制すとは、日本の柔道の極意だが、先日の試合は力負けをしてしまって残念だ。
- 小さいからといって、弱いと決めつけてかかったので、柔能く剛を制すで負けてしまった。
「柔能く剛を制すか、剛よく柔を制するか」
まとめ
柔道や相撲といった、体と体がぶつかり合うような試合では、体の大きな選手のほうが有利だと思うのではないでしょうか。
体が大きいことももちろん武器にはなりますが、それだけでなくしなやかさや柔軟さを鍛えることで、小さな体でも勝つことができるのではないでしょうか。
弱いと思ってあきらめずに、強いものにも挑戦したいですね。

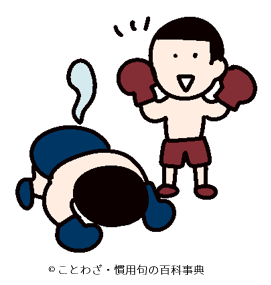








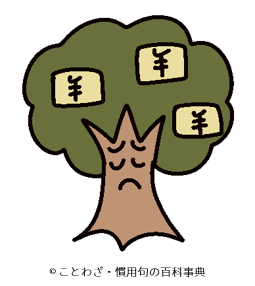

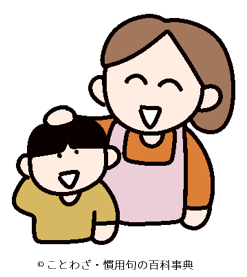
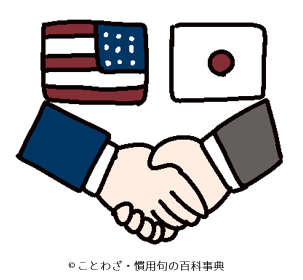
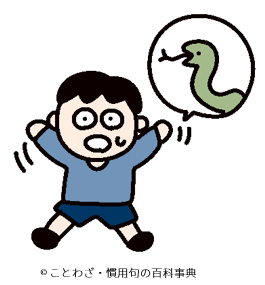

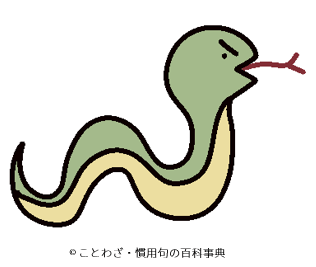





この言葉は、見かけ上弱いものが実際には強いものに勝ることがあるという教えを示しているんだね。柔軟性や機敏さが、硬直性や単純な力よりも有効であることを表しているんだ。